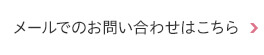コロナ不況と解雇
1.コロナ不況

新型コロナウイルスの感染拡大により、あらゆる業種で業績が悪化しています。
新型コロナウイルスの感染防止のための、都道府県知事からの休業要請、多くの市民が自宅で過ごして自粛することでお客が来店しないなど、多くの会社では、売上が減少し、資金繰りが厳しくなっています。
リーマンショックを超える不況の到来とも言われています。
不況になりますと、会社は、人件費を削減するために、労働者を解雇することがあります。
会社から支給される給料で生活している労働者にとって、解雇は、収入源を絶たれることになり、まさに死活問題です。
コロナ不況が到来することで、これから解雇が増えていくことが予想されます。
ここでは、労働者がコロナ不況で解雇された場合の対処法について解説します。
2.解雇
⑴解雇とは
解雇とは、労働者の意向にかかわらず、労働契約を終了させる、使用者の一方的な意思表示をいいます。
正社員である労働者がまだ働きたいと言っているのに、会社が、有無を言わさずに、労働契約を終了させて、労働者に仕事をさせず、給料も支払わなくなるのです。
⑵解雇権濫用法理
解雇されると、労働者は、生活の糧である給料を失い、生活に困窮するおそれがあります。
そのため、会社は、簡単に、労働者を解雇することができません。
会社は、可能な限り、解雇を回避して、雇用を維持すべき義務を負っているのです。
このことについて、労働契約法16条では、次のように規定されています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
労働者に解雇されるべき理由があり、解雇されてもやむを得ない場合に限って、はじめて解雇は有効になるのです。
これを解雇権濫用法理といいます。

⑶整理解雇
ア.整理解雇とは
新型コロナウイルス感染拡大の影響で会社の業績が悪化したことを理由に、労働者を解雇することを、整理解雇といいます。
いわゆるリストラです。
すなわち、会社の経営上の理由によって生じた人員削減の必要性に基づき、労働者を解雇するのが整理解雇です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で会社の業績が悪化したことについて、労働者には、全く落ち度がありません。
労働者に全く落ち度がないにもかかわらず、会社側の経営事情で解雇されてしまうので、裁判実務では、以下に述べる整理解雇の4要件(要素)に基づいて、整理解雇が有効か無効かが厳格に判断されます。
イ.整理解雇の4要件(要素)
整理解雇が有効か無効かを判断する要件(要素)として、次の4つが挙げられます。
①人員削減の必要性があること
②解雇回避努力を尽くしていること
③合理的な人選基準を立てて、これを適正に運用していること
④労働者・労働組合の納得を得られるように誠実に説明・協議を尽くしていること
この4つの要件(要素)について、詳しく解説します。
ウ.①人員削減の必要性があること
会社の経営状況が悪化し、経費削減の必要性が認められても、それが人員削減によって達成されなければならない程度に達していない場合や、人員削減以外の経費削減によって達成できる程度のものである場合には、人員削減の必要性は否定されます。
会社がどういった情報を集めて、どのような事実を認識し、その認識した事実に基づいて人員削減が必要との判断に至ったのかを確認することが重要になります。
人員削減の必要性の有無や程度の判断材料となる事情としては、会社の収支や借入金の状況、取引先との取引量の動向、資産状況、人件費や役員報酬の動向、社員の採用動向、業務量、株式配当などが挙げられます。
エ.②解雇回避努力を尽くしていること
会社は、雇用を保障する観点から、企業規模や経営状態など具体的事情のもとにおいて、整理解雇を避けるために、できる限りの措置を講じなければならないのです。
具体的には、経費削減、役員報酬の削減、残業規制、新規採用の停止縮小・中途採用や再雇用の停止、従業員に対する昇給停止や賞与の減額・不支給、配転・出向・転籍の実施、ワークシェアリングによる時短勤務や一時帰休、非正規雇用労働者との間の労働契約の解消、希望退職者の募集、などが挙げられます。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響をふまえて、国は、雇用調整助成金の受給要件を緩和し、受給金額を拡充しています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業などを行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、国が事業主に対して、休業手当や賃金などの一部を助成するものです。
都道府県知事からの営業自粛要請を受けて、会社が自主的に休業し、事業活動が縮小した場合、会社は、雇用調整助成金を活用して、休業期間中、労働者に対して、賃金の全額、若しくは、平均賃金の6割以上の休業手当を支払って、雇用を維持すべきです。
コロナ不況において、雇用調整助成金を活用することなく、会社が整理解雇を実施した場合、解雇回避努力を尽くしていないと判断されると考えられます。
オ.③合理的な人選基準を立てて、これを適正に運用していること
整理解雇の対象者を誰にするかという人選は、恣意的なものであってはならず、客観的で合理的な基準を設定し、その基準を適正にあてはめて運用していることが必要となります。
具体的な整理解雇の対象者の選定基準としては、
勤務態度の優劣(欠勤日数、遅刻回数、規律違反歴など)、
労務の量的貢献度の多寡(勤続年数、休職日数など)、
労務の質的貢献度の多寡(過去の実績、業務に有益な資格の有無など)、
雇用形態(正社員か非正規雇用労働者か)、
労働者側の事情(年齢、家族構成、共稼ぎか否かなど) が挙げられます。
カ.④労働者・労働組合の納得を得られるように誠実に説明・協議を尽くしていること
整理解雇に先立ち、会社は、労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性とその内容(時期・規模・方法)、人選基準などについて、十分な説明を行い、誠意をもって協議しなければなりません。
単に、「○億円の赤字だから解雇せざるをえない」などと概括的な数字を掲げるだけでは、説明義務を尽くしたとはいえません。
3.解雇の対処法
会社から、ある日突然、解雇を通告された場合、労働者としては、どのように対処すればいいのかについてまとめました。
⑴解雇であることを確認する
会社から、本当に解雇されたのかを確認する必要があります。
解雇通知書などの文書が交付されていれば、解雇であることは明らかですが、社長から「辞めてくれないか」と口頭で言われたことを解雇と早合点してしまう労働者がいらっしゃいます。
「辞めてくれないか」というのは、退職勧奨という、会社からのお願いなので、労働者が会社を辞めたくないのであれば、退職勧奨に応じる必要はなく、きっぱりと断ればいいのです。
退職勧奨を受けただけなのに、解雇されたと早合点して、会社にいかなくなると、無断欠勤を理由に解雇されるなど、予期せぬ事態が生じることがありますので、注意が必要です。
口頭による解雇通告の場合、解雇の意思表示があったといえるかが微妙なことがあります。
そのような場合には、発言の内容や、会話の前後の状況などを勘案して、解雇の意思表示があったのかを判断していきます。

⑵解雇理由を特定する
労働者が解雇を争う場合、会社が主張する解雇理由を一つ一つ論破していきます。
会社が主張する解雇理由を論破していくためには、会社が主張している解雇理由が明確になっていなければなりません。
そのため、会社が主張する解雇理由を特定させることが不可欠です。
解雇理由を特定させるためには、会社に対して、解雇理由を文書で明らかにさせることが重要です。
会社は、労働者から求めがあった場合には、遅滞なく、解雇理由証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条)。
労働者が請求しても、会社が解雇理由証明書を交付しない場合、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科せられることがありますので、労働基準監督署に法違反の申告をして、解雇理由証明書を交付させることを検討します。
会社から交付される解雇理由証明書には、「能力不足」、「協調性の欠如」など抽象的な解雇理由しか記載されていないことが多いです。
抽象的な解雇理由しか記載されていない場合には、会社に対して、どのような能力がどのように不足しているのか、協調性の欠如として、どのようなことがあったのか、などの具体的な解雇理由を明らかにするように求めます。
⑶解雇無効の主張と就労意思の表明
解雇が無効となった場合、労働者は、会社に対して、解雇されて会社で働いていなかった期間の未払賃金を請求できます。
この未払賃金を請求するためには、労働者は、会社に対して、労務提供の意思と能力があることを示す必要があります。
そのため、労働者は、会社に対して、「解雇は無効なので、就労させるように請求します。」などと記載した文書を配達証明付内容証明郵便で送付します。
解雇された会社に戻りたくなかったとしても、未払賃金を請求するために、会社に対して、解雇無効の主張と就労意思を表明する文書を送るべきです。
⑷解雇を前提とした行動をしない
会社に対して、解雇が無効であるとして争う場合、退職を前提とした行動をとるべきではありません。
労働者が退職を前提とした行動をとると、解雇無効の主張と矛盾することになり、会社から、解雇とは別の労働契約の終了原因を主張されて、争点が増えて、労働者に不利になるからです。
ア.退職金や解雇予告手当を請求しない
退職金は、労働者が会社を辞めることを前提に支払われるものですので、労働者が、退職金を請求することは、自分から会社を辞めることを認めることにつながりますので、解雇無効の主張と矛盾するリスクがあります。
また、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、30日前に予告をしない会社は、労働者に対して、30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条)。
労働者が会社に対して、解雇予告手当を請求することは、労働者が就労意思を喪失したと判断されるリスクがあります。
そのため、解雇を争う場合には、労働者から、会社に対して、退職金や解雇予告手当を請求しないようにしてください。
もっとも、労働者が請求していないのに、会社が、労働者の給料口座に、退職金や解雇予告手当を振り込んできた場合には、振り込まれた退職金や解雇予告手当を未払賃金に充当することを文書で会社に伝えれば、問題ありません。
イ.離職票の受領と健康保険証の返却は問題ない
労働者が会社を解雇された場合、次の就職が決まるまで、無職となり、収入がなくなるので、雇用保険の失業給付を受給することになります。
雇用保険の失業給付を受給するためには、離職票をハローワークに提出する必要があります。
生活のために失業給付の受給が必要ですので、会社に対して、離職票の交付を求めても、解雇無効の主張と矛盾することにはなりません。
また、解雇された場合、会社から健康保険証の返却を求められることが多いのですが、労働者が会社に健康保険証を返却しても、解雇無効の主張と矛盾することにはなりません。
⑸再就職
解雇が無効であると争い、解雇した会社に戻りたい場合でも、解雇を争う裁判をしているうちに時間が経過することがよくあります。
解雇された労働者が、解雇を争っている期間中、ずっと無職でいると、生活ができないので、生活のために、その期間、他の会社に就職して収入を得ても、労働者の就労の意思が問題とされることはほとんどありません。
そのため、解雇を争っている期間中に再就職をしても、特に問題はありません。

⑹雇用保険の失業給付
解雇されて給料が支払われなくなり、当面の生活を維持するために、もっとも利用されているのは雇用保険の失業給付です。
雇用保険は、労働者を雇用している全ての事業に適用されますので、事業主が届出や保険料納付の手続を怠っていたとしても、労働者は、失業給付を受けられます。
失業給付の受給資格については、離職前2年間に通算して12ヶ月以上、被保険者(適用事業に雇用されている労働者)であったことが必要ですが、解雇の場合、特定受給資格者として、離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者であればよいことになり、有利に取り扱われます。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は、原則として、離職した日の直前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となります。
雇用保険で失業給付を受給できる日数のことを所定給付日数といいます。
所定給付日数は、被保険者として雇用された期間や年齢によって区分され、雇用された期間が長いほど、所定給付日数は増えます。
解雇された特定受給資格者は、所定給付日数が長く認められます。
失業給付の受給期間は、原則として、離職の日から1年以内となっています。
解雇された労働者が失業給付を受給するためには、会社から交付される離職票をハローワークに提出して、失業の認定を受けます。
会社から送られていた離職票に記載されている賃金額や離職理由に誤りがないか、ハローワークに離職票を提出する前に、離職票の記載内容をよく確認するようにしてください。
4.解雇を争う手続
⑴交渉
弁護士は、クライアントから依頼を受けた場合、いきなり法的手段を採ることは少なく、まずは、会社に通知書を送付するなどして、会社や会社の代理人弁護士との間で交渉を行います。
クライアントの要求と、相手方の要求をすり合わせて、互いに譲歩できる余地があれば、解決点を探り、話し合いで事件を解決することも多いです。
裁判手続はどうしても時間がかかってしまいますが、交渉ですと、短期間で解決でき、当事者双方にとって、時間と手間を省けるメリットがあります。
もっとも、交渉による話し合いでは、妥協点がみつからない場合もありますので、そのようなときには、交渉から裁判手続へ移行します。
⑵通常訴訟
通常訴訟とは、地方裁判所に裁判を提起することです。
解雇が無効である場合には、労働者は、解雇後も労働契約上の権利を有していることになるので、労働契約上の権利を有する地位の確認を請求します。
また、解雇されて以降、未払になっている賃金については、無効な解雇を行った会社は、労働者に賃金を支払わなければならないので、労働者は、会社に対して、未払賃金の請求をします。
提訴してから判決がでるまでは、通常1年以上かかることが多いです。
判決までいかなくとも、裁判手続の途中で、和解で解決することもあります。
労働者の復職意思が強い場合や、会社が和解に応じる可能性が低い場合に採ることが多い手続です。
⑶労働審判
労働審判は、次の4つの特徴がある裁判手続です。
①調停(合意による解決)を試みるとともに、調停が成立しない場合には、原則として3回以内の期日で労働審判(裁判所の判断)を出すこと
②労働審判手続は、1人の裁判官と労働関係について専門的な知識経験を有する労使各1名の審判員から構成される労働審判委員会によって行われること
③裁判所が労働審判を出して、当事者から異議が出なかった場合、労働審判は裁判上の和解と同じ効力を有すること
④労働審判は、当事者から異議が出された場合にはその効力を失いますが、新しく訴訟提起しなくても、労働審判の申立時に地方裁判所に訴訟提起があったものとみなされること
労働審判は、申立から3カ月程度で結論が出され、話し合いによる柔軟な解決が図られます。
解雇をされたので、前の職場に復帰したくはないが、会社に対して金銭請求をしたい場合に採ることが多い手続です。
⑷仮処分
通常訴訟の結果が出る前に、仮に労働契約上の権利を有する地位を定めたり、仮に賃金の支払を認めるのが、仮処分という裁判手続です。
仮処分は、申立から2~3カ月から6カ月程度で結論を得られることが多く、通常訴訟に比べて手続が早く進みます。
また、仮処分手続の中で和解が成立することも多く、仮の手続とはいえ、最終的な紛争解決も可能です。
もっとも、仮処分では、通常訴訟では求められることのない、保全の必要性が求められます。
保全の必要性とは、仮処分がされないことによって生じる労働者の不利益が著しく大きいことをいいます。
労働契約上の権利を有する地位を仮に定める地位保全仮処分の場合、労働者の他からの収入の有無、再就職の難易、労働者としての地位がないことによる著しい不利益等が考慮されます。
賃金の仮払いを求める賃金仮払い仮処分の場合、労働者の他からの固定収入の有無、資産の有無、同居家族の収入の有無等が考慮されます。
裁判所は、保全の必要性を厳しく検討してきますので、緊急を要し、労働審判や通常訴訟による解決を待っているのでは、労働者の不利益が大きい場合に、仮処分の手続を採るかを検討します。

5.弁護士にご相談を
労働者が解雇されますと、なぜ自分が解雇されなければならないのかという疑問や、明日からの生活をどうすればいいのかという不安など、大変辛い状況に追い込まれてしまいます。
このまま解雇を受け入れるしかないのか、会社と争ったら何か請求できるのか、様々な葛藤が生じます。
解雇されて悩んでいる場合には、弁護士にご相談ください。
相談者がもとの会社に復職したいのか、復職せずに金銭請求したいのか、早期解決を求めるのか、会社はどのような対応をしてくるのか、どのような証拠があるのか、などを総合考慮して、どのような法的手段で事件を解決すべきかを検討し、アドバイスします。
解雇事件が解決に至る筋道がみつかるかもしれませんので、弁護士にご相談することをおすすめします。