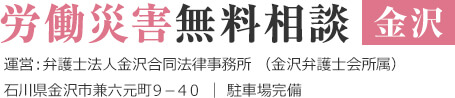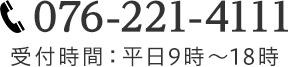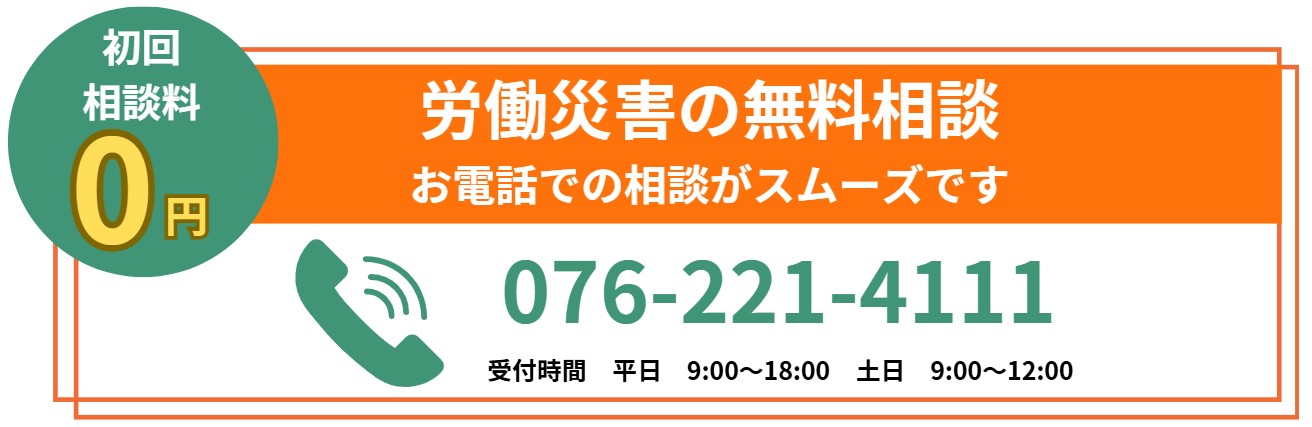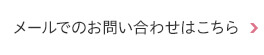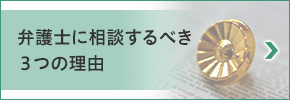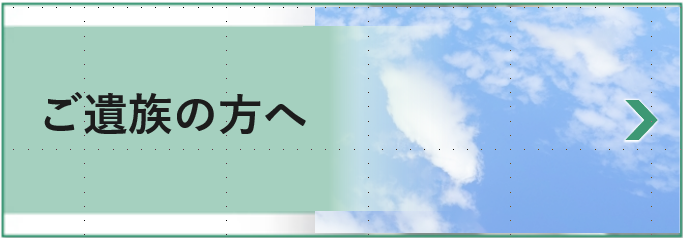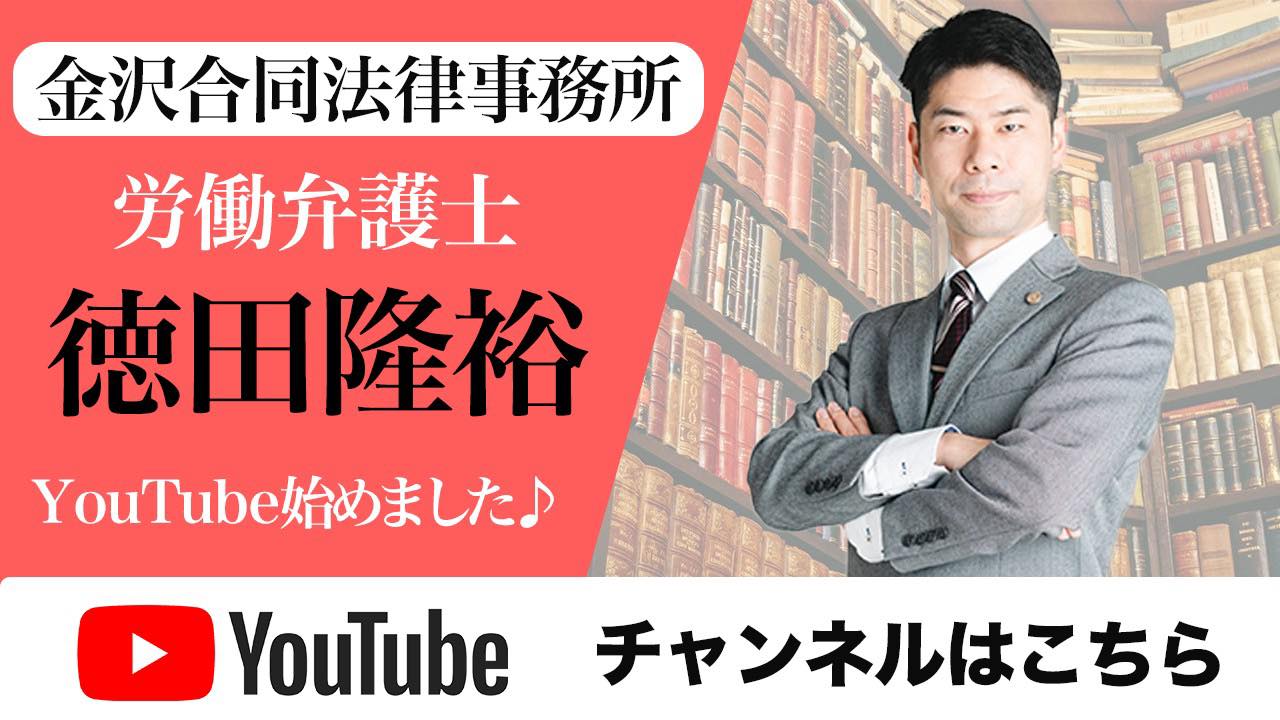労災の後遺障害の等級認定を適正化するポイント【弁護士が解説】
建設現場で仕事をしていたところ、高いところから転落してしまい、足を骨折してしまいました。
足首の関節の曲げ伸ばしがうまくいかず、痛みも残っています。
主治医からは、後遺障害が残るかもしれないと言われています。
労災事故において、後遺障害が残った場合、何か補償はないのでしょうか。
結論から先に言いますと、労災保険の障害補償給付の申請をして、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた、年金若しくは一時金が支給され、今後の生活が一定程度安定します。
今回は、労災保険における後遺障害について、分かりやすく解説します。

1 労災の後遺障害とは?
労災事故に巻き込まれて、けがを負った場合、労災保険を利用すれば、労災保険から治療費が全額支給されます。
また、労災事故のけがの治療のために、会社を休業することになったとしても、労災保険から、給料の約80%の補償金が支給されます。
このように、労災保険を利用して、労災事故のけがの治療をしていると、現代の医学では、これ以上、けがの症状が改善されない状態をむかえます。
これ以上、けがの治療をしても、症状がよくならない状態になったことを、症状固定といいます。
そして、症状固定の時点において、残っている症状のことを後遺障害といいます。
すなわち、労災事故が発生する前と比較して、労働者にとって悪しき症状が残っており、以前と同じように働くことが困難な状態になっていることを、後遺障害といいます。

2 労災の後遺障害認定手続きの流れ
⑴ 労災保険の障害補償給付
後遺障害が残ると、通常、労働者の労働能力が低下します。
そして、労働能力が低下すれば、以前と同じように働くことが困難となり、収入が減少します。
この後遺障害による収入の減少に対する補償が、労災保険の障害補償給付です。
労災事故によるけがが後遺障害と認定された場合、労災保険から、後遺障害の等級に応じた、年金若しくは一時金が支給されます。
後遺障害による補償を受けることによって、被災労働者の今後の生活が、一定程度安定することになります。
そのため、労災事故によるけがについて後遺障害が残った場合には、必ず、労災保険の障害補償給付の申請をしてください。
⑵ 主治医に後遺障害の診断書を作成してもらう
ここから、労災において、後遺障害と認定されるための手続きの流れを説明します。
まずは、主治医から、症状固定と言われましたら、主治医に、労災保険の後遺障害の診断書を書いてもらいます。
労災保険の後遺障害の診断書は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
痛みだけの症状を主治医に伝えていて、関節がうまく曲げ伸ばしできないことを主治医に伝えていない場合、関節の可動域制限が後遺障害の診断書に記載してもらえない可能性があります。
そのため、主治医に対して、ご自身の残存している症状について、しっかりと伝え、漏れがないように、後遺障害の診断書を作成してもらいましょう。
⑶ 労災保険の様式第10号の請求書を労働基準監督署へ提出する
主治医に、後遺障害の診断書を作成してもらったら、次に、労災保険の様式第10号の障害補償給付支給請求書を作成します。
労災保険の様式10号の請求書は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
この請求書の「災害の原因及び発生状況」の欄に、労災事故にあった時の状況を、具体的に正確に記載するようにしてください。
労災保険の様式10号の請求書が完成したら、労働基準監督署へ提出します。
⑷ 労働基準監督署による調査
労働基準監督署は、労災保険の様式10号の請求書を受理した場合、カルテを検討し、主治医や労災医員の医師に意見照会をして、被災労働者に残存している悪しき症状が後遺障害と認定できるかを調査します。
労働基準監督署が後遺障害と認定して、障害補償給付の支給をするまでに、概ね3ヶ月ほどかかります。
⑸ 障害補償給付の支給
労働基準監督署の調査の結果、被災労働者に残存している悪しき症状が後遺障害と認定されますと、労災保険から、障害補償給付が支給されます。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、後遺障害と認定されたか否か、後遺障害の等級は何級なのか、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
障害補償給付の支給決定の通知と共に、労動者が、労災保険の様式10号の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。
3 労災保険の障害補償給付の支給金額
労災事故によるけがが後遺障害と認定された場合、労災保険から、障害補償給付として、後遺障害の等級に応じて、年金若しくは一時金が支給されます。
後遺障害が1級から7級までは、年金が支給され、8級から14級までは一時金が支給されます。
年金の支給は、原則として、対象者が死亡するまで継続しますので、7級と8級とでは、トータルで受給できる補償金額に大きな差が生じます。
⑴ 後遺障害1級から7級
後遺障害1級から7級に該当した場合、労災保険から、障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給されます。
後遺障害1級から7級の場合の補償金額は、以下のとおりです。
|
<障害等級第1級から第7級の場合> |
|||
|
障害等級 |
障害(補償)年金 |
障害特別支給金※ |
障害特別年金 |
|
第1級 |
給付基礎日額の |
342万円 |
算定基礎日額の |
|
第2級 |
給付基礎日額の |
320万円 |
算定基礎日額の |
|
第3級 |
給付基礎日額の |
300万円 |
算定基礎日額の |
|
第4級 |
給付基礎日額の |
264万円 |
算定基礎日額の |
|
第5級 |
給付基礎日額の |
225万円 |
算定基礎日額の |
|
第6級 |
給付基礎日額の |
192万円 |
算定基礎日額の |
|
第7級 |
給付基礎日額の |
159万円 |
算定基礎日額の |
給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものをいいます。
算定基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前1年間の賞与を365日で割って得られたものをいいます。
⑵ 後遺障害8級から14級
後遺障害8級から14級に該当した場合、労災保険から、障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。
これらは、一時金なので、支給は1回のみです。
後遺障害8級から14級の場合の補償金額は、以下のとおりです。
|
<障害等級第8級から第14級の場合> |
|
||
|
障害等級 |
障害(補償)一時金 |
障害特別支給金※ |
障害特別一時金 |
|
第8級 |
給付基礎日額の |
65万円 |
算定基礎日額の |
|
第9級 |
給付基礎日額の |
50万円 |
算定基礎日額の |
|
第10級 |
給付基礎日額の |
39万円 |
算定基礎日額の |
|
第11級 |
給付基礎日額の |
29万円 |
算定基礎日額の |
|
第12級 |
給付基礎日額の |
20万円 |
算定基礎日額の |
|
第13級 |
給付基礎日額の |
14万円 |
算定基礎日額の |
|
第14級 |
給付基礎日額の |
8万円 |
算定基礎日額の |
⑶ 後遺障害10級の場合に障害補償給付としていくら支給されるのか
ここで、後遺障害の第10級の10の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当した場合で、いくらの補償が受けられるのかを検討してみます。
後遺障害10級の場合、障害補償給付として、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。
10級の場合、①障害補償一時金は、給付基礎日額の302日分が支給されます。
10級の場合、②障害特別一時金は、算定基礎日額の302日分が支給されます。
10級の場合、③障害特別支援金は、39万円が支給されます。
具体的なケースで、10級の障害補償給付の金額を計算してみます。
毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円の労働者が10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害10級と認定されたケースで、障害補償給付の金額を計算すると、次のとおりとなります。
①障害補償一時金
まずは、直近3ヶ月間の給付基礎日額を計算します。
7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,782.6
1円未満の端数は、1円に切り上げるので、給付基礎日額は、9,783円となります。
10級の場合、障害補償一時金は、給付基礎日額の302日分が支給されますので、9,783円×302日=2,954,466円となります。
②障害特別一時金
まずは、直近1年間の算定基礎日額を計算します。
1年間の賞与が60万円なので、365日で割ると、60万円÷365日=1,643.8となり、1円未満の端数は1円に切り上げるので、算定基礎日額は、1,644円となります。
10級の場合、障害特別一時金は、算定基礎日額の302日分が支給されますので、1,644円×302日=496,488円となります。
③障害特別支援金
10級の場合の障害特別支援金は、39万円です。
以上を合計すると、2,954,466円(①障害補償一時金)+496,488円(②障害特別一時金)+39万円(③障害特別支援金)=3,840,954円となります。
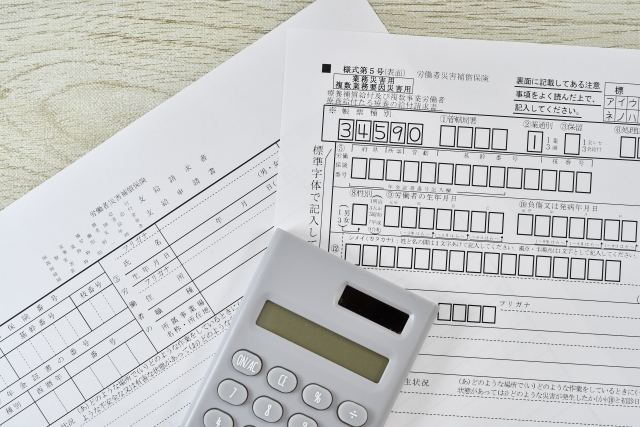
4 後遺障害と認定されなかった場合の対処法
労災事故によるけがについて、障害補償給付の申請をしたものの、労災の後遺障害の認定基準に該当しなかった場合、けがや病気と労災事故との因果関係が認められなかった場合、後遺障害が認定されないことがあります。
また、後遺障害と認定されたものの、想定していた後遺障害とは異なり、低い等級で後遺障害と認定されることもあります。
このように、労働基準監督署の後遺障害の認定に納得がいかない場合、不服申立ての制度があります。
⑴ 審査請求
労働基準監督署の後遺障害の認定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、労動者災害補償保険審査官に対して、審査請求をすることができます。
この審査請求において、労働基準監督署の後遺障害の認定に誤りがあると認められれば、労働基準監督署の決定が取り消され、新たに、後遺障害の認定がなされます。
⑵ 再審査請求
審査請求において、結論が変わらなかった場合、審査請求の決定に不服があれば、審査請求の決定書が送付された日の翌日から2ヶ月以内に、労働保険審査会に対して、再審査請求ができます。
再審査請求でも、後遺障害の判断が変わらなかった場合には、裁判所に対して、取消訴訟を提起することになります。
一般的に、労働基準監督署がくだした判断を覆すのは容易ではなく、審査請求を検討する場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

5 弁護士の後遺障害申請サポート
労災の後遺障害では、適正な等級認定を受けることが重要になりますところ、弁護士に、後遺障害の等級認定のサポートを依頼することで、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
労災の後遺障害の等級認定では、主治医の後遺障害の診断書が重要になります。
もっとも、医師は、治療については、専門家ではありますが、後遺障害について、専門的な知識を有しているとは限りません。
主治医が、後遺障害の専門的な知識を有しておらず、後遺障害の診断書に記載漏れがあった場合、適正な後遺障害の等級認定が受けられないリスクがあります。
そこで、後遺障害の専門的な知識を有する弁護士が、被害者と共に、主治医と面談をして、後遺障害の診断書に漏れなく、必要な事項を記載してもらうように、主治医に依頼をすることで、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
また、労災の後遺障害では、関節の可動域制限が見過ごされる可能性があります。
例えば、肩関節の可動域が、健康な肩の可動域と比較して、4分の3以下に制限されていれば、12級の後遺障害に該当し、2分の1以下に制限されていれば、10級の後遺障害に該当します。
主治医が可動域制限を見過ごしてしまった場合、12級や10級の後遺障害の等級認定を受けられないリスクがあります。
弁護士が、主治医に対して、可動域制限の測定を依頼することで、可動域制限の見過ごしを回避することができます。
そして、被害者が、自身の症状である痛みやしびれ、日常生活で不自由をしていること、労働能力が低下したことなどを、労働基準監督署に対して、正確に伝える必要があります。
弁護士は、被害者から、症状や日常生活での不自由さ、労働能力の低下について、必要な聞き取りをし、自己申告書という資料の作成のサポートをして、労働基準監督署に対して、被害者の現状を正確に伝えます。
このように、後遺障害の等級認定のサポートを弁護士に依頼することで、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
当事務所では、後遺障害の等級認定のサポートに力をいれておりますので、労災の後遺障害でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。