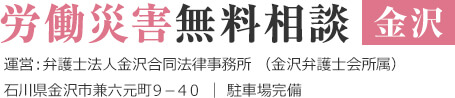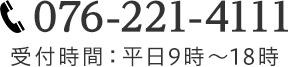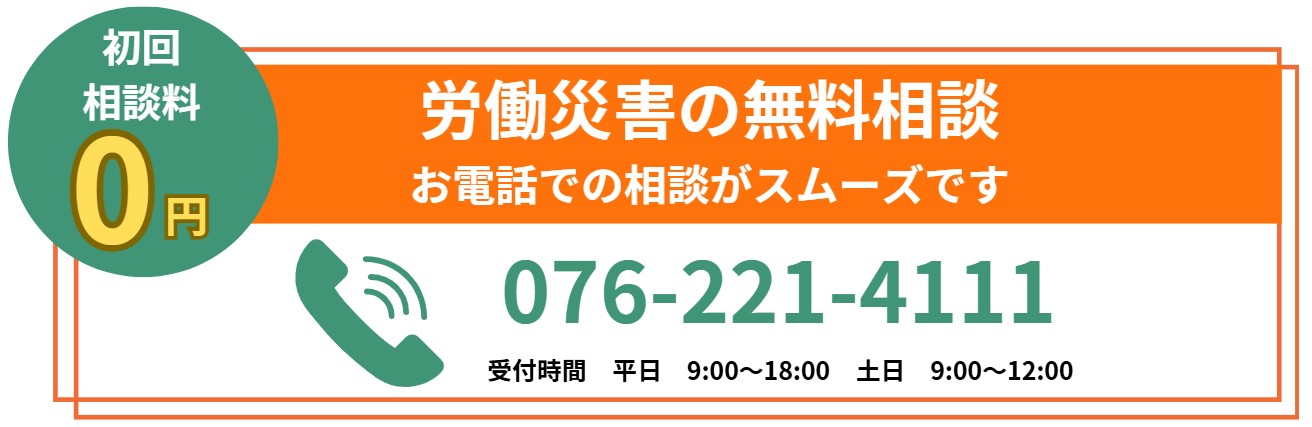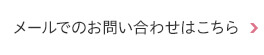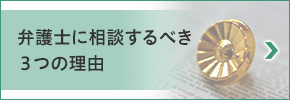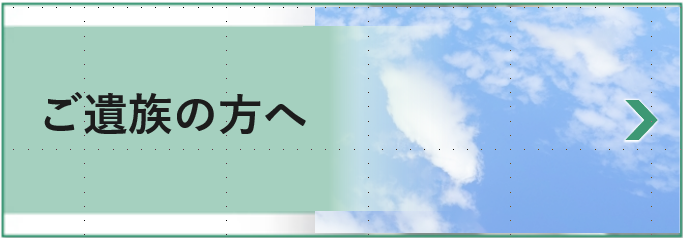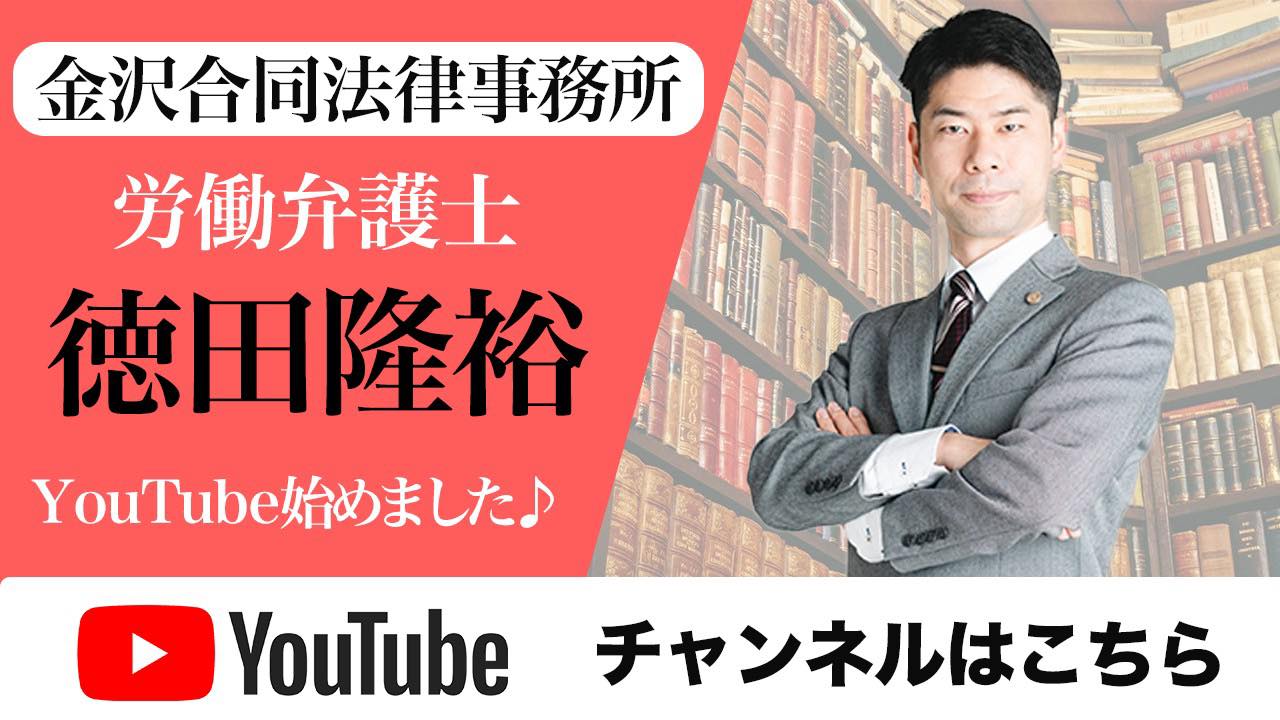労災の休業補償の手続きと注意点!給付期間や申請手続きの流れを弁護士が解説
仕事中にケガをしてしまい、長期間、会社を休むことになりました。
会社を休んでいる期間、給料が支払われないので、今後の生活が不安です。
労災事故にまきこまれて、長期間、休業する場合、何か補償はあるのでしょうか。
労災が発生した場合、休業時の収入をカバーする制度として労災保険による休業補償給付があります。
本記事では、休業補償給付の制度の概要や給付期間、申請の手続き、受給の際の注意点などをわかりやすく解説します。
さらに、申請の流れや事業主とのやりとりにおいて気をつけるべきポイントにも触れ、労働者が不利にならないよう手続きを進めるための情報を提供します。
万が一のトラブルを回避するために、ぜひ最後までご覧いただき、必要なときに適切な行動が取れるよう備えておきましょう。

1.労災の休業補償とは
労災が原因で労働ができず賃金を受けられなくなったときに支給されるのが休業補償です。
労災による負傷や疾病が原因で仕事を休まざるを得ない場合、労災保険から休業補償が支給されます。
この給付によって、休業が長期間にわたったとしても、ある程度の収入が確保される点が大きなメリットです。
年次有給休暇を使わずに欠勤しても,治療費とは別に給付金を受け取れるので、休業期間も安心して治療を受け続けることができます。
支給対象者は、業務や通勤が原因で生じた負傷または病気が理由で休業し、賃金の支払いを受けられない労働者です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用であっても、雇用形態にかかわらず、休業補償を受給できます。
1‐1 休業補償給付と休業給付
仕事中に怪我をした場合、業務災害となります。
業務災害と認められるためには、業務遂行生が認められることを前提に業務起因性が認められる必要があります。
業務遂行性とは、労働者が会社の支配下にある状態をいいます。
労働者が業務に従事している最中はもちろんのこと、業務に従事していなくても、休憩時間中など、会社が指揮監督を行いうる余地があって、その限りで会社の支配下にある場合、原則として業務遂行性があるとされます。
業務起因性とは、業務に内在する危険が現実化したものによると認められることをいいます。
すなわち、会社の業務と労働者の怪我や病気の間に、社会通念上相当な因果関係があることをいいます。
業務災害に該当すれば、休業補償給付を受給できます。
仕事へ通勤する道中に事故に巻き込まれて怪我をした場合、通勤災害となります。
通勤災害に該当すれば、休業給付を受給できます。
1‐2 休業補償の要件
休業補償は、治療を受けている労働者が、休業しなければならない状態である場合に、休業開始4日目から支給を受けることができます。
休業補償を受給するためには、次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
①労災事故によるけがのために治療をしていること
②治療のために働くことができないこと
③賃金を受けていないこと
働くことができないとは、一般に労働できない場合をいい、軽作業であれば働ける場合は、これに当てはまらないとされています。
治療が終了したり、給料を受給できるようになると、休業補償を受給することができなくなります。
下記にて労災発生後から労災申請の手続きまでの流れについて解説しておりますので、合わせてご覧ください。

2.休業補償のポイント
休業補償を受けるにあたって知っておきたい、計算方法や年次有給休暇との関係、申請手続きなどのポイントを確認します。
具体的な計算方法や手続きフローを理解すれば、実際の休業時に混乱せずにすむでしょう。
2-1.休業補償の計算方法について具体例をもとに解説
休業補償によって支払われるのは、賃金の全額ではありません。
「休業補償給付」が給付基礎日額(労災事故発生日の直前3ヶ月間の賃金を日割り計算した平均賃金)の60%、「休業特別支給金」が給付基礎日額の20%、合計で賃金の80%相当の金額しか支払われません。
ようするに、会社を休んでいても、労災保険から、給料の約80%分が支給されるのです。
それでは、休業補償として、具体的にいくらの補償を受給できるのかを計算してみます。
3ヶ月間の給料の合計額が777,533円、3ヶ月の総日数92日、労災事故が発生してから30日間休業したケースで、休業補償給付の金額を計算してみます。
まず、労災事故が発した日以前3ヶ月間に、労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額である、給付基礎日額を計算します。
777,533÷92=8,451.44
給付基礎日額を計算する際、1円未満の端数は1円に切り上げて計算します。
そのため、給付基礎日額は、8,451+1=8,452円となります。
次に、休業補償給付金は、給付基礎日額の60%、休業特別支給金は、給付基礎日額の20%が支給されるので、次のように計算します。
休業補償給付金 8,452×60%=5,071.2
休業特別支給金 8,452×20%=1,690.4
1日当たりの休業補償給付の金額の1円未満の端数は切り捨てになるので、休業補償給付金は、1日当たり5,071円、休業特別支給金は、1日当たり1,690円となります。
その結果、1日当たりの休業補償給付の金額は、5,071+1,690=6,761円となります。
そして、休業補償給付は、休業4日目から支給されるので、30日間休業しても、30日-3日=27日分しか支給されないことになります。
よって、今回のケースでは、支給される休業補償給付の金額は、6,761×27=182,547円となります。
2-2.年次有給休暇との関係
休業補償を受給できるケースでも、「年次有給休暇」を使うことは可能です。
休業補償からは賃金の約80%までしか支給されないので、年次有給休暇によって100%の賃金をもらえればメリットはあるといえます。
もっとも,休業補償の対象日を年次有給休暇として扱ってしまうと,休業補償の支給対象外になってしまうので,年次有給休暇を利用するのか,労災の休業補償を利用するのかを,よく検討する必要があります。
年次有給休暇を取得した場合、その年度において、年次有給休暇を取得しようとしても、年次有給休暇が残っておらず、休めなくなったり、治療のために、休業期間が長くなる場合、年次有給休暇が足りなくなるリスクもありますので、労災保険の休業補償を取得することをおすすめします。
2-3.申請方法
休業補償を請求するタイミングですが、1ヶ月ごとに請求するのが一般的です。
休業補償を受給したいときには以下のように進めましょう。
会社へ報告
まずは労災事故が発生したことを会社に報告します。労災保険の様式8号の文書を作成して会社に証明をもらいましょう。
もっとも、会社が証明を拒否してきても、そのことを労働基準監督署に伝えれば、労働基準監督署は労災申請を受理してくれますので、問題はありません。
病院で診察を受ける
病院に行って診察と治療を受け、労災保険の様式8号の文書に証明をもらいます。
労働基準監督署へ労災保険の様式8号の文書を提出する
作成した休業補償給付の申請書を労働基準監督署に提出します。その後,労働基準監督署の審査があり、給付の決定があれば、休業4日目から休業補償給付が支給されます。
なお、休業補償給付の申請の際に使用する、労災保険の様式8号の文書については、こちらの厚生労働省のホームページから入手できます。
また、休業補償給付については、こちらの厚生労働省のパンフレットが、大変参考になります。
2-4.退職した場合
労災事故にまきこまれた際に勤務していた会社を退職した後であっても、被災した労動者が、休業補償の要件を満たしているならば、引き続き、休業補償を受給することができます。
退職後に休業補償の請求をする際、勤務先の会社の証明は不要になります。
会社を退職したら、休業補償を受給できなくなるのではないかと不安になる必要はありません。
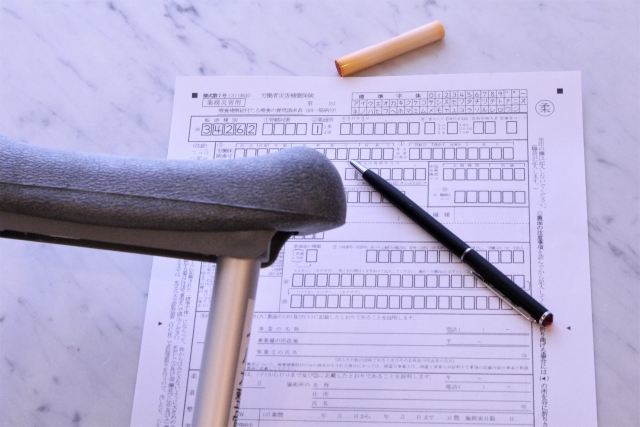
3.休業補償の注意点
休業補償は一定の条件を満たさないと支給されないケースがあります。
見落としがちな注意点を押さえておきましょう。
症状固定や治癒と判断されるタイミングも重要です。
休業補償は無制限に続くわけではなく、必要な療養が終わるまでの間に限られるため、医師の診断や労働基準監督署の判断によって、休業補償の支給が打ち切られることがある点を、理解しておきましょう。
3-1.休業補償が支給される期間は全期間ではない
開始時期
休業補償が支給されるのは、休業後4日目からです。
休業当初の3日間は休業補償を受けることができません。
休業当初3日分の休業については、労働基準法76条により,会社には,平均賃金の60%分を補償すべき義務が定められているので、会社へ請求することを検討します。
ただし,通勤災害の場合には、会社に対する休業補償の義務が認められていません。
終了時期
休業補償は、基本的に労働者が再度働けるようになるまで支給されます。
ただし,けがが完治しなくても症状が固定して治療を終了すると、休業補償の支給も終わります。
症状固定後に後遺障害が残った場合には,別途労働基準監督署に申請をして後遺障害の認定を受け、後遺障害の等級に応じた、障害補償給付を受けることができます。
症状固定については、主治医の意見をもとに、労働基準監督署が判断します。
症状固定のタイミングについては、主治医とよく相談するようにしてください。
3-2.賃金を受け取っていると休業補償を受けられない
休業補償は「仕事を休んで治療をして無給」になっていることが,支給の要件となるので、会社から給料をもらっている場合には支給されません。
年次有給休暇を取得すると、賃金を受け取っていることになりますので、休業補償を受給できません。
3-3.2年の時効に注意
労災保険の休業補償は、労働不能のため、賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年が経過しますと、時効で消滅してしまいます。
この2年の時効は、あっという間に過ぎてしまいますので、労働災害に巻き込まれて怪我をした場合、なるべく早く、労災申請をするようにしてください。
このように、労災保険を利用すれば、会社を長期間休業しても、給料の約80%が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
そのため、労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
けがをして働けなくなった労働者にとって,休業補償は非常に重要です。申請方法がわからない、会社が対応してくれないなどでお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。
当事務所では、労災事故にまきこまれた労働者の方をサポートするために、労災申請のサポートをしております。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやlineでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。