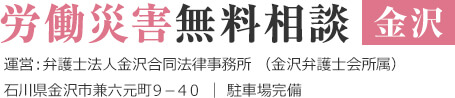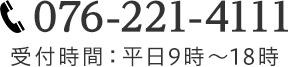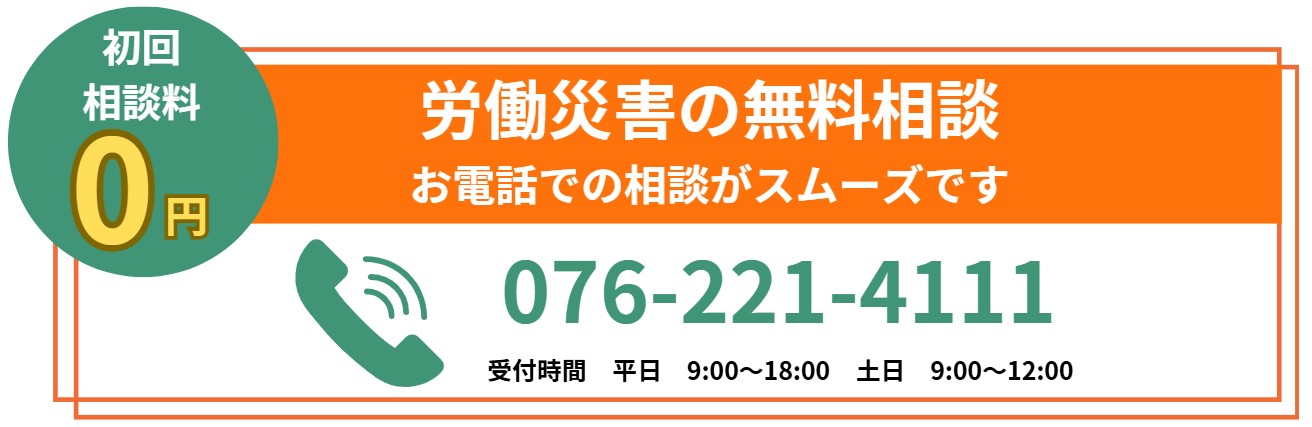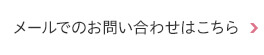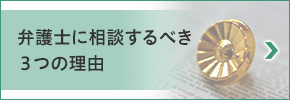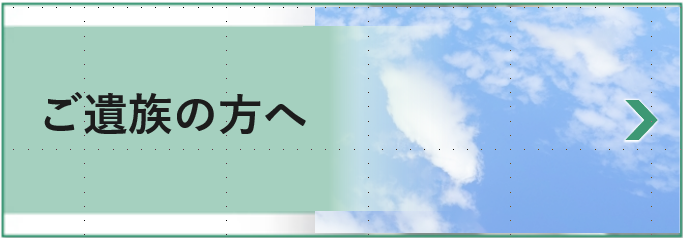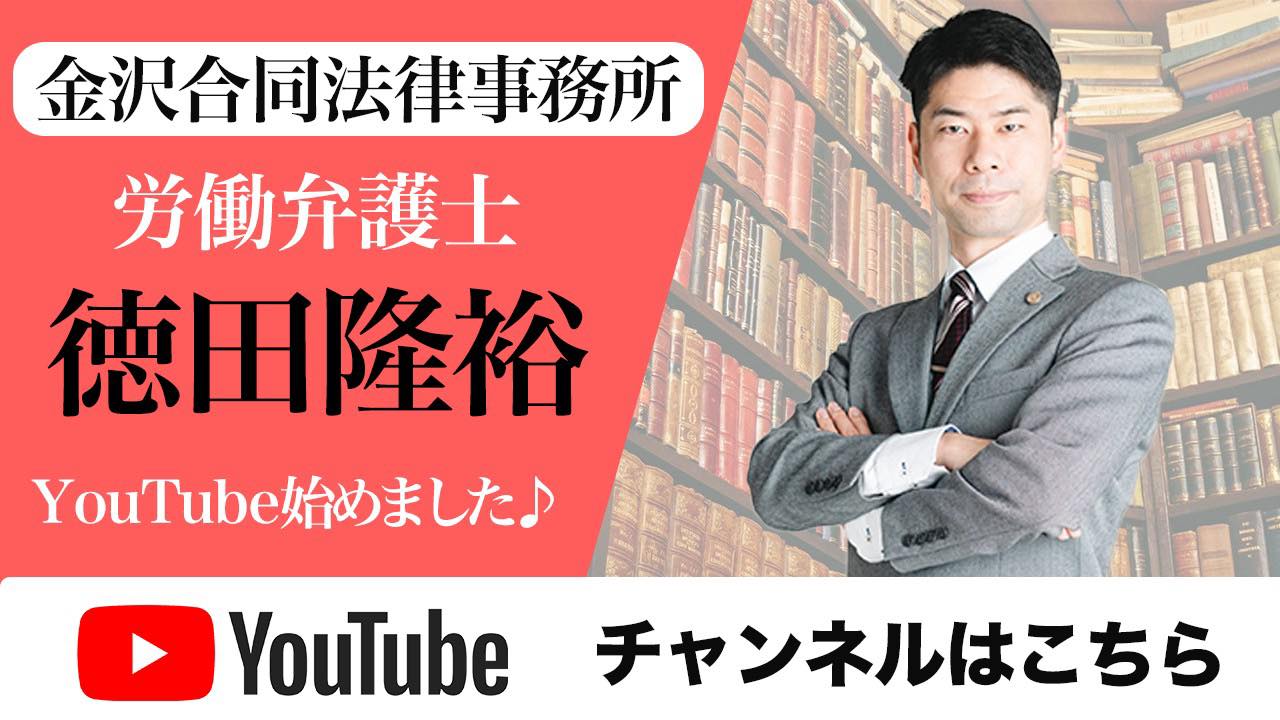上司からのパワハラでうつ病を発症し、労災認定後に425万円の損害賠償請求が認められた事例
上司からのひどいパワハラでうつ病を発症し、長期間休職しています。
パワハラをした上司や何もしてくれなかった会社に対して、損害賠償請求をしたい場合、どうすれよいでしょうか。
結論から先にいいますと、労災認定がされて、パワハラを証明できる証拠がある場合、上司や会社に対して、損害賠償請求を検討します。
今回は、上司からのパワハラでうつ病を発症し、労災認定後に425万円の損害賠償請求が認められた解決事例を紹介します。

1 上司からのパワハラでうつ病を発症
依頼者は、病院で看護師として働いていましたところ、同じ病棟の看護師長から、パワハラを受けて、うつ病を発症しました。
依頼者が、看護師長から受けたパワハラの内容は、次のとおりです。
「あんたがこんなひどい病棟を作った。あんたが悪い」、「50歳なんだから、そんなこと自分で考えなさい」、「あなた、何も知らないのね、何もわかってないね」、「いい給料もらって、給料分働きなさいよ」等と言われて侮辱されました。
依頼者は、病院に対して、看護師長からパワハラを受けて辛いので、何とかしてほしいと相談しましたが、病院からは、「もうしばらく我慢してくれ」、「そこは、聞き流して」と言われるだけで、看護師長に対するパワハラを止めることは何もしてくれませんでした。
看護師長から、依頼者に対するパワハラは、8ヶ月間に及び、依頼者は、動悸、胃痛、吐気、時々涙が出るようになり、精神科を受診したところ、うつ病と診断され、長期間、休職することになりました。

2 労災認定
依頼者は、看護師長からのパワハラは、労災になると考えて、ご自身で労災申請をしました。
⑴ 精神障害の労災認定基準
ここで、精神障害の労災認定基準について解説します。
精神障害が労災と認定されるためには,厚生労働省が公表している、心理的負荷による精神障害の労災認定基準に記載されている、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①対象疾病である精神障害を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと
この3つの要件について詳しく解説していきます。
① 対象疾病の発病
精神障害で労災と認定されるためには,被災労働者が,対象疾病を発病していなければなりません。
どんなに強い心理的負荷や過重労働があったとしても,精神障害を発病していないと判断されれば,労災認定を受けることができません。
この対象疾病とは,ICD-10(世界保健機関が定める診断ガイドラインのことです)でF2,F3,F4に分類される病気です。
代表的なのは,うつ病,双極性感情障害,適応障害などです。
対象疾病の発病については、精神科や心療内科の診断書やカルテをもとに認定されます。
② 強い心理的負荷
精神障害を発病するような、強い心理的負荷を生じさせる業務上の出来事が存在したかどうかが,精神障害の労災認定のための重要なポイントとなります。
具体的には,精神障害を発病する前6ヶ月の間に,「心理的負荷による精神障害の認定基準」の別表1「業務による心理的負荷表」に記載されている具体的出来事に該当することがあったかを検討していきます。
別表1「業務による心理的負荷表」に記載されている具体的出来事に該当することがあり,その具体的出来事の心理的負荷の強度が「強」と判断されれば,労災認定されます。
例えば、パワハラを受けて、労災申請をしようと思った場合、自分の受けたパワハラが、心理的負荷評価表に記載されている、「強」と評価されるパワハラに該当するかを検討します。
心理的負荷評価表において、心理的負荷が強と評価されるパワハラは、次のとおりです。
①上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
②上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
③人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がないまたは業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃が執拗に行われた場合
例えば、バカ、アホ、まぬけ、ハゲ、デブ、給料どろぼうなど、人を侮辱することを何回も言われた場合、心理的負荷が強になります
④必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が執拗に行われた場合
例えば、他の労働者がいる前で、長時間大声で怒鳴り散らされて叱責されることが何回もあると、心理的負荷が強になります。
⑤心理的負荷としては中程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
例えば、パワハラを受けていることを会社に相談しても、会社が何も対応をしてくれなかった場合、心理的負荷が強になります。
他方、身体的攻撃や精神的攻撃が行われても、行為が反復・継続していない場合、心理的負荷は中となります。
そのため、自分が受けたパワハラが、上記①~⑤のどれかに該当すれば、労災と認定されますが、上記①~⑤のどれにも該当しないのであれば、労災と認定されません。
1回のパワハラについて録音があっても、その他のパワハラについて録音がなく、パワハラが執拗に行われたことを証明できず、心理的負荷の強度は中と評価され、労災と認定されるのは難しいことがあります。
もっとも、心理的負荷の強度が中に該当する、パワハラの出来事があった場合、精神障害発病前の6ヶ月間のどこかで、1ヶ月100時間程度の時間外労働をしていたのであれば、心理的負荷は強と評価されます。
そのため、精神障害を発症して、労災申請をする場合には、発症時期から6ヶ月間のどこかに1ヶ月100時間程度の時間外労働がないかを検討します。
具体的には、タイムカードやパソコンのログデータ、日報、入退館記録等の労働時間を証明できる証拠を収集し、1ヶ月に100時間ほどの時間外労働がなかったかを検討します。
③ 業務以外の心理的負荷と個体側要因
精神障害の労災認定基準では,業務以外の心理的負荷と個体側要因が除外要件としてあげられています。
ようするに、離婚、身内の死亡、災害にあった、近所の騒音、友人に裏切られた等のプライベートな出来事で、精神障害を発病していないということです。
業務以外の心理的負荷については,「心理的負荷による精神障害の認定基準」の別表2「業務以外の心理的負荷評価表」に記載されている出来事があるか,あるとして,その出来事の心理的負荷の強度はどれくらいかを検討します。
心理的負荷の強度がⅠやⅡの出来事があっても問題ありませんが,Ⅲの出来事がある場合には,Ⅲの出来事が精神障害の発病の原因と言えるかを慎重に検討していきます。
個体側要因の具体例としては,就業年齢前の若年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており,請求に係る精神障害がその一連の病態である場合や,重度のアルコール依存状況がある場合などがあげられます。
⑵ 依頼者の日記でパワハラが認定された
さて、今回の事件では、依頼者は、日々の出来事を日記に記録を残しており、看護師長から、パワハラを受けた場合、その日のうちに、どのようなパワハラを受けたのかについて、詳細に記載していました。
一般的には、日記は、後から記憶を喚起して記載することが可能ですので、証拠としての価値は低くみられるのですが、今回の依頼者の場合、毎日、詳細に日々の出来事を記録していたため、日記の証拠価値が高く評価されたと考えられます。
この日記の記録をもとに、労働基準監督署は、看護師長の依頼者に対するパワハラを認定しました。
そして、労働基準監督署は、依頼者が看護師長から受けたパワハラの心理的負荷の強度は、「中」であると評価したものの、依頼者が病院にパワハラの相談をしても、何も対応をしなかったことについて、心理的負荷の強度を「強」と評価して、労災と認定しました。
通常、言葉の暴力によるパワハラの場合、録音がないことには、パワハラの認定は難しいのですが、今回の事件では、依頼者の詳細な日記の記録をもとに、パワハラの認定を勝ち取ることができました。
また、パワハラ自体の心理的負荷の強度が「中」であっても、会社に相談したものの、会社が何も対応をしなかった場合、心理的負荷の強度が「強」に該当して、パワハラが労災と認定されることがあります。

3 パワハラの損害賠償請求
ご自身で労災認定を受けた依頼者は、上司と病院に対して、損害賠償請求をしたいとう要望のもと、当法律事務所へ法律相談にこられました。
労災認定を受けていますので、まずは、労働局に対して、個人情報の開示請求をして、労働基準監督署の労災の記録を取り寄せ、損害賠償請求が認められるかを検討しました。
⑴ 上司に対する損害賠償請求
優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労動者の就業環境を害する行為は、違法なパワハラに該当します。
違法なパワハラを行った上司は、故意または過失によって、他人の権利や利益を違法に侵害し、損害を与えるという、不法行為責任を負います。
すなわち、不法行為をした加害者は、被害者に対して、損害賠償責任を負うのです。
依頼者は、看護師長に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をしました。
依頼者は、うつ病を発症したものの、幸い、別の職場に復帰できる程度に症状が回復したため、後遺障害の認定はなく、うつ病で休職していた期間の休業損害と、慰謝料の損害賠償請求をしました。
⑵ 病院に対する損害賠償請求
労働基準監督署の労災の記録を検討したところ、依頼者が、病院に対して、看護師長からのパワハラの相談をしたものの、病院が何もしていなかったことが明らかになりました。
本来であれば、病院は、看護師長の依頼者に対するパワハラの実態調査をして、パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応をすべきでした。
そのため、病院は、依頼者の職場環境が看護師長のパワハラによって害されないように防止配慮すべき義務に違反しており、損害賠償責任を負います。
また、病院の従業員が、事業の執行について、不法行為を行った場合、病院は、民法715条の使用者責任を負い、損害賠償義務を負担しなければなりません。
そこで、依頼者は、病院に対しても、損害賠償請求をしました。
⑶ 病院との交渉で425万円の損害賠償を回収した
看護師長と病院に、それぞれ代理人が就き、看護師長は、パワハラの事実を争ってきました。
他方、病院は、ある程度の損害賠償額を依頼者に支払い、示談で解決することを提案してきました。
依頼者は、看護師長のパワハラでうつ病を発症する以前、精神科に通院していた病歴があり、過去に精神科の通院歴がある場合、精神的な要因(素因)が、損害の発生や拡大に影響を与えたならば、その影響度合いに応じて、加害者の賠償責任を減額するという、素因減額が認められることが予想されました。
裁判になった場合、時間がかかる上に、素因減額で一定程度、損害賠償額が減額されることが見込まれました。
また、うつ病で長期間休職していた依頼者にとって、さらなるストレスがかかる裁判を提起することは得策ではありませんでした。
そのため、裁判を避けて、交渉で事件を解決することを選択しました。
病院の弁護士と交渉した結果、最終的に、病院から、425万円の損害賠償を支払ってもらうことで、合意が成立しました。
不法行為の損害賠償請求では、病院と看護師長から合計でいくらの損害賠償額を回収できるかということになり、病院から、損害賠償を回収したため、看護師長に対して、これ以上、損害賠償請求することはできません。
後は、病院が、看護師長に対して、求償権を行使するかという問題となります。
依頼者は、パワハラのうつ病で、長期間苦しんだものの、最終的には、425万円の損害賠償が認められて、納得して事件が解決できて、喜んでいただけました。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
関連記事
- 脚立から転落して骨折した労災事故で、後遺障害12級の12に認定された事例【弁護士が解説】
- 労災による耳鳴り・聴力障害で後遺障害と認定されて会社に損害賠償請求して400万円の賠償金を獲得した事例
- 上司からのパワハラでうつ病を発症し、労災認定後に425万円の損害賠償請求が認められた事例
- 交通事故の労災で12級12号の後遺障害が認定され、約200万円の一時金を獲得できた事例
- 長時間労働による過労死が労災と認定され、会社との間で損害賠償請求の示談が成立した事例
- 腰痛の悪化について労災認定され、後遺障害14級が認定された事例
- 化学物質を吸引した労災事故で、会社と交渉して、200万円の解決金を得た事例
- 切断した電線が右目に当たり、後遺障害準用8級が認定された労災事故で、会社と交渉して、約1200万円の損害賠償金を得た事例
- 労災事故による腰椎破裂骨折で11級5号の後遺障害が認定された事例
- 頭部外傷による高次脳機能障害で後遺障害7級4号が認定されたケース