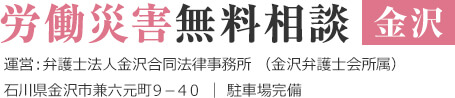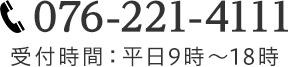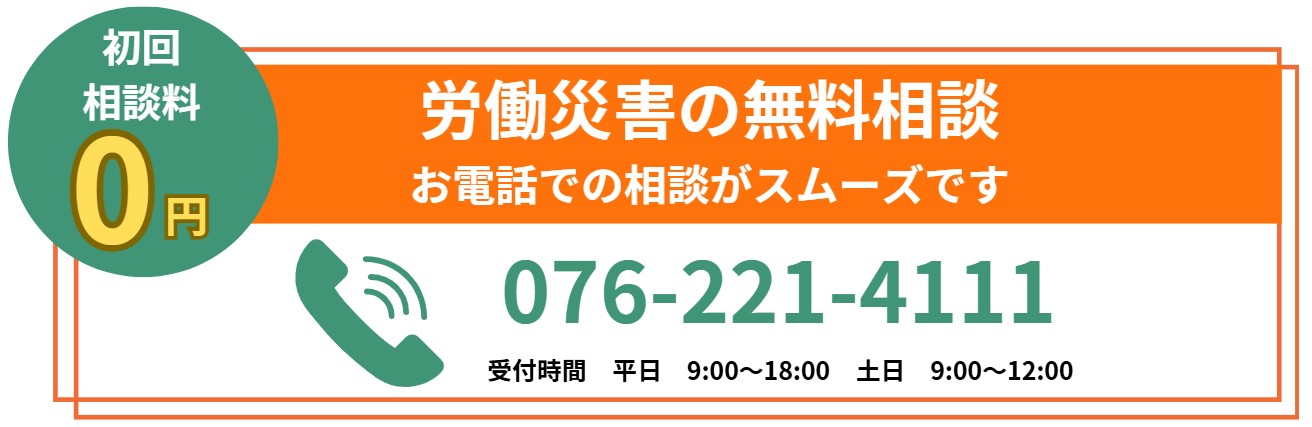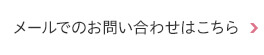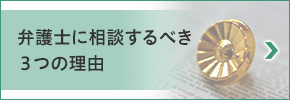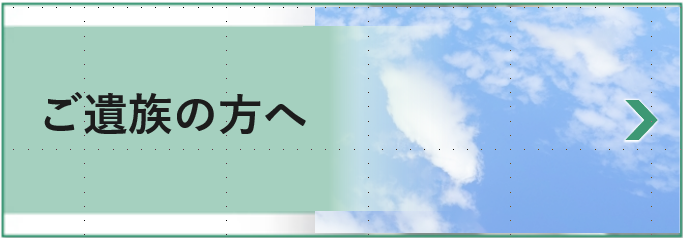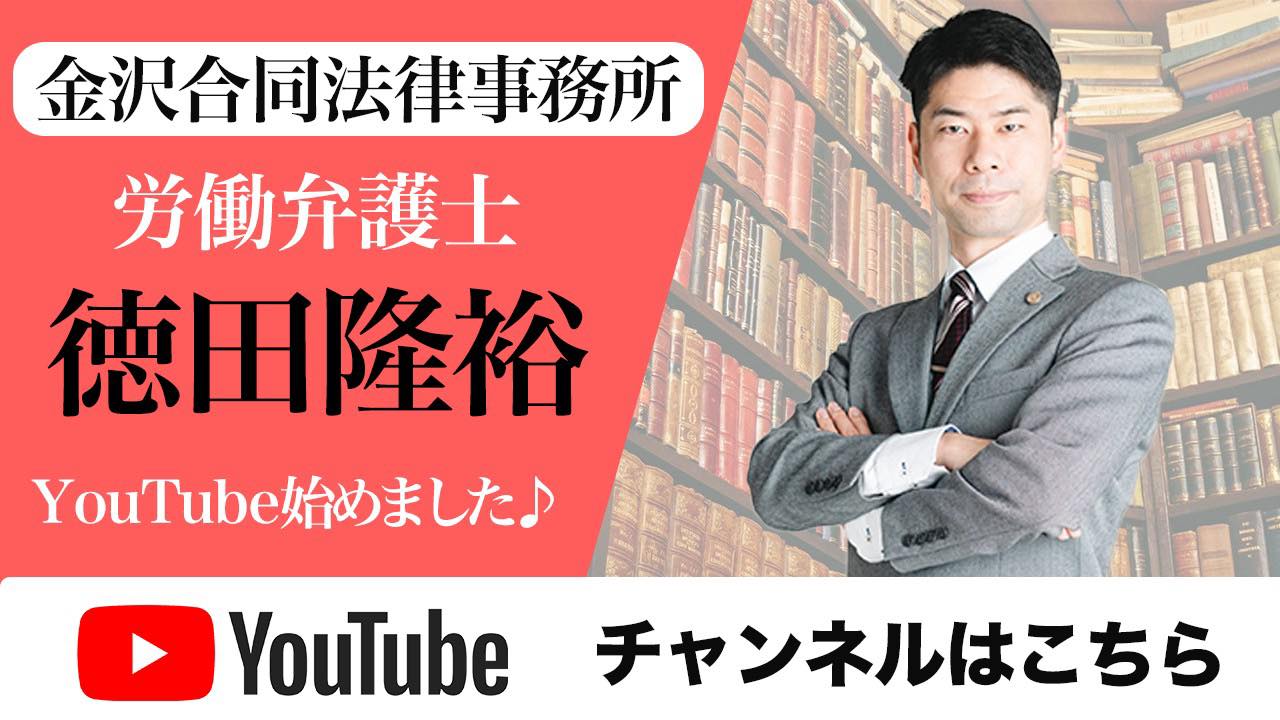労災による耳鳴り・聴力障害で後遺障害と認定されて会社に損害賠償請求して400万円の賠償金を獲得した事例
職場における騒音が原因で難聴になった場合、会社に対して、損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
結論から先にいいますと、職場における騒音が原因で難聴になったことについて、労災認定されれば、会社に対して、損害賠償請求を検討します。
今回は、仕事中の騒音によって、耳鳴りや音感難聴となり、後遺障害と認定されて、会社に損害賠償請求をして、400万円の賠償金を獲得した解決事例を紹介します。

1 労災で耳鳴り・聴力障害に
60代の男性依頼者は、清掃会社に勤務していたところ、高圧洗浄機や高圧吸引機を使用して、汚水を吸い取る作業を地下の密閉空間で行っており、機械の操作音がうるさく、地下空間で音が反響するため、日常的に騒音にさらされていました。
そして、依頼者は、ある施設における清掃作業で、高圧コンプレッサーを使用して、空気を吐き出し、灰を吹き飛ばす作業をしたところ、いつもの10倍の馬力の機械を使用したため、反響音が大きく、作業後、同僚から呼ばれても聞こえず、耳が聞こえにくくなりました。
依頼者は、耳鳴りがして、音が聞こえない状態が続いたため、耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査をしたところ、右耳も左耳も悪いが、左耳のほうが特に悪いと言われ、薬の処方を受けたものの、症状は改善されませんでした。
耳鳴りや難聴が改善されなかったため、依頼者は、補聴器を購入したのですが、その費用が高額であったため、仕事が原因で聴力障害を発症したのに、補聴器の金額を自己負担しなければならないことに納得がいかず、労災申請をすることを決意しました。
そして、難聴の労災申請をするために、当事務所へ法律相談に来られました。
2 労災認定

依頼者のお話を聞きますと、長年、騒音に暴露される環境で働いていたため、騒音性難聴で労災認定されないかについて、検討しました。
⑴ 騒音性難聴の労災認定基準
騒音性難聴とは、長時間大きな音にさらされることで内耳の音を感じる細胞(有毛細胞)がダメージを受け、聴力が低下する難聴です。
工場や工事現場などの職業性騒音、またはヘッドホンやイヤホンで大音量を聴くことによって引き起こされ、初期には自覚症状が少ないまま進行し、高音域から聞こえにくくなるのが特徴です。
著しい騒音に暴露される業務に長期間引き続き従事した後に、騒音性難聴を発症した場合、労災と認定されることがあります。
厚生労働省は、被災労働者の耳の位置における騒音が概ね85dB以上である業務に、概ね5年又はこれを超える期間、従事して、騒音性難聴を発症した場合、労災と認定するという基準を設けています。
依頼者の話によると、依頼者が地下空間で、使用していた高圧洗浄機や高圧吸引機の騒音は、85dB以上であったと考えられ、また、5年に近い期間、騒音に暴露されていたと考えられたので、騒音性難聴で労災と認定されると考えました。
そこで、依頼者から労災申請サポートのご依頼を受けて、労災申請をしました。
⑵ 耳鳴りと音感難聴で労災認定される
労働基準監督署は、騒音性難聴について、地下空間での騒音作業については、声を張れば会話できる程度の騒音であり、依頼者が連続して騒音作業に従事していないとして、労災認定基準を満たしていないとして、労災とは認定されませんでした。
もっとも、高圧コンプレッサーを使用して灰を飛ばす作業について、高圧コンプレッサーの騒音は、108dBであり、作業環境において反響音が大きく、他の同僚も一時的に、耳が聞こえにくくなっていたことから、強大音への暴露があったと認定され、音響外傷による、左耳の音感難聴と耳鳴りについて、労災と認定されました。
依頼者は、もともと、右耳に音感難聴があったことから、今回の労災事故で左耳に音感難聴が生じ、加重と評価され、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上となり、後遺障害等級表第11級の3の3「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」と認定されました。
また、難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価され、耳鳴りで準用12級と認定されました。
なお、右耳については、後遺障害等級表第14級の2の2「一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当することから、後遺障害11級の障害補償給付の給付基礎日額223日分から、既存の右耳の14級の障害補償給付の給付基礎日額56日分を差し引いて、給付基礎日額167日分が支給されることになりました。
結果として、障害補償一時金1,458,578円、障害特別一時金276,385円、障害特別支給金210,000円が労災保険から支給されました。

3 会社に対する損害賠償請求
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
⑴ 安全配慮義務違反
労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
今回のような、職場における騒音について、厚生労働省は、騒音障害防止のためのガイドラインを策定しています。
騒音障害防止のためのガイドラインでは、会社が作業時間の管理として、騒音レベルごとに、1日の暴露時間の目安を定めておりますので、会社は、職場の騒音を測定して、騒音レベルに応じて、1日の騒音暴露時間の目安を超えないように、労働者を働かせる必要があります。
そのため、会社が職場の騒音の測定を怠り、1日の騒音暴露時間を超えて、労働者を働かせた場合、安全配慮義務違反と認定される可能性があります。
また、騒音障害防止のためのガイドラインには、作業管理として、耳栓やイヤーマフ等の聴覚保護具を使用させることが記載されています。
そのため、会社は、騒音がひどい環境において、労働者に作業をさせる際、耳栓やイヤーマフ等の聴覚保護具を使用させていなかった場合、安全配慮義務違反と認定される可能性があります。
今回の事件では、会社は、騒音の人体に及ぼす影響及び聴覚保護具の使用について、労働安全衛生教育をしておらず、依頼者に対して、聴覚保護具を使用させていなかったことについて、安全配慮義務違反があったと主張しました。
⑵ 示談交渉で400万円の解決金を回収
依頼者は、加重で後遺障害等級の第11級の3の3と認定されましたが、今回の労災事故では、左耳の音感難聴で第14級の2の2、耳鳴りで準用第12級と認定されたので、後遺障害12級で、逸失利益と慰謝料を計算して、会社に対して、損害賠償請求をしました。
会社からは、依頼者以外に、難聴の症状を訴えている労働者はいないことを理由に、業務起因性を争う主張がありましたが、労働基準監督署が業務起因性を認定していることから、会社は、本気で争う様子ではなく、話し合いで解決することを提案してきました。
裁判をすると、1年くらい時間がかかりますので、示談交渉で早期に解決することは、依頼者にとってメリットは大きいです。
そこで、会社の代理人弁護士と交渉して、当方の請求金額の約9割の400万円の解決金を支払ってもらうことで、示談がまとまり、解決しました。
依頼者は、裁判を経ることなく、早期に請求金額の約9割の解決金を獲得して、事件を解決することができましたので、大変満足されていました。
このように、職場での騒音によって、聴力障害を発症した場合、労災と認定されれば、会社に対して、損害賠償請求が認められる可能性があります。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
関連記事
- 脚立から転落して骨折した労災事故で、後遺障害12級の12に認定された事例【弁護士が解説】
- 労災による耳鳴り・聴力障害で後遺障害と認定されて会社に損害賠償請求して400万円の賠償金を獲得した事例
- 上司からのパワハラでうつ病を発症し、労災認定後に425万円の損害賠償請求が認められた事例
- 交通事故の労災で12級12号の後遺障害が認定され、約200万円の一時金を獲得できた事例
- 長時間労働による過労死が労災と認定され、会社との間で損害賠償請求の示談が成立した事例
- 腰痛の悪化について労災認定され、後遺障害14級が認定された事例
- 化学物質を吸引した労災事故で、会社と交渉して、200万円の解決金を得た事例
- 切断した電線が右目に当たり、後遺障害準用8級が認定された労災事故で、会社と交渉して、約1200万円の損害賠償金を得た事例
- 労災事故による腰椎破裂骨折で11級5号の後遺障害が認定された事例
- 頭部外傷による高次脳機能障害で後遺障害7級4号が認定されたケース