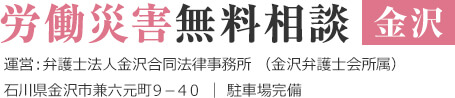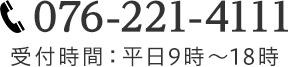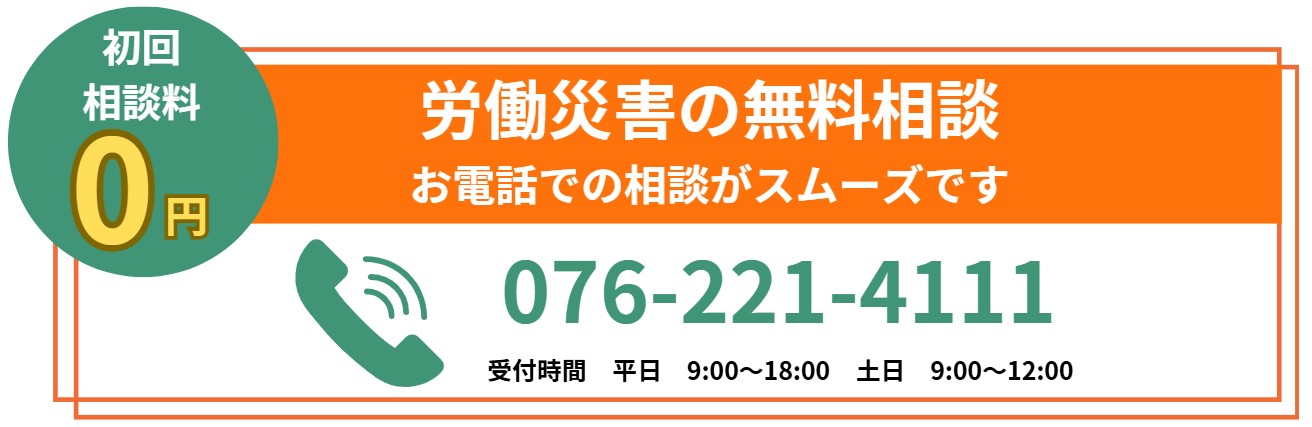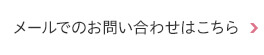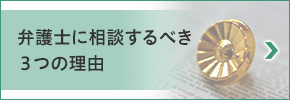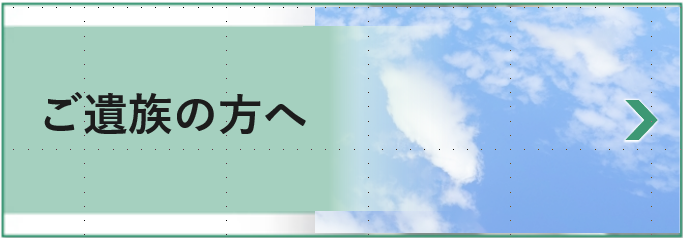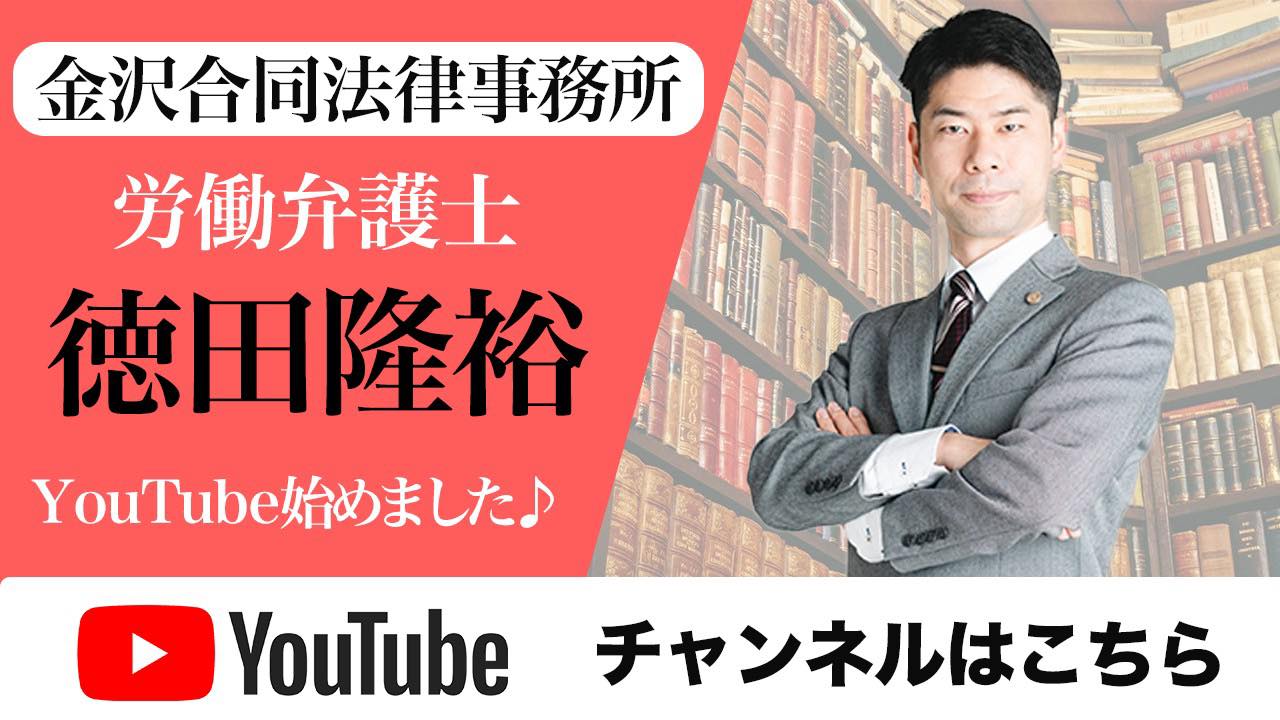労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
労災による骨折は、業務や通勤中の不慮の事故によって起こるため、ケガの程度に応じて長期間の治療と休業が必要になることがあります。特に骨折は身体へのダメージが大きく、復帰までに時間を要するケースも少なくありません。
労働災害において、休業補償を受けるためには、労災として認定されるための要件を正しく把握することが重要です。労災認定に向けて、必要書類や申請手続き、補償期間についてのポイントを整理しておくと安心です。
この記事では、骨折が労災として認定される基準や休業補償の期間・打ち切り条件などをわかりやすく解説します。弁護士に相談するメリットも含めてチェックし、トラブルなく適正な補償を受け取るための参考にしてください。

労災による骨折とは?
労災保険は業務中または通勤途上で起こったケガに対して適用され、骨折は代表的な負傷例の一つです。
骨折は、転倒や物の落下、交通事故など様々なシーンで発生し、治療期間が長期化しやすい特徴があります。特に業務災害では、高所での作業中に足を踏み外したり、重量物を扱っていて手や足を負傷することが多く見受けられます。通勤途上でも、バイクや自転車での転倒事故や、歩行中に車にはねられて骨折するケースがみられます。
骨折すると、患部を固定して治療する必要があり、復帰のためにはリハビリも不可欠となります。労災として認定されれば、治療費はもちろん、休業補償や後遺障害が残った場合の補償なども受けられる点が押さえておきたいポイントです。
ただし、骨折で労災認定してもらうためには、事故が業務または通勤に起因するものであることを証明しなくてはなりません。早めに会社に報告し、医師の診断書やレントゲン写真など必要な資料を整えることが大切です。
骨折が業務災害・通勤災害として認定される条件
骨折が労災として認定されるためには、業務災害または通勤災害として労働基準監督署が判断する必要があります。業務災害の場合は、労働者が労働契約に基づき会社の支配下にあるという業務遂行性と、業務に内在する危険が現実化したという業務起因性が認められた時に、労災と認定されます。
通勤災害の認定基準は、自宅と勤務先の間を通常の経路で往復していたかどうかという点が重視されます。遠回りや寄り道をした場合は通勤災害とならない可能性がありますが、やむを得ない事情があれば認定されることもあります。
いずれにしても、事故発生時の状況や経緯を正しく報告し、業務上・通勤上の災害に該当することを証明する必要があります。曖昧な点があれば、労働基準監督署から追加の調査や質問が行われることもあるため、事実関係を整理しておきましょう。
骨折が起きやすい代表的なケース
業務災害では足場の不安定な高所作業や、重量物を持ち上げる現場などが挙げられます。足を滑らせての転落や、落下物の衝突で手足を骨折する事故は、建設現場や工場などで多発しやすいパターンです。
通勤災害の場合は、バイクや自転車での転倒事故が代表的です。急ぐあまりスピードを出しすぎると転倒リスクが高まり、骨折につながる深刻な事態を招きやすいことを意識しましょう。また、通勤の途中で交通事故に巻き込まれることもあります。
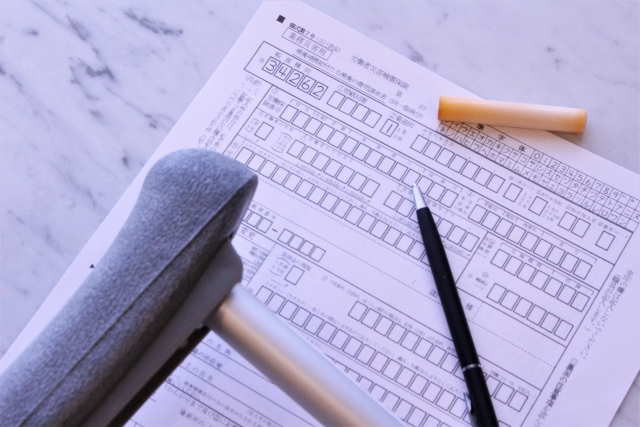
骨折で休業補償を受け取るための要件
骨折について、休業補償を受けるためには支給要件をすべて満たしている必要があります。
労災保険の休業補償は、ケガによって就業できない期間の生活を支援するための制度です。ケガによる休業が日常生活に直接影響し、収入が断たれる状況は労働者にとって大きな不安要素となります。ここでは、休業補償を受け取るための支給要件について、解説します。
休業補償は、休業開始の4日目から適用されるため、まずは労働基準監督署に労災事故の詳細を届け出ることが不可欠です。会社で作成する書類や医師の診断書も必要となるため、早めの準備が求められます。
また、骨折で安静や治療が必要だという医師の診断が大前提となります。加えて、会社から賃金の支払いがない休業日数分を対象として申請を行う形になるため、給与の支給状況も確認することが重要です。
①業務災害又は通勤災害によって治療を受けていること
業務中や通勤途上の事故で骨折した場合に労災保険の対象となります。ただし、業務外の私的行為による事故は認められないため、事故の時点での行動が仕事や通勤と関連しているかが鍵です。
通勤災害の場合は、経路や逸脱又は中断があったかどうかも認定に影響します。理由が正当と判断されれば労災認定される場合もあるので、正直かつ詳細に申立てすることが求められます。
労災事故発生後は、まず会社に状況を報告するとともに、労働基準監督署への手続きに必要となる書類の作成を進めます。業務上・通勤上のケガであることを示す証拠や証言が重要となります。
②ケガによって労働することができないこと
骨折は病院での精密検査や治療が必須となるケガですが、休業補償を受け取るためには医師が「就業不能状態である」と診断する必要があります。
診断書において、治療の程度や安静期間が示されていれば、労働基準監督署は休業の妥当性を判断しやすくなります。
また、治療期間中の状態変化に応じて再度、診断書の提出などを求められることもあるため、主治医の指示をよく確認しましょう。可能であればケガの状態をしっかり記録しておくと、後日の証明にも役立ちます。
③給与を受け取っていない休業日数があること
休業補償給付は、給与が支払われていない休業日数に対して支給されます。逆に、有給休暇を使用して賃金を受け取っている日数については休業補償の対象外となります。
待期期間として扱われる最初の3日間は会社が60%の補償をする義務がありますが(労働基準法76条1項)、その後の4日目から労災の休業補償給付が適用されます。会社の就業規則や労働契約によっては、賃金が一部支給されるケースもありますので注意が必要です。
しっかりと休業日数を管理し、会社からどの程度の賃金が出ているかを明確に把握しておきましょう。漏れや重複があると申請が遅れる原因になるため、事前に給与担当者と確認を行うとスムーズです。

労災骨折の申請手続きの流れ|必要書類と注意点
骨折による労災認定を受けるためには、正確な手続きと書類の準備が欠かせません。
まずは会社への報告が最初のステップです。事故発生日時や場所、ケガの状況を詳しく伝え、会社側が作成する様式を確認しましょう。こ
医師から発行される診断書やレントゲン写真は、骨折の状態を示す重要な証拠となります。確実に労災請求に使えるように、医療機関とコミュニケーションを取りながら書類を整えましょう。
労働基準監督署に労災申請する際は、書類に不備がないかを再度確認し、必要に応じて会社や医療機関に追加書類を依頼します。審査は数週間から数か月程度かかることもあるため、早めに着手することが大切です。
会社への報告と医師の診断書の用意
労災事故が起きたら、できるだけ早く会社に連絡し、労災保険による対応が必要な旨を伝えましょう。骨折で動きづらい場合でも、電話やメールで会社に報告を行い、上司や労務担当者に状況を共有します。
医師の診断書には、骨折の部位と程度、治療の見込み期間などが明確に示されることが理想です。休業補償給付を申請する上で不可欠な資料となるため、診断書の内容をよく確認して受け取りましょう。
また、レントゲンやMRIなどの検査結果についてもコピーを保持しておくと、後に労働基準監督署から照会があった際にスムーズに対応できます。
労働基準監督署における申請と調査のプロセス
会社とともに労働基準監督署に提出する書類を作成し、労災事故の状況と骨折の治療状況を正確に報告します。労災申請書には、労災事故が発生した日時や場所、負傷の様子などをできるだけ詳細に記載すると良いでしょう。
労働基準監督署は、提出書類をもとに事実関係を調査し、必要に応じて会社や医療機関に対して追加の確認を行うことがあります。
無事に労災認定が下りれば、休業補償給付など各種給付を受け取れるようになります。書類の不備や記載ミスを避けるため、提出前に内容を入念にチェックしておきましょう。

骨折時に受け取れる労災保険の主な給付
労災で骨折した場合、休業補償給付だけでなく、治療費など多様な補償制度が用意されています。
労災保険には、療養補償給付や休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付など、さまざまなサポートが整備されています。骨折は治療期間が長引くことが多いため、これらを上手に利用して復帰するまでの生活を支えていくことが重要です。
特に休業補償給付は、業務や通勤に起因するケガで働けない場合に支給されるため、ボルト除去などの再手術が必要になった場合でも、必要性が医師によって認められれば追加で申請が可能です。
ただし、症状固定と判断されるかどうかなど、打ち切り時期の問題や傷病補償年金への移行タイミングなど細かなルールも存在します。自分の状態や治療計画に応じて、どの給付がいつまで受け取れるのかを確認しておくことが大切と言えます。
療養(補償)給付|治療費と薬剤費の補償
骨折の治療では入院費や手術費、装具の作成など多額の費用がかかることがあります。労災の場合、このような治療費や薬剤費について基本的に全額補償され、自己負担は発生しません。
通常の健康保険では自己負担が必要ですが、労災保険で認められれば費用面での負担は大きく軽減できます。
診察時に必ず労災保険を利用したい旨を伝え、病院側で労災対応をしてもらうよう手続きしましょう。未申告のまま健康保険を使うと、後で切り替えが複雑になる場合があります。
休業(補償)給付|休業中の給与の補償
骨折による休業が4日以上にわたる場合、休業補償給付として給付基礎日額の60%が支給されます。さらに加えて同額の20%が休業特別支給金として支給されるため、トータルで80%ほどが補償される形になります。
これは被災労働者の生活を支える重要な給付であり、療養が長引く場合でも一定の収入が確保される安心材料となります。
待期期間(最初の3日)については会社が60%を補償する義務がある一方、勤務先の就業規則によっては独自の補償を行っている企業も存在します。
傷病(補償)給付|長期療養時の給付
骨折の治療が長期にわたり、なおかつ症状固定前の時点で一定期間を超える場合、休業補償給付から傷病補償給付へ移行するケースがあります。これは怪我の重症度や医師の判断に基づき、休業補償給付の打ち切りを行うかどうかが決定されます。
傷病補償給付は傷病等級に応じて、金額が異なり、後遺症が残る見込みがあり、労働能力が著しく低下している場合などに対象となります。
中には、症状固定後に後遺障害が残るケースもあるため、傷病補償給付を受けるか、障害補償給付に移行するかなど、医師の診断や実際の回復状態によって判断が求められます。
障害(補償)給付|後遺障害が残った場合の補償
骨折が重症化し、後遺障害が残った場合には障害等級に応じて障害(補償)給付が支給されます。これには一時金の給付と年金形式の給付があり、障害の程度に応じて支給内容が異なります。
具体的には、後遺障害の等級が1級から14級まで分類され、その等級によって支給金額が変わります。労働能力が、どの程度損なわれたかを客観的に診断書などで示す必要があるため、医師の診断や検査データが重要です。
後遺障害が残った場合には、会社との雇用継続が難しくなるケースや、仕事内容の変更を余儀なくされることもあるでしょう。そのような場合には障害年金など他の社会保障制度も含めて検討するとよいです。
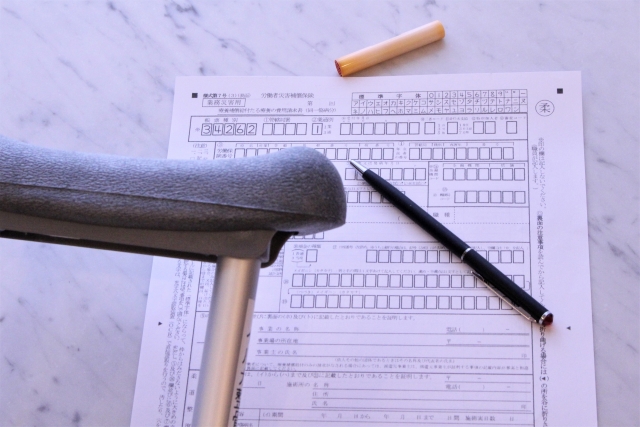
休業補償給付はいつからいつまで支給される?
骨折による休業補償は無期限に続くものではありません。支給が始まるタイミングや打ち切りとなるケースを知っておくことが重要です。
労災時の休業補償給付は、事故発生から4日目以降の休業日数を対象として支給が行われます。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、この期間中の補償は会社側が担うことになっていますが、就業規則によっては全額支払われる場合もあります。
また、治療が長引く場合には休業補償給付を継続して受けられますが、症状固定や就労可能となった時点で休業補償給付は打ち切りとなります。症状固定と認められれば、障害補償給付への移行を検討します。
治療中に職場復帰を試みるケースもあるでしょうが、部分的な就労を行う場合は給与の支給状況や医師の判断を確認する必要があります。休業補償給付の減額や調整が生じるケースもあるため、復帰時期については慎重に検討することが大切です。
待期期間の考え方|開始日とその間の補償
労災保険による休業補償給付は、災害発生日から連続する3日間に関しては支給されません。これが待期期間と呼ばれるもので、会社にはこの3日間について60%の休業補償を行う義務があります。
ただし、企業によっては独自の補償制度を設けており、待期期間中に全額補償されるケースもあるため、就業規則や労働契約を確認してみましょう。
4日目以降は労災保険により一定の給付が行われ、給付基礎日額の60%相当が休業補償給付として、給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給される仕組みとなっています。
打ち切りになるケース①:症状固定による障害補償給付への移行
休業補償給付は、ケガが回復するまで継続して支給されますが、治療を継続してもそれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。症状固定と判断された時点で休業補償給付は打ち切りとなるのが一般的です。
後遺障害の程度に応じて年金か一時金が支給されます。
この移行の段階は、医師の見解を含めて丁寧に確認する必要があります。症状固定が早すぎると感じる場合は、納得のいく説明を主治医や労働基準監督署から得るようにしましょう。
打ち切りになるケース②:仕事に復帰して賃金を得た場合
休業補償給付は働けない状態を前提としたものです。よって、途中で職場復帰し、賃金を得る状況になれば支給自体が打ち切りとなります。
ただし、完全復帰ではなく一部時短勤務やリハビリ勤務をしながら給与が発生している場合など、状況に応じて給付金の調整が行われることもあります。会社とよく相談したうえで手続きを進めましょう。
職場復帰後になお再手術が必要になった場合などは、再度労災として休業補償給付の申請を行うことも可能です。主治医の判断書類をそろえてから労働基準監督署に手続きをします。

骨折治療の流れと職場復帰までの目安
労災事故で骨折を負った場合、治療から職場復帰までには段階的なリハビリが求められることが一般的です。
骨折治療は、骨を固定し、安定した状態で骨癒合を待つことから始まります。手術が必要なケースでは、プレートやボルトなどを使って患部を安定させ、術後は痛みや腫れが引くまで一定期間の安静が必要となります。
その後、段階的にリハビリを進め、骨が十分に癒合したタイミングで負荷をかける運動を行うなど、復帰に向けた準備を整えます。治療や回復のペースは個人差がありますが、医師と相談しながら無理のない計画を立てることが大切です。
復職時期は会社の産業医などの意見も参考に決めることが多いでしょう。焦って復帰して再度ケガを悪化させれば、結果的に休業期間が延びるリスクもあるため、十分に注意してください。
自宅療養やリハビリ中でも休業補償は受けられる?
労災認定された骨折であれば、入院・通院問わず医師の診断書で就業不可とされれば休業補償給付の対象となります。自宅で安静を保つよう指示されるケースでも、会社から給料が支払われない日数をについて、休業補償給付の申請ができます。
ただし、自己判断で選んだリハビリや、因果関係が不明確な医療行為は補償対象外となる場合があります。必ず主治医の指示に基づく治療やリハビリであることが前提です。
骨が癒合するまでには時間がかかるため、自宅療養を余儀なくされることも少なくありません。定期的に医師の診察や検査を受け、就労不可が続く場合には継続して休業補償給付を受けられるよう手続きを忘れずに行いましょう。
職場復帰の判断基準と手続きのポイント
職場復帰は、骨折の部位や回復度合いによって異なります。医師から仕事が可能と認められた段階でも、実際に業務で負荷がかかる場面を想定し、リハビリを行いながらテスト的に働く場合もあります。
復帰前には会社の産業医や上司とも相談し、業務内容が無理のない範囲に調整されているかを確認しましょう。フルタイムが難しい場合は、時短勤務や軽作業から始めることも選択肢となります。
職場復帰後も痛みや腫れが再発した場合は、その都度医師に相談し、必要があれば再び労災保険による休業補償を検討しましょう。適切なプロセスを踏むことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。

休業補償給付の額の計算方法
労災の休業補償給付は、労災事故前の給与水準をもとに算定され、一定の割合で支給される仕組みです。
休業補償給付では、過去3か月間の賃金を合計し、その合計を3ヶ月間の総日数で割り出した給付基礎日額を用いて計算が行われます。給付基礎日額の60%が休業補償給付となり、さらに20%が休業特別支給金として支給されるのが基本です。
正社員だけでなくパートやアルバイトであっても労災保険に加入していれば同様の計算方法で休業補給付を受け取れます。
また、必要に応じて会社への損害賠償請求も検討できる場合があります。
給付基礎日額の算出方法と具体例
給付基礎日額は、労災発生日以前の連続した3か月間に受け取った賃金総額を3ヶ月間の総日数で割って得られる1日あたりの平均賃金です。
例えば、過去3か月で90万円の賃金(残業代などを含む)を得ていた場合、総日数が92日だったとすると、1日あたりの給付基礎日額は、90万÷92=17,308円となります。そこから休業補償給付60%の10,384円、休業特別支給金20%の3,461円を合計すれば、13,845円が1日あたりの支給額となる計算です。
実際の計算では細かい部分もあるため、事前に会社や労働基準監督署に相談し、書類記入を慎重に行うことが求められます。
有給休暇取得や部分的な就労の扱い
休業補償給付は無給の休業日が対象ですが、有給休暇を取得している場合、その日数分は賃金が支払われているため、休業補償給付は支給されません。
また、時短勤務やリハビリ勤務等の部分的に就労して賃金を得ていた場合、得ている賃金額に応じて、休業補償給付が減額される可能性があります。
会社側の理解と労働基準監督署のルールをきちんと把握しておかないと、支給漏れや過払い問題が起こることもあるため、就業形態に応じた正確な情報共有が大切です。
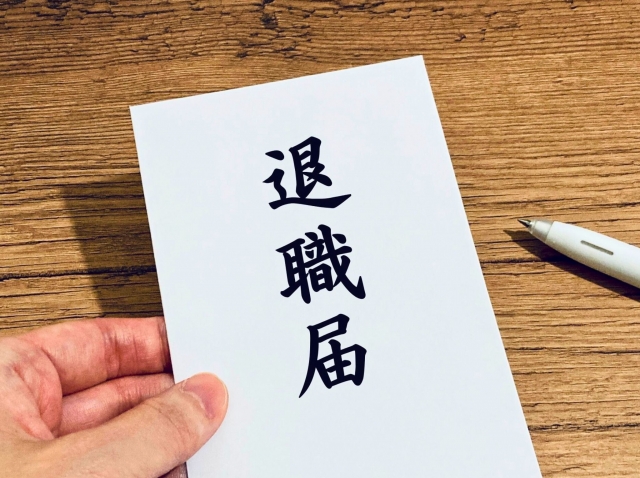
退職や解雇があった場合の休業補償
骨折による長期休業中に退職や解雇が発生した場合、労災保険の支給はどのように扱われるか確認しておく必要があります。
労災事故は在職中に起きたものであれば、退職後でもそのケガに起因する休業補償給付を受給できるのが原則です。
一方、解雇については、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間、会社は解雇することができません。そのため、休業補償給付を受給している期間中に解雇された場合、解雇は無効になります。
万一、解雇された場合、早急に弁護士などの専門家に相談し、労働審判等の法的手段を検討する必要があります。
退職後でも休業補償は受けられる?
労災が認定された時点で在職していれば、退職後も休業補償給付を受けること自体は可能です。
退職後に治療が長引いている場合でも、会社との雇用関係が途切れた時点で打ち切りになるわけではありません。
休業補償受給中に解雇された場合の対処法
労働基準法上、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間、会社は解雇することができませんので、不当に解雇された場合は無効となります。
解雇通告を受けたら、まずはその理由や根拠を確認し、納得がいかなければ専門家に相談しましょう。弁護士に助言を求めると、会社側との交渉や法的手続きのサポートが得られます。
解雇が無効と認定されれば、解雇期間中の賃金に相当する分や、損害賠償を請求できる可能性もあります。焦って解雇を受け入れず、正当な権利を守るために行動しましょう。

骨折で会社や第三者への損害賠償請求は可能?
労災保険以外に、会社の安全配慮義務違反や第三者の過失が認められる場合は、損害賠償請求を検討します。
労災保険は労働者保護のための制度ですが、会社に過失があった場合や、第三者による加害行為で骨折した場合などは、別途損害賠償を請求することが可能です。例えば、安全対策が不十分だった現場で組織的な問題が発覚した場合、会社に対する損害賠償請求の根拠となり得ます。
一方で、労災保険から給付を受け取った場合も、損害賠償請求で一定の金額が減額されるケースがあります。
会社に安全配慮義務違反があるかどうかの判断は複雑で、事実関係の立証が求められるため、必要であれば弁護士等専門家のアドバイスを受けることを検討したほうが良いでしょう。
安全配慮義務違反による会社への損害賠償請求のポイント
会社が労働者の安全を確保するために必要な措置を怠り、それが原因で骨折が発生した場合、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。具体的には、危険箇所の放置や必要な保護具の未支給などが該当します。
安全配慮義務違反が認定されると、慰謝料や逸失利益などの損害賠償を会社に請求できます。
事実関係の調査や必要書類の収集など、負担が大きい手続きを伴うため、会社側が責任を認めない場合は弁護士のサポートを活用しましょう。
見舞金を受け取れるケース
会社独自の慶弔見舞金制度などにより、骨折などのケガに対して見舞金を支給している企業もあります。これは労災保険とは別に支給されるため、申請方法や対象範囲を確認しておきましょう。

労災の骨折に関するQ&A
骨折に関わる労災保険制度について、よく寄せられる疑問をまとめました。
どのような骨折でも労災の対象となるか、パート・アルバイトにも同じ補償が適用されるのかなど、実状に即した疑問がつきものです。制度を正しく理解し、疑問点を解決することでスムーズに給付を受け取りましょう。
疲労骨折など、じわじわと悪化した場合でも業務との因果関係が認められれば、労災が適用されるケースがあります。どこまでが仕事負荷によるものかを客観的に示すためには医師の診断が重要となります。
Q1:疲労骨折でも労災認定される?
疲労骨折は、業務での反復動作や過度の負担が原因で起こることがあります。この場合でも、医師の診断や業務内容との因果関係が証明されれば、労災として認められる可能性があります。
何度も同一部位を痛めている場合や、職場の作業態勢に問題がある場合は早めに会社や産業医と協議し、職場環境の改善策を講じることが重要です。
Q2:パートやアルバイトでも同様に休業補償給付を受け取れる?
労災保険は雇用形態にかかわらず、労働者であれば全員が加入対象となります。そのため、パートやアルバイトであっても業務上や通勤途上のケガであれば労災の休業補償給付を受けられます。
ただし、給付基礎日額の算定については、実際に得ていた賃金が反映されるため、アルバイト・パートの方が受給額は正社員より低くなる傾向にあります。これは賃金総額が低い場合が多いためです。
Q3:通勤災害の範囲|遠回りや寄り道をした場合は?
労災保険で通勤災害と認められる範囲は、自宅と勤務先を合理的な経路及び方法で往復していることが基本です。単なる買い物や寄り道で経路が大きく逸脱していれば、通勤災害と認められない可能性が高まります。
ただし、保育園への子どもの送り迎えなど社会通念上必要とされる行為であれば、合理的経路として認定される可能性があります。通勤経路が複数ある場合も、通勤ルートとして定着していれば認められることがあります。
トラブル回避のためにも、普段から通勤経路を一貫して利用することが望ましいでしょう。
Q4:ボルト除去など追加手術でも休業補償給付は支給される?
骨折治療では、時間が経過してからボルト除去などの再手術を行うケースがあります。こうした手術も、引き続き治療が必要と判断されれば労災の休業補償給付の対象となります。
再手術に伴う休業日が生じる際は、必ず医師の診断書を用意し、労働基準監督署へ届け出ることで引き続き休業補償給付を受け取れる可能性があります。

弁護士に労災の相談をするメリット
労災認定や休業補償給付を巡る問題が起きた場合、弁護士への相談は円滑な解決につながります。
会社が労災の認定に非協力的な態度を取ったり、通勤災害の認定で不当と感じる結果が出たりした場合、法律の専門家のサポートが心強い味方となります。複雑な書類作成や交渉を代理してもらうことで、精神的な負担が軽減されます。
また、会社への安全配慮義務違反や第三者への損害賠償請求など、通常の労災保険手続きとは別の領域に踏み込む場合にも弁護士が活躍します。慰謝料や逸失利益の算定、交渉段階で適正な損害賠償金額を引き出せる可能性が高まるでしょう。
まとめ|骨折による労災補償を理解して早期復帰と適正な保障を目指そう
骨折は治癒まで時間がかかりやすいため、休業補償給付を活用して生活と治療を両立させることが大切です。
労災における骨折の補償は、業務災害・通勤災害の認定や適切な手続きによって手厚くサポートされます。安心して療養を続けるために、会社や労働基準監督署への届け出、医師の診断書の入手などを確実に行い、要件を満たしているかを確認しましょう。
休業補償給付は4日目から支給され、打ち切りは症状固定や職場復帰、傷病補償給付への移行などの段階で行われます。治療が長期化する場合でも継続して補償を受けられる制度がある点は心強いところです。
万一、会社の安全配慮義務違反が疑われたり、休業補償給付の打ち切りが不当と感じたりした場合は、弁護士に相談するとスムーズです。自らの権利を守りつつ、焦らず回復と復帰を進めていきましょう。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説