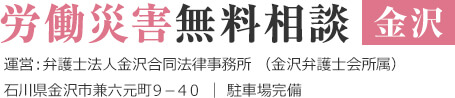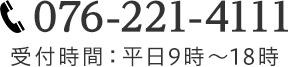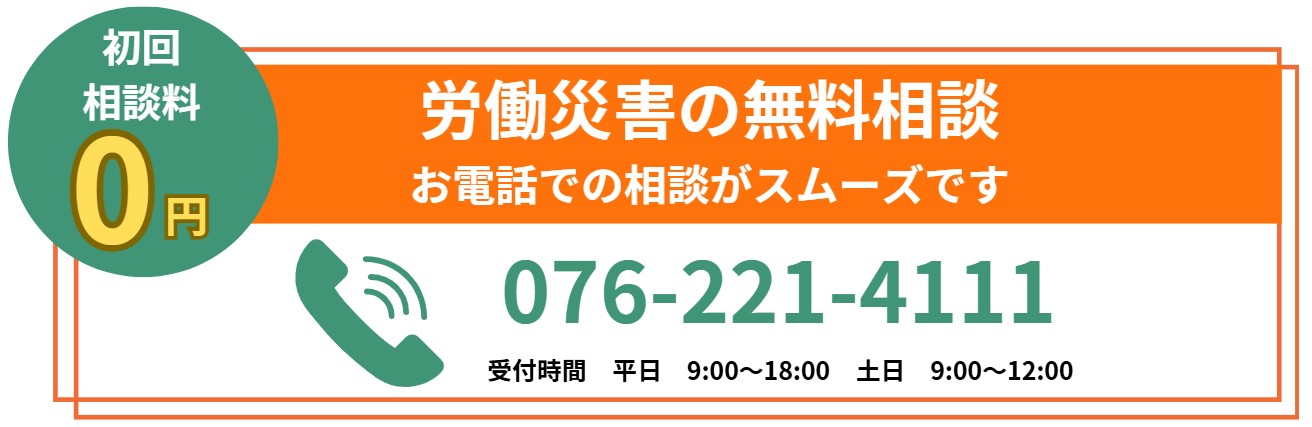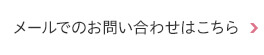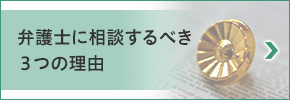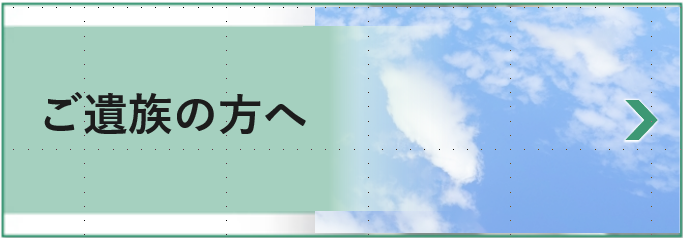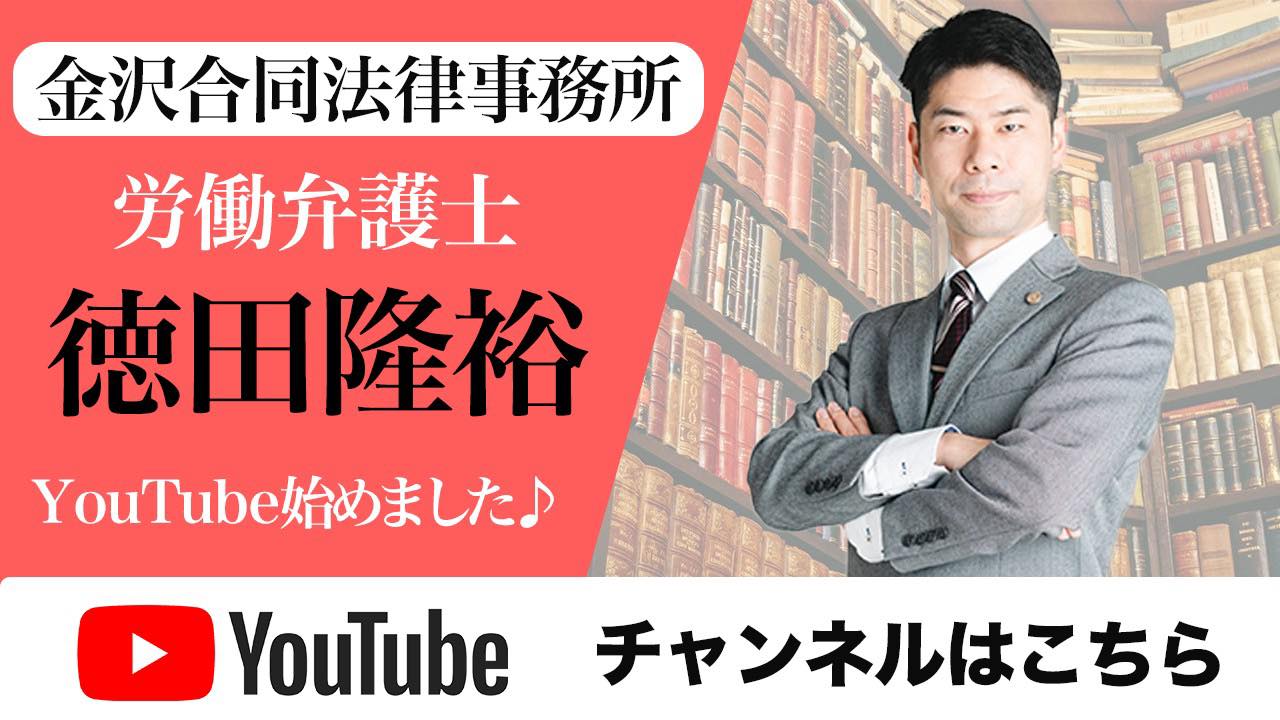複数の職場で勤務していた場合の労災はどうなる?
副業と労災
Q.本業のA社以外にも副業でB社に働いていたところ、過労によってうつ病を発症して、通院治療中です。このような場合、労災の対象になりますか。
複数の職場で勤務していた場合も、労災の対象となります。

複数の職場で勤務していた場合、異なる事業における労働時間や労働日数はそれぞれ通算されます。
うつ病発症前の6ヶ月間に、ある1ヶ月間、A社で70時間の時間外労働を行い、B社で30時間の時間外労働を行えば、1ヶ月の時間外労働は、通算して100時間となり、その他に上司とトラブルがあったり、取引先からクレームを受けたといった出来事があれば、心理的負荷は「強」となり、労災と認定されます。
また、労災保険からの給付は、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割計算した給付基礎日額をもとに計算されるところ、複数の職場で勤務している場合には、その職場ごとの給付基礎日額を合算した額をもとに、支給額が決まります。
そのため、複数の職場で働いている場合には、そのことを労働基準監督署に伝えて、複数の職場での賃金を合算して、労災保険からの給付を算定してもらえるようにする必要があります。
複数の職場で勤務している場合には、複数の職場における心理的負荷の程度や過重性を考慮する必要がありますので、労災申請をするにあたり、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説