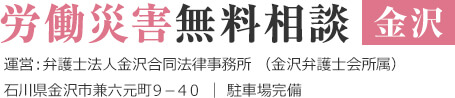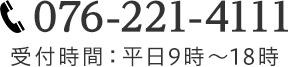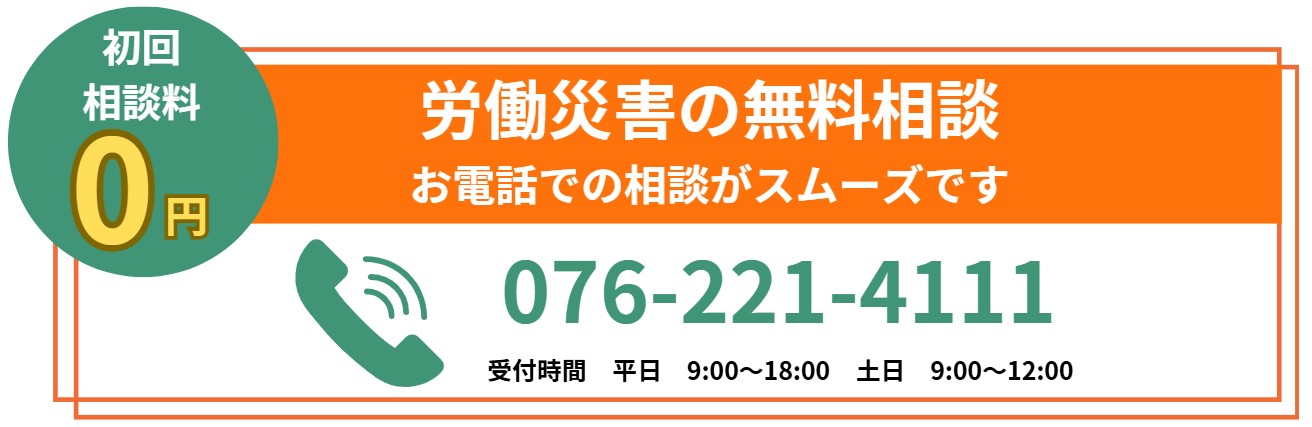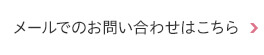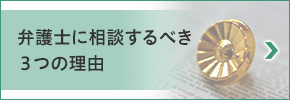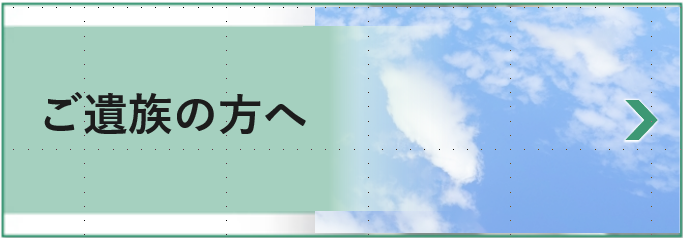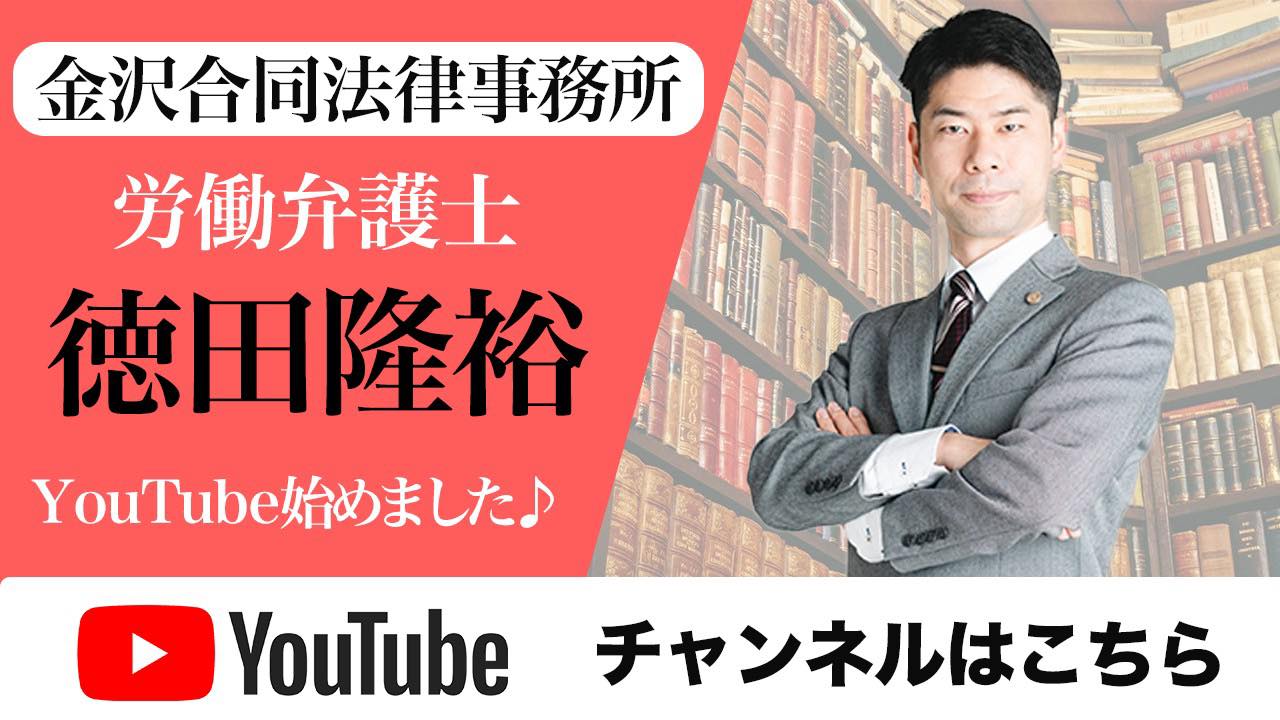振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
建設現場で、チェンソーや削岩機などの振動工具を使用していたところ、手のしびれや感覚異常が発症しました。
医師からは、振動障害と診断されました。
振動障害について、労災と認定されるのでしょうか。また、会社に対して、損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
結論から先に言いますと、振動障害は、一定の条件を満たせば、労災認定され、場合によっては会社に対して損害賠償請求も可能です。
今回は、振動障害の労災認定と損害賠償請求についてわかりやすく解説します。

振動障害とは?
振動障害の症状
振動障害とは、振動工具の振動が、その工具を把持する手指、手掌、腕に刺激を与えるため、振動曝露の継続により、その刺激が手指、手掌、前腕の内部に及び、血管や神経に影響を与えることによって生ずる障害をいいます。
振動障害は、末梢循環障害(手指のレイノー現象や冷感等)、末梢神経障害(手指、前腕のしびれや痛み、知覚異常等)、運動器障害(骨・関節の変形、筋萎縮等)を主体としています。
振動障害における代表的な症状として、手指のしびれや冷え、さらにはレイノー現象と呼ばれる発作的な血流障害が挙げられます。レイノー現象とは、寒冷刺激や精神的ストレスによって、指先などが一時的に蒼白や紫色になる、冷感、しびれ、痛みを伴う現象です。
長期間にわたり振動にさらされると、末梢神経へのダメージが蓄積し、感覚が鈍くなるだけでなく、痛みが強くなったり動かしづらくなったりするケースもあります。
振動障害が進行すると、レイノー現象などの顕著な血流障害が起こりやすくなります。特に低温環境にさらされると手指が白くなったり、しびれが持続したりするため、日常の動作が制限されてしまうこともあります。
さらに、末梢神経障害が悪化すると、ボタンの留め外しや細かい作業に、強い不便を感じる可能性があります。
振動障害は建設業で発症しやすい
建設業は振動工具を多用することから、振動障害のリスクが高い実情があります。
建設業においては、チェンソーやハンマードリル、削岩機など複数の振動工具を使う場面が多く、高い振動ばく露量にさらされることがあります。特に長時間作業が常態化している現場では、労働者が振動障害を発症するケースが多いといえます。
振動障害の労災認定者数において、建設業の占める割合は他の業界と比較しても高いのが現状です。これは、寒冷地での野外作業が多いことや、長時間に及ぶ重労働が求められるためと考えられます。また、安全教育や作業時間管理の徹底が不十分な現場も少なくないことも原因の一つとして挙げられます。

振動障害の労災認定
ここからは、振動障害の労災認定について解説します。
労災認定基準
労災保険では、削岩機、鋲打機、チェンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の抹消循環障害、末梢神経障害又は運動器障害であって、次の要件を満たす場合に、振動障害が労災と認定されます。
1.振動業務に相当期間従事した後に発生した疾病であること。
2.次に掲げる要件のいずれかに該当する疾病であること。
(1) 手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的又は間けつ的に現われ、かつ、次のイからハまでに掲げる障害のすべてが認められるか、又はそのいずれかが著明に認められる疾病であること。
イ 手指、前腕等の末梢循環障害
ロ 手指、前腕等の末梢神経障害
ハ 手指、前腕等の骨、関節、筋肉、腱等の異常による運動機能障害
(2) レイノー現象の発現が認められた疾病であること。
要件1の「振動業務」とは、次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務をいいます。
(1) さく岩機
(2) チッピングハンマー
(3) 鋲打機
(4) コーキングハンマー
(5) ハンドハンマー
(6) ベビーハンマー
(7) コンクリートブレーカー
(8) スケーリングハンマー
(9) サンドランマー
(10) チェンソー
(11) ブッシュクリーナー
(12) エンジンカッター
(13) 携帯用木材皮はぎ機
(14) 携帯用タイタンパー
(15) 携帯用研削盤
(16) スイング研削盤
(17) 卓上用研削盤
(18) 床上用研削盤
(19) (1)から(18)までに掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
要件1の「相当期間」とは、概ね1年又はこれを超える期間をいいます。
振動業務の従事歴が相当期間に満たなかったとしても、振動工具の使用時間が長い場合、休憩時間又は休止時間が少ない場合、未整備の振動工具を使用している場合、未熟練のため振動工具を過度の握力により保持している等の場合には振動障害が起こり得ると考えられるので、次の事項に留意し、個別に業務起因性の判断がなされます。
イ 振動工具の1日当たり使用時間数、1カ月当たり使用日数、使用月数、一連続使用時間数、延使用時間数、寒冷期における使用頻度並びに休憩時間又は休止時間及びその配分
ロ 振動工具の種類、その振動の加速度、振動数及び振幅並びに振動工具の重量及び整備状況
ハ 作業環境(温度条件等)、作業姿勢、作業熱練度及び保護具(手袋、耳栓等)の使用状況
ニ イからハまでに掲げる事項のほか個々の事案に応じて必要と認められる事項
まとめますと、振動レベルが高い工具を1年以上使用し、寒冷地での作業や休憩が十分に取れなかったという状況が重なれば、労災認定の可能性が高まります。
労災保険からの補償
労災と認定されれば、労災保険から、次の補償を受給することができ、労働者にとってメリットが大きいです。
⑴ 療養補償給付
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は様式第7号の文書を使用します。
⑵ 休業補償給付
労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
⑶ 障害補償給付
労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
加えて、振動障害による労災申請の場合、医師の診断書や作業内容、使用工具の種類を証明できる資料も提出します。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

振動障害の損害賠償請求
労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、会社の安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
振動障害の予防対策
厚生労働省は、振動障害の予防対策として、次の措置を講じることが有効であるとしています。
①使用する振動工具は、振動や騒音が出来る限り少なく軽量なものを選び、取扱説明書で示した時期及び方法により、定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つ必要があること。
②振動曝露時間を管理し、連続して振動業務に従事しないようにすること。
③振動工具を使用する労働者に対して、振動障害予防のための特殊健康診断を定期的に行い、その結果に基づく就業上の措置を行うこと。
④適切な暖房設備を有する休憩室等を設けること。
⑤防振手袋等の保護具を支給し、使用させること。
⑥手、腕、肩、腹等の運動を主体とした体操を行うこと。
⑦振動工具を使用する労働者に対して、安全衛生教育を行うこと。
会社がこれらの振動障害の予防対策を何もしていなかった場合、安全配慮義務違反が認められることになります。
振動障害で安全配慮義務違反を認めた裁判例の紹介
ここでは、振動障害で安全配慮義務違反を認めた裁判例を紹介します。
⑴ 三菱重工業(神戸造船所)事件・神戸地裁平成6年7月12日判決
原告ら被災労働者は、造船所における就労中に振動暴露を受けて、振動障害に罹患したことについて、会社に対して、安全配慮義務違反の損害賠償請求をしました。
裁判所は、原告らの振動障害について、次の安全配慮義務違反を認めました。
①従業員に対して、振動暴露を受けさせないようにするため、振動工具を使用させない義務及び同義務の内容として、作業工法の改善と振動工具そのものの改善による振動発生の抑止、次善の策としての防振保護具等の活用による振動暴露の防止。
②作業時間の制限、工具使用上の注意・教育、健康診断の実施、作業環境の改善
これらの安全配慮義務違反が認められ、原告らの損害賠償請求が認められました。
⑵ 日本冷熱事件・熊本地裁令和6年4月24日判決
原告は、長時間の振動作業に従事したことによって、手指前腕のしびれ、痛み、こわばり等の振動障害を発症したとして、会社に対して、安全配慮義務違反の損害賠償請求をしました。
裁判所は、会社が次のことをしていなかったことを根拠に、安全配慮義務違反を認めました。
①防振装置を付けた防振工具や防振手袋の支給
②振動作業の時間の管理や作業方法の指導
③暖房設備や温水供給設備を備えた休憩室の設置
これらの安全配慮義務違反が認められ、原告の損害賠償請求が認められました。
⑶ 兵庫県公立大学法人(振動病)事件・神戸地裁姫路支部令和7年1月23日判決
原告は、充電式チェンソー、エンジン付刈払機、植木バリカン、自走式草刈機を使用して作業をしていたこところ、振動病を発症したとして、勤務していた大学法人に対して、安全配慮義務違反の損害賠償請求をしました。
裁判所は、原告に対し、振動工具の使用時間を確認したり、作業計画を策定し、その計画に従って作業を行う旨指示するなどの義務があったにもかかわらず、被告大学法人は、原告の振動工具の使用時間を把握せず、その使用時間や程度に応じて、適切な作業計画を策定していないのであるから、安全配慮義務違反が認められました。
その結果、267万円の損害賠償請求が認められました。
このように、労災保険では補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説