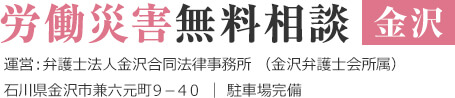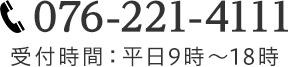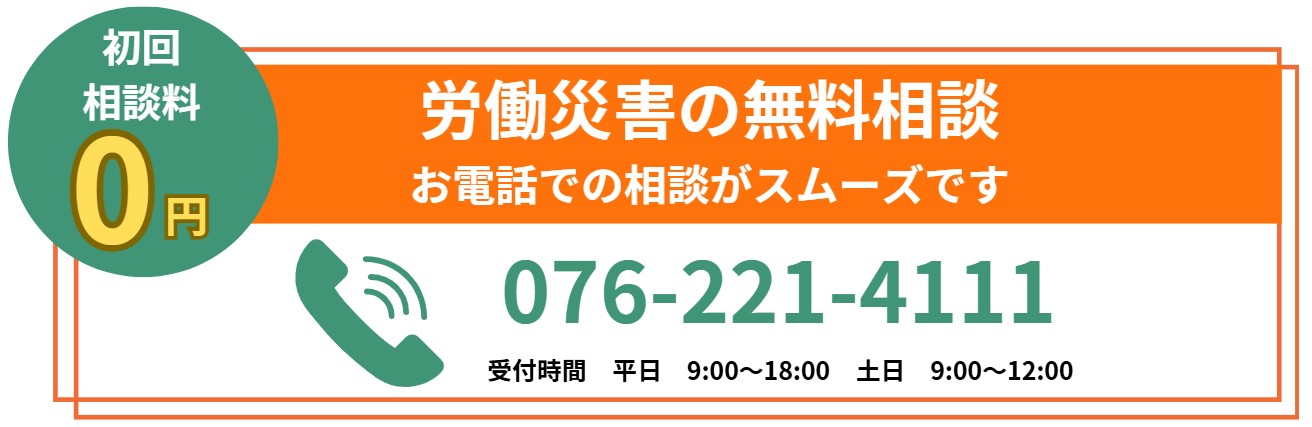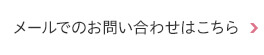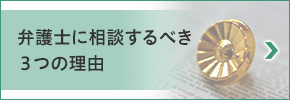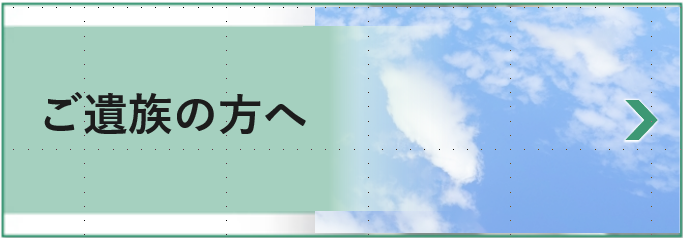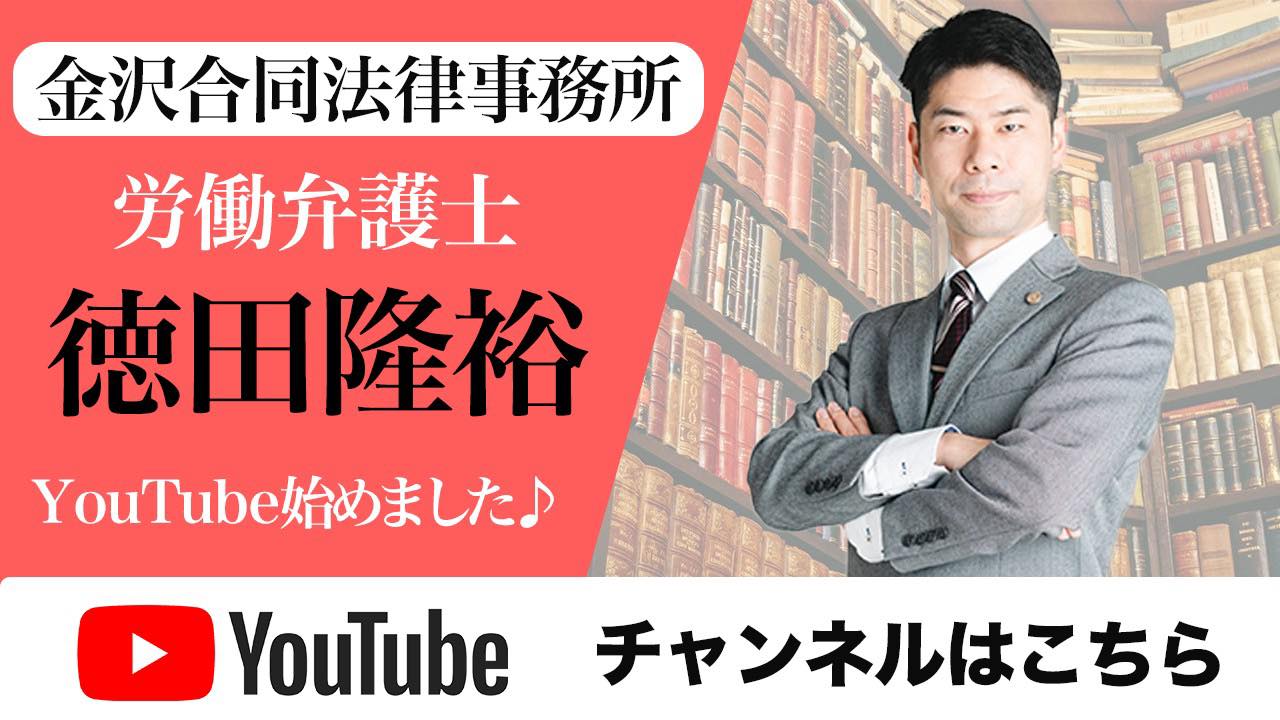仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
屋外の建設現場で仕事をしていたところ、気温がどんどんあがり、熱中症になり、倒れてしまいました。
重度の熱中症と診断され、脳に障害が残るかもしれないと言われています。
仕事中に熱中症になった場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。
結論から先にいいますと、仕事中に熱中症になった場合、労災保険から補償を受けられ、場合によっては、会社に対する損害賠償請求が認められることもあります。
今回は、熱中症の労災と損害賠償請求について、わかりやすく解説します。

1 熱中症による労災が増えている
職場における熱中症による労災事故は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年増加傾向にあります。
令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と、厚生労働省の調査開始以来最多を記録しました。
特に、仕事中の熱中症による死亡の人数は、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあります。
仕事中に熱中症が発症した件数が多いのは、1位建設業、2位製造業、3位運送業となっております。

2 熱中症が労災になる場合とは
⑴ 熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称をいいます。
熱中症の症状としては、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等があげられます。
熱中症が重度になると、脳に障害が残ることもあり、最悪、死亡に至ることもありえます。
⑵ 熱中症の労災認定基準
仕事中に熱中症を発症した場合、次の2つの労災認定基準の要件を満たした場合、熱中症が労災と認定されます。
①熱中症を発症したと認められること(医学的診断要件)
熱中症を発症したと認められるためには、作業環境や気温等のデータに加えて、他の疾病ではなく熱中症を発症していることが、外見や体温などからも診断できることが必要でして、次のabcによって判断します。
a 作業条件及び温湿度条件等の把握
b 一般症状の視診(痙攣・意識障害等)及び体温の測定
c 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断
②熱中症の発症が業務に起因すること(一般的認定要件)
次のabcを総合判断して認定します。
a 業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる原因が存在すること
b 当該原因の性質、強度、これらが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
c 業務に起因しない他の原因により発病したものではないこと
具体的にどれくらいの温度・湿度や作業強度だと、熱中症になる危険が大きくなるかといいますと、WBGT値という暑さ指数が基準値を超える状況であれば、熱中症を発症する危険が大きくなり、労災認定の可能性が高くなります。
特に、WBGT値が31℃を超えるような状況であれば、どのような作業状況であっても熱中症を発症する危険が大きい状態であるといわれています。
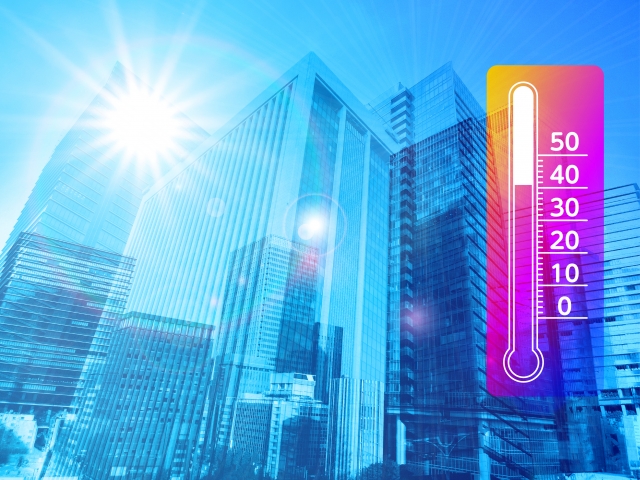
3 仕事中に熱中症になったら労災申請をする
仕事中に熱中症を発症した場合、必ず労災申請をしてください。
労災申請をして、熱中症が労災と認定されれば、以下のような補償を受けることができ、被災労働者の生活が安定します。
⑴ 療養補償給付
労災保険を利用することができれば、仕事中の熱中症の治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。
⑵ 休業補償給付
また、仕事中の熱中症の治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
⑶ 障害補償給付
そして、仕事中の熱中症によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑷ 労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
厚生労働省の労災申請の書式については、こちらのサイトをご参照ください。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

4 会社に対する損害賠償請求
⑴ 労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
⑵ 安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
熱中症の場合、厚生労働省が、令和3年に、「職場における熱中症予防基本対策要綱」を策定して公表しており、会社が行うべき、熱中症の予防対策として、次のことがあげられています。
①作業環境管理
a WBGT値(暑さ指数)の低減
高温多湿の作業場所において、発熱体と労動者の間に熱を遮ることのできる遮蔽物等を設けること
屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設けること
高温多湿作業場所に適度な通風又は冷房を行うための設備を設けること
b 休憩場所の整備
高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること
高温多湿作業場又はその近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設けること
水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えるよう高温多湿作業場所に飲料水等の備え付けを行うこと
②作業環境
作業時間の短縮、熱への順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)、水分及び塩分の摂取、透湿性及び通気性のよい服装を着用させること、作業中の巡視、連絡体制の整備
③健康管理
健康診断の実施、労働者への健康管理指導、作業開始前の労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認
④労働衛生教育
労働者に対する熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急措置、熱中症の事例等についての労働衛生教育
そして、会社がこのような措置をとらずに、労働者が仕事中に熱中症を発症した場合、会社は、安全配慮義務違反に該当し、損害賠償責任を負うことになります。
⑶ 裁判例の紹介
仕事中の熱中症の損害賠償請求の裁判例を紹介します。
大阪高裁平成28年1月21日判決です。
この事件では、造園業の会社に雇用されて、気温39℃、湿度45%で、WBGT値が33℃の現場において、伐採・清掃作業中に熱中症を発症して死亡した労働者の遺族が、会社に対して、安全配慮義務違反の損害賠償請求を提起しました。
裁判所は、この事件における会社の安全配慮義務について、次のように判断しました。
「日頃から高温環境下において作業員が具合が悪くなり熱中症と疑われるときは、作業員の状態を観察し、涼しいところで安静にさせる、水やスポーツドリンクなどを取らせる、体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水を掛けながら風を当て、氷でマッサージするなど体温の低下を図るといった手当を行い、回復しない場合及び症状が重い場合などは、医師の手当てを受けさせること等の措置を講ずることを教育していく義務があったというべきである。」
そして、現場監督者が、被災した労働者の具合が悪くなったことを認識した後、被災した労働者の状態を確認しておらず、高温環境を脱するために適切な場所での休養をさせることをせず、そのまま現場に放置し、熱中症による心肺停止状態に至る直前まで、救急車を呼ぶ等の措置をとらなかったことから、会社は、現場監督者に対して、労働安全教育をしていないとして、安全配慮義務違反が認められました。
結果として、会社に対して、36,070,835円の損害賠償請求が認められました。
このように、仕事中に熱中症を発症した場合、会社が熱中症対策を何もしていなかったならば、会社に対して、損害賠償請求ができることがあります。
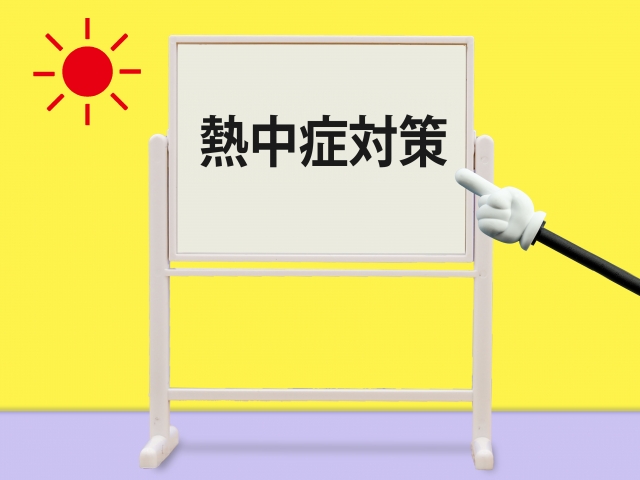
5 令和7年6月労働安全衛生規則改正
仕事中の熱中症による死亡の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために、令和7年6月に、労働安全衛生規則が改正され、事業者が講ずべき措置について、新たな規定が設けられました。
⑴ 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合、又は、当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合に、その旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければなりません。
すなわち、会社は、熱中症の疑いがある場合に、報告をさせる体制を整備しなければならないのです。
具体的には、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労動者双方向での定期連絡やこれらの措置の組み合わせが挙げられます。
また、会社は、熱中症の疑いがある場合に、報告をさせる体制を整備したことを、労動者に周知しなければなりません。
周知の方法としては、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることなどが挙げられます。
⑵ 事業者が熱中症による健康障害を防止すべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせること、その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければなりません。
すなわち、熱中症を発症した労動者を発見した場合のどのような処置をすべきかについての手順を定めて、労動者に周知することが義務化されました。
具体的には、熱中症のおそれのある労動者を発見→作業離脱、身体冷却→医療機関への搬送、といった処置の手順を作成して、労動者へ周知しなければならないのです。
また、事業場における緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先を定めた場合には、これらも周知する必要があります。
このように、令和7年6月の労働安全衛生規則の改正により、会社が熱中症対策として取り組まなければならないことが増えたため、労動者側としては、安全配慮義務違反の主張をしやすくなったと考えられます。
仮に、仕事中に熱中症を発症した場合、上記の義務を会社が遵守していたかを検討し、会社に対して、安全配慮義務違反による、損害賠償請求ができないかを見極めていきます。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説