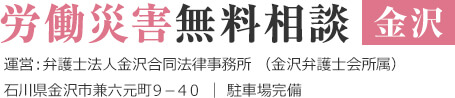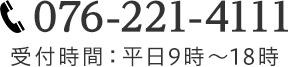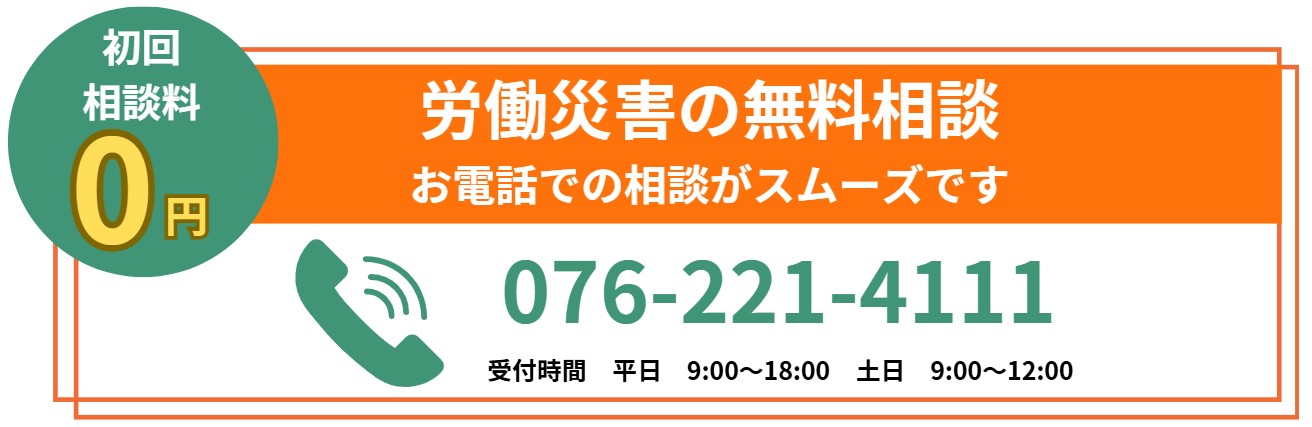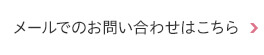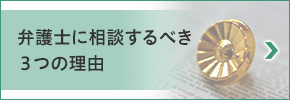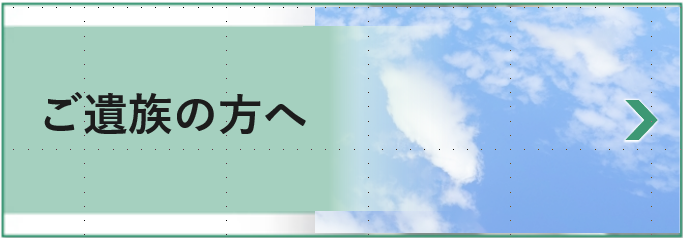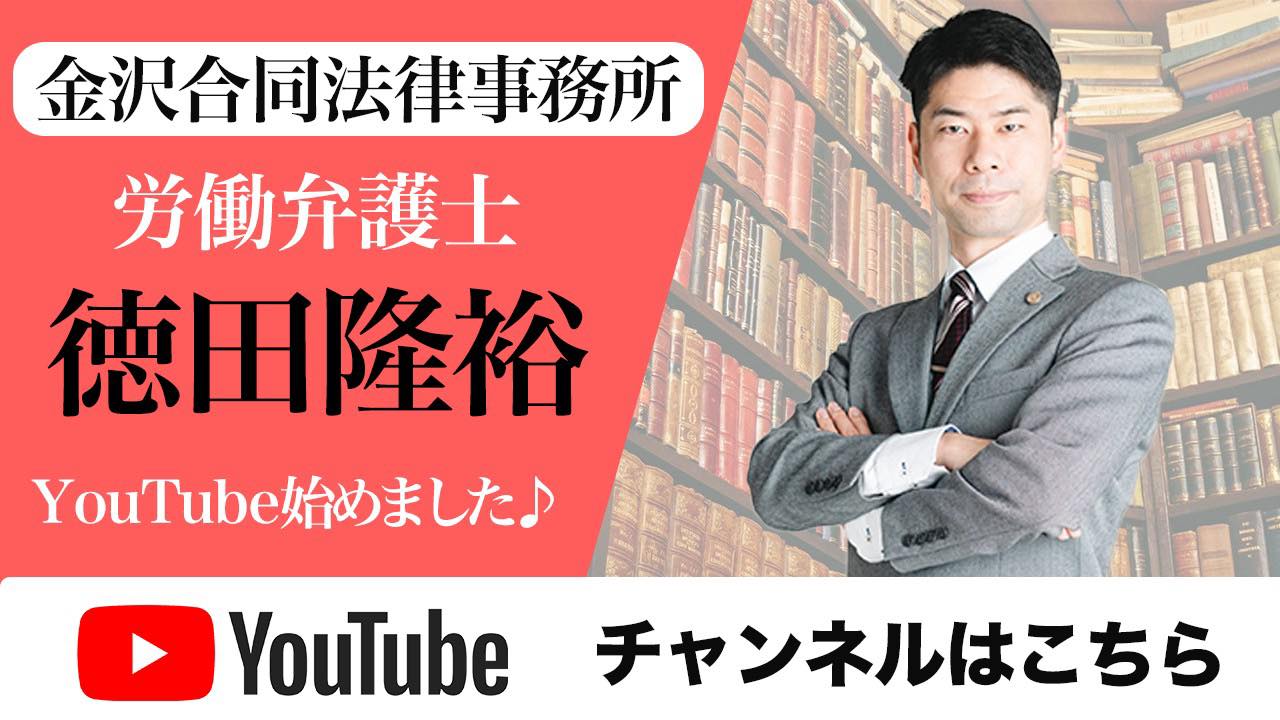労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
夫が建設現場で働いていたところ、高所から転落して、重傷を負いました。
今後の治療費や生活費の工面などで不安がいっぱいです。
家族が労災事故に巻き込まれてしまった場合、どのような補償を受けることができるのでしょうか。
労災保険を利用することで、治療費が無料になり、会社を休業している期間、給料の約8割が支給されます。
また、場合によっては、会社に対する損害賠償請求を検討します。
今回は、労災事故によって、家族が重傷を負った場合、労災保険からどのような補償を受けることができるのか、会社に対して損害賠償請求ができるのかについて、弁護士が分かりやすく解説します。

1 労災保険とは
労災保険は、業務中や通勤途中に起きたケガや病気、障害、死亡に対して、国が労働者やその遺族に補償を行う公的な保険制度です。
労働者を一人でも雇っている事業所であれば、原則としてすべての労働者が加入対象となります(パート・アルバイトを含む)。
仮に、会社が労災保険の届出や加入手続をしていなかったとしても、労働者は、当然に労災保険の適用を受け、労災保険からの補償を受給することができるのです。
業務災害と通勤災害
業務災害とは、業務そのものや業務に付随する行為が原因となって起きた労災事故をいいます。業務災害は、労働者が労働契約に基づき会社の支配下にあるという業務遂行性と、業務に内在する危険が現実化したという業務起因性の2つの要件が認められる必要があります。
具体的には、次の場合、業務災害に該当します。
- 工場での作業中に機械に巻き込まれてケガをした
- 高所作業中に転落した
- 長時間労働で脳や心臓の疾患を発症した
- 業務上のストレスでうつ病になった
他方、通勤災害は、住居と就業の場所を往復する際の合理的な経路や方法を用いた移動中に発生する負傷や疾病、死亡をいいます。通勤災害が認められるためには、就業の場所と住居の間を合理的な方法や経路で移動している最中に起きた事故であることが大前提です。公共交通機関や徒歩、自転車、マイカーなど、普段利用している手段で通勤している場合に適用される可能性があります。
労災保険と健康保険の違い
①治療費
労災保険の場合、治療費が全額支給されます。
健康保険を利用した場合、原則として、治療費の3割が自己負担となります。
②休業期間中の賃金の補償
労災保険の場合、給料の約80%分が補償されます。
健康保険の傷病手当金として、給料の3分の2が補償されます。
③後遺障害の補償
労災保険の場合、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
健康保険には、後遺障害の補償はありません。
このように、労災保険と健康保険を比べると、労災保険からの補償が手厚いことがわかります。
労災事故に巻き込まれた場合、健康保険を利用するのではなく、必ず、労災保険を利用するようにしてください。

家族が労災事故で重傷を負った場合にするべきこと
突然の労災事故で、家族が重傷を負ってしまった時、ショックと混乱で、何から手を付けていいのか分からないかもしれません。
ここでは、労災事故後、まずすべきことを解説します。
⑴ 医療機関での治療
病院には、必ず、労災事故で負傷したことを伝えてください。病院に、労災事故であることを伝えることで、適切な診断書の作成や、労災申請に必要な手続の協力を得やすくなります。
受診している病院が、労災指定医療機関であれば、労災保険の様式5号を病院に提出すれば、自身で治療費を支払う必要がなく、無料で治療を受けることができます。
他方、受診している病院が、労災指定医療機関でないならば、いったん、治療費全額を病院の窓口で支払い、治療費の領収書と一緒に、労災保険の様式7号を、労働基準監督署へ提出すれば、後日、労災保険から、治療費が振り込まれます。
⑵ 労災事故の状況の記録化
労働基準監督署に、労災と認定してもらうためには、労災事故の発生状況を、詳細に、正確に記録することが必要となります。
労災事故に巻き込まれた場合、次のことを文書に残す、写真で記録することをおすすめします。
- 事故発生の日時・場所
- 業務内容や作業指示の内容
- 事故が発生した具体的な経緯(例:機械の故障、転落など)
- 目撃者の有無や証言
- 安全装置・マニュアルの有無と遵守状況
また、会社に労災事故の状況を報告します。会社に労災事故を報告した場合、会社が労災隠しをすることがあります。
しかし、労災隠しは犯罪ですので、会社からの労災隠しの圧力に屈してはならず、必ず、労災申請をしてください。労災隠しされそうな場合には、弁護士へご相談ください。
⑶ 今後の生活・収入の見通しをたてる
労災事故によって重傷を負った場合、長期の入院・療養・復職困難といった状況により、被災労働者の収入が著しく減少する可能性があります。
場合によっては、家族が介護や看護にあたるために離職や休職を余儀なくされるケースもあります。
そのため、労災保険から、どのような補償を受けることができるのかを理解することが重要です。労災認定まで、時間がかかる場合には、先に、健康保険の傷病手当金を受給することを検討します。
また、労災保険からの補償を受けられるようになった場合、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
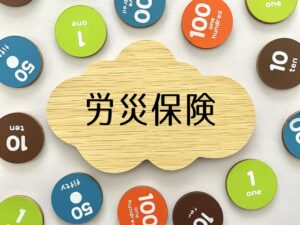
労災保険からの補償
労災事故によって重傷を負った場合、被災労働者や家族に重い負担が生じますので、労災事故による補償を必ず受けてください。
そのため、労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
ここからは、労災と認定された場合の、労災保険からの補償について、解説します。
⑴ 療養補償給付
労災申請をして、労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
⑵ 休業補償給付
労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
⑶ 傷病補償給付
労災事故によるケガの治療を開始して、1年6ヶ月を経過しても、ケガが治癒しておらず、そのケガの障害の程度が重篤な場合、労災保険から年金が支給されます。
傷病等級1級から3級に該当する、重篤な傷病の場合に限って支給されます。
⑷ 障害補償給付
労災事故によるケガが、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、第10号の様式と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑸ 介護補償給付
労災事故によって重篤な後遺障害が残った場合に受ける介護に対する給付を、介護補償給付といいます。
後遺障害等級で1級又は2級と認定され、常時又は随時の介護が必要な状態になっている場合に、支給を受けることができます。
労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社に労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

会社に対する損害賠償請求
労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、会社の安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
逸失利益と慰謝料
労災事故によって、重傷を負い、後遺障害が残った場合、会社に対する損害賠償請求で重要になるのは、逸失利益と慰謝料です。
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。労災事故によって、後遺障害が残り、労働能力が一定程度喪失ことによって、収入が減少した損害の賠償を請求できるのです。年収が大きい成人の場合、逸失利益が数千万円になることが多いです。
労災事故の損害賠償で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
入通院慰謝料については、入院の月数と通院の月数から計算します。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
労災事故によって、重傷を負った場合、入通院期間が長期化し、重度の後遺障害が残った場合、慰謝料が数千万円になることが多いです。
このように、労災保険では補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。

弁護士に労災事件を依頼するメリット
⑴ 安全配慮義務違反の立証と証拠収集の支援
労災事故の損害賠償請求では、会社の安全配慮義務違反を被害者側が立証する必要があります。
弁護士は労災事故状況の調査、証拠の収集、過去の裁判例等をもとに、的確な立証と主張を行い、被害者の損害の回復が最大限になされるように支援します。
⑵ 会社との交渉を任せられる
会社は、労災事故における損害賠償金の支払いを、できるだけ抑えようと、様々な主張をしてきます。
弁護士が代理人となることで、交渉力が格段に高まり、適正な損害賠償金を受けやすくなります。
⑶ 家族の精神的・時間的負担の軽減
労災事故後は、家族が介護・医療手続き・生活再建などに追われます。
法的な部分を弁護士に任せることで、家族が本当に必要なサポートに集中できるようになります。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説