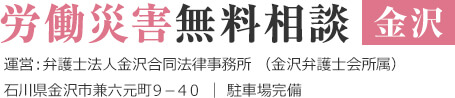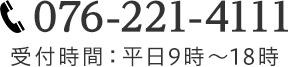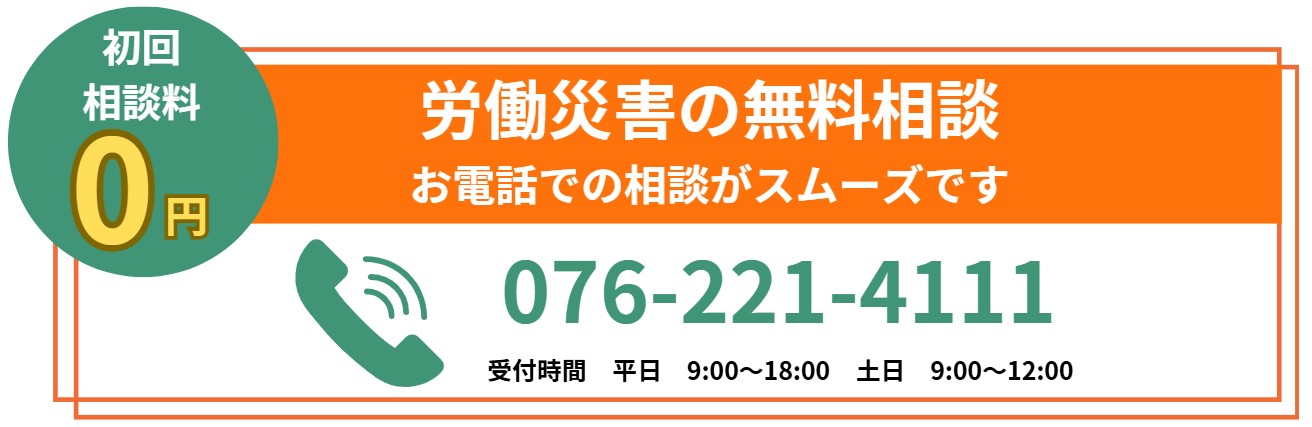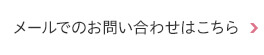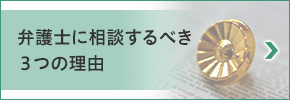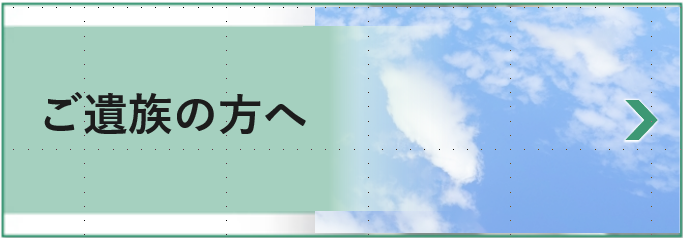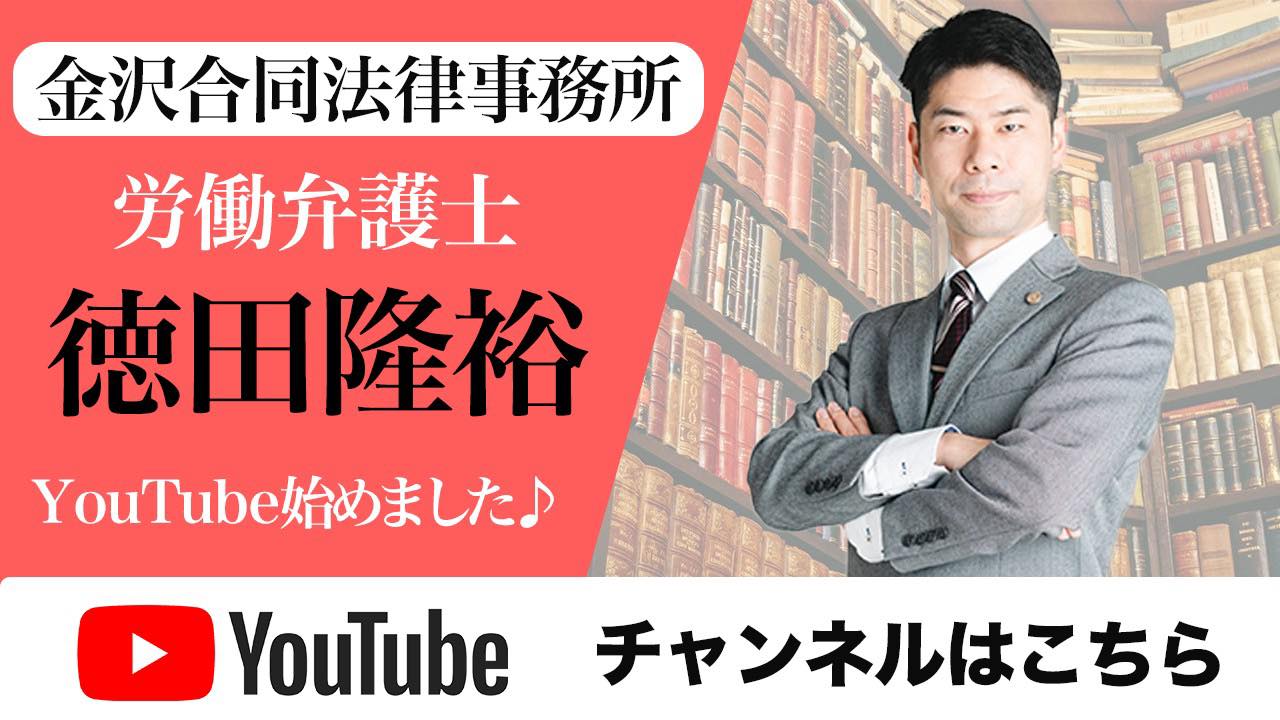下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説
下請業者のもとで、災害の復旧・復興工事の現場で働いていたところ、労災事故に巻き込まれてしまい、重症を負いました。
労働契約を締結していた下請業者は、零細企業であり、損害賠償請求をしても、資力がなく、回収が難しそうなので、建設現場で、元請業者の従業員から、業務指示を受けて働いていたことから、元請業者に対して、損害賠償請求をできないのでしょうか。
結論から先にいいますと、元請業者と下請業者の労動者との間に、実質的な指揮監督関係がある場合には、元請業者に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。
今回は、建設現場における、下請業者の労動者が、元請業者に対して、損害賠償請求する方法について、わかりやすく解説していきます。

1 石川県における公費解体の労災事故の増加
2024年1月1日に発生した能登半島地震、及び、2024年9月に発生した能登半島の豪雨災害で、多くの家屋が被災し、2025年3月時点において、公費解体が進んでいます。
公費解体や復旧・復興関連の工事が進むにつれ、石川県内では、労災事故の発生件数が増加しています。
石川労働局の発表によりますと、2025年1月末までに、能登半島地震や豪雨災害の復旧・復興関連の工事で、石川県内で、58件の労災事故が起き、3人が死亡しているようです。
58件の労災事故のうち、半数は公費解体の現場で発生しており、増加傾向が見られ、労災事故の形態としては、屋根やはしご等からの転落事故が半数ほどを占めているようです。
具体的には、次のような労災事故が発生しています。
①木造家屋解体工事の労災事故
道具を取り出すため、廃棄物運搬用のトラックの運転席後部と荷台の間の講台に乗ったところ、体勢を崩して、荷台内側に墜落し、荷台内にあった屋根瓦に側頭部が激突し、死亡した。
②埋設排水管修繕工事における労災事故
修繕作業中に、被災者が重機で誤って切断した電気配線及び配管を復旧していた際、配管を揺さぶったところ、掘削した法面が崩れて土砂に埋まり、背部等を骨折した。
③仮設住宅工事における労災事故
天井に部材取り付け作業中、はしごを上る途中で体勢を崩し、約2メートルの高さから墜落して、背部を負傷した。
このように、復旧・復興工事の現場において、労災事故に巻き込まれた場合、必ず、労災申請をしてください。
2 労災保険からの補償
⑴ 療養補償給付
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。
⑵ 休業補償給付
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
⑶ 障害補償給付
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑷ 労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
厚生労働省の労災申請の書式については、こちらのサイトをご参照ください。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

3 雇用されている会社に対する損害賠償請求
⑴ 労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
⑵ 安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、高所からの転落や墜落の労災事故の場合、会社は、高さが2メートル以上の箇所で、労働者に作業をさせる場合、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置するか、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させなければなりません(労働安全衛生規則518条)。
また、会社は、スレートでふかれた屋根の上で、労働者に作業をさせる場合、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を貼る等踏み抜きによる危険の防止の措置をとらなければなりません(労働安全衛生規則524条)。
そのため、会社が、労動者に高所で作業させるにあたって、作業床を設置しなかった、歩み板を設置しなかった、防網を張っていなかった、安全帯を使用させなかった場合に、会社に安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
⑶ 後遺障害5級の場合にいくらの損害賠償請求ができるのか?
それでは、公費解体の作業中に、屋根から転落して、背部を負傷し、脊髄を損傷して、後遺障害の第5級の1の2の「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当した場合、会社に対して、いくらくらいの損害賠償請求ができるのかを計算してみます。
毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円、年収420万円の40歳の労働者が、10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害5級と認定されたケースで、損害賠償請求の金額を計算してみます。
ここでは、労災事故の損害賠償請求で大きな金額になる、①休業損害、②逸失利益、③慰謝料を計算します。
①休業損害
まず、労災事故後に会社を休んでいた期間の休業損害を計算します。
休業損害は、収入日額に休業日数をかけて計算します。
収入日額は、労災事故前3ヶ月間の給料総額を期間の総日数で割って計算するので、労災保険の給付基礎日額の計算とほぼ同じです。
今回のケースの場合、収入日額は、7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,783円
休業日数が330日であれば、休業損害は、9,783円×330日=3,228,390円となります。
もっとも、休業損害からは、労災保険から支給された休業補償給付を控除します。
休業補償給付は、給料の約80%が支給されますが、80%のうちの20%の休業特別支給金は控除されません。
そのため、休業損害から控除されるのは、給料の約60%分である休業補償給付だけです。
例えば、今回のケースで、給料の約60%分である休業補償給付として、1,937,034円が支給されていた場合、会社に対して請求できる休業損害は、3,228,390-1,937,034=1,291,356円となります。
②逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
逸失利益は、次の計算式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、労災事故の前年の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害によって、労働者の労働能力がどれくらいの割合で喪失したかを算出するものです。
後遺障害5級の場合、労働能力喪失率は、79%です。
労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力が喪失された期間のことで、原則として、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて計算します。
今回のケースの場合、40歳で症状固定なので、労働能力喪失期間は、27年間となります。
ライプニッツ係数とは、労災事故などの損害賠償金に生じる中間利息を控除するための係数です。
逸失利益の損害賠償請求では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることなります。
その損害賠償金を運用すると利息が生じるので、この利息分を控除するために、ライプニッツ係数を使用します。
27年に対応するライプニッツ係数は、18.3270です。
今回のケースで逸失利益を計算すると、次のとおりとなります。
420万円×79%×18.3270=60,808,986円
この逸失利益の金額から、障害補償給付のうち、これまでに受給した障害補償年金を控除します。
障害補償給付のうち、障害特別年金と障害特別支援金は控除されません。
今回のケースで、これまでに受給した障害補償年金が1年間分の1,800,072円とした場合、会社に対して請求できる逸失利益は、60,808,986-1,800,072=59,008,914円となります。
③慰謝料
労災事故の損害賠償で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
入通院慰謝料については、入院の月数と通院の月数から計算します。
例えば、入院2ヶ月、通院8ヶ月の場合、入通院慰謝料は、164万円になります。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
後遺障害5級の場合、後遺障害慰謝料は、1400万円になります。
このように、労災保険では補償されない損害について、雇用されている会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。
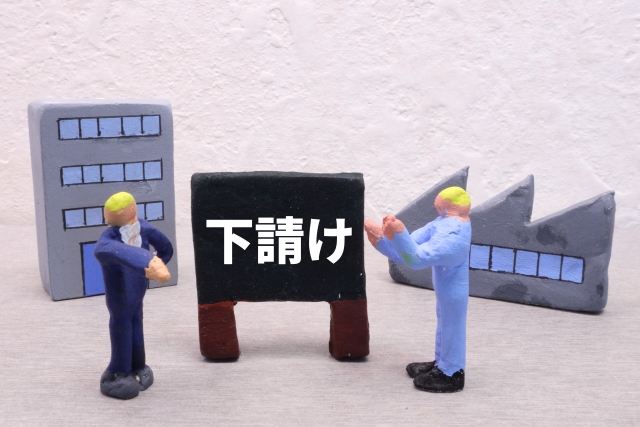
4 元請業者に対する損害賠償請求
⑴ 実質的な指揮監督関係があるか
公費解体や災害の復旧・復興工事では、労動者に重篤な後遺障害が残る労災事故が発生することがあり、前述したとおり、損害賠償の金額が膨大になることがありえます。
もっとも、被災した労動者の直接の雇用主が、零細な下請業者の場合、下請業者に対して、膨大な損害賠償請求をしても、下請業者に資力がないために、下請業者から、損害賠償金を回収できないリスクがあります。
そのような場合、資力が十分に見込める、元請業者に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
元請業者と、下請業者の労動者との間には、労働契約関係はありませんが、元請業者が、下請業者の労動者に対して、実質的に指揮監督を行っており、元請業者に安全配慮義務違反が認められれば、下請業者の労動者は、元請業者に対して、損害賠償請求をすることができます。
それでは、どのような場合に、元請業者と下請業者の労動者の間に、実質的な指揮監督関係が認められるのでしょうか。
具体的には、次の①~⑩の事情を総合考慮して、実質的な指揮監督関係があるのかを判断します。
①現場事務所の設置、係員の駐在ないし派遣
②作業工程の把握、工程に関する事前打ち合わせ、届出、承認、事後報告
③作業方法の監督、仕様書による点検、調査、是正
④作業時間、ミーティング、服装、作業人員等の規制
⑤現場巡視、安全会議、現場協議会の開催、参加
⑥作業場所の管理、機械・設備・器具・ヘルメット・材料等の貸与・提供
⑦管理者等の表示
⑧事故等の場合の処置、届出
⑨専属的下請関係か否か
⑩元請企業の組織的な一部に組み込まれているか、構内下請けか
また、労働基準法87条1項の規定も、元請業者に対する損害賠償請求を検討する上で、役立ちます。
労働基準法87条1項では、建設業において、数次の請負によって行われる場合には、原則として、元請業者を災害補償義務者とすると規定されています。
すなわち、建設業においては、下請・孫請など数次の下請によることが慣行化されており、その工事に関する危険負担は、事実上元請業者が負担する場合が多いこと、下請業者は補償義務を負担する能力のない場合が多いことから、労働災害補償については、元請業者を使用者とみなして、元請業者に補償を行わせることにしたのです。
このように、元請業者と下請業者の労動者との間に、実質的な指揮監督関係が認められた場合、次に、元請業者に安全配慮義務違反が認められるかを検討します。
⑵ 元請業者の安全配慮義務違反
労働安全衛生法では、同じ場所において行う事業の仕事の一部を下請業者に請け負わせている事業者を元方事業者といい、建設業の元方事業者を特定元方事業者といいます。
この特定元方事業者は、労働安全衛生法30条において、労働災害を防止するために、次のような必要な措置を講じなければならないのです。
①協議組織の設置及び運営
②作業間の連絡及び調整
③作業場所の巡視
④教育に対する指導及び援助
⑤仕事の工程に関する計画等の作成
⑥建設機械等の作業計画等に関する指導
⑦建設現場の状況等の周知
元請業者が、上記①~⑦の措置を講じておらず、労災事故が発生した場合、元請業者に安全配慮義務違反が認められ、元請業者に対して、損害賠償請求ができます。
このように、下請業者の労動者が、元請業者の指揮命令に従って働いていて、労災事故に巻き込まれた場合、元請業者に対して、損害賠償請求をすることを検討します。
⑶ 労災の死亡事故における多重請負関係会社に対する損害賠償請求が認められた裁判例の紹介
ここでは、雇用主以外の会社に対する損害賠償請求が認められた裁判例を紹介します。
今回、紹介する裁判例は、一光ほか事件の名古屋高裁令和6年11月6日判決(労働判例1339号29頁)です。
この事件は、建設工事現場において、水管橋の足場資材の搬出作業に従事していた、当時17歳の被災労働者が、地上12.9メートルに位置する歩廊またはその横桁から用水路に転落して死亡した労災事故について、ご遺族が、元請業者、一次下請業者、二次下請業者、労働者派遣元、実質的な雇用主に対して、損害賠償請求をしました。
実質的な雇用主について、被災労働者を仕事に従事させるに当たっては、その年齢や経験等から適当な仕事であるか、実際の現場の指揮監督が適正に行われているかを確認し、従事させる仕事を選択し、仕事内容に応じた適切な指導をするなどして、被災労働者の生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていました。
しかし、実質的な雇用主は、送り出し教育を含めた安全衛生教育を実践したことは全くうかがわれず、本件解体作業につき、その年齢や経験等から適当な仕事であるか、実際の現場の指揮監督が適正に行われているかなどの確認をしていなかったとして、安全配慮義務違反が認められました。
労働者派遣元について、被災労働者を派遣する者として、被災労働者の従事する作業の内容を把握し、危険な業務が行われるおそれがあるときには、その差止めあるいは是正を派遣先に求め、また、必要に応じて派遣を停止するなどして、被災労働者が危険な業務に従事することによって、生命身体の安全を損なうことのないよう予防すべき注意義務を負っていました。
しかし、派遣元は、被災労働者が17歳であるにもかかわらず、高所作業を伴う解体作業に作業員として派遣し、被災労働者にヘルメットを貸与し着用させた以外に安全に配慮した形跡が全くないことから、安全配慮義務違反が認められました。
二次下請業者について、自身の従業員を安全衛生責任者及び主任技術者として、職務を行わせ、被災労働者を直接指揮監督下において、解体作業に従事させていたことから、被災労働者の生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていました。
しかし、二次下請業者は、安全衛生教育を実施しておらず、被災労働者をして墜落制止用器具の胴ベルトを装着させずに足場資材の搬出作業を行わせ、被災労働者が手すりを乗り越えて横桁へ移動したことを制止しなかったことから、安全配慮義務違反が認められました。
一次下請業者について、安全衛生責任者は、請負人の労働者が行う作業のみでなく、当該労働者以外の者の行う作業によって生じる労働災害に係る危険の有無の確認等の安全対策を行うとされていることを踏まえると、被災労働者との間で雇用主に準ずる特別な社会的接触の関係に入っていたものとして、被災労働者の生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていました。
しかし、一次下請業者は、被災労働者の年齢を確認、把握し、被災労働者を高所での解体作業に従事させることの当否を検討すべきであったほか、解体作業の作業場所、内容、被災労働者の経験年数に照らし、安全衛生の確保に係る活動として危険予知活動を徹底させるべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったとして、安全配慮義務違反が認められました。
元請業者について、労働安全衛生法15条1項の特定元方事業者に該当し、労働安全衛生法29条及び30条の規定により、関係請負人の労働者を対象として、必要な指導、是正のため必要な指示を行う義務を課されていたほか、作業場所の巡視、労働者の安全衛生教育について必要な措置を講ずるものとされていることから、雇用主に準ずる特別な社会的接触の関係に入っていたものとして、被災労働者の生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていました。
しかし、元請業者は、特定元方事業者として、毎作業日に少なくとも一回、巡視を行い、被災労働者の年齢を確認、把握するよう努め、被災労働者を派遣労働者として高所での解体作業に従事させることの可否を検討すべきであったほか、自ら及び下請業者をして、解体作業の作業場所、内容、被災労働者の経験年数に照らした安全衛生の確保に係る活動としての危険予知活動を徹底させるべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったとして、安全配慮義務違反が認められました。
その上で、被災労働者は、墜落制止用器具の胴ベルトを装着しない状態で手すりを乗り越えた過失があることから、15%の過失相殺が認められ、結果として、ご遺族に、合計4892万円の損害賠償請求が認められました。
このように、建設工事現場における労災事故においては、損害賠償請求の回収という観点から、直接の雇用主だけではなく、元請業者等にも、損害賠償請求ができないかを検討するのが効果的です。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説