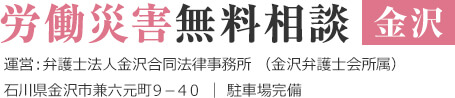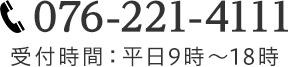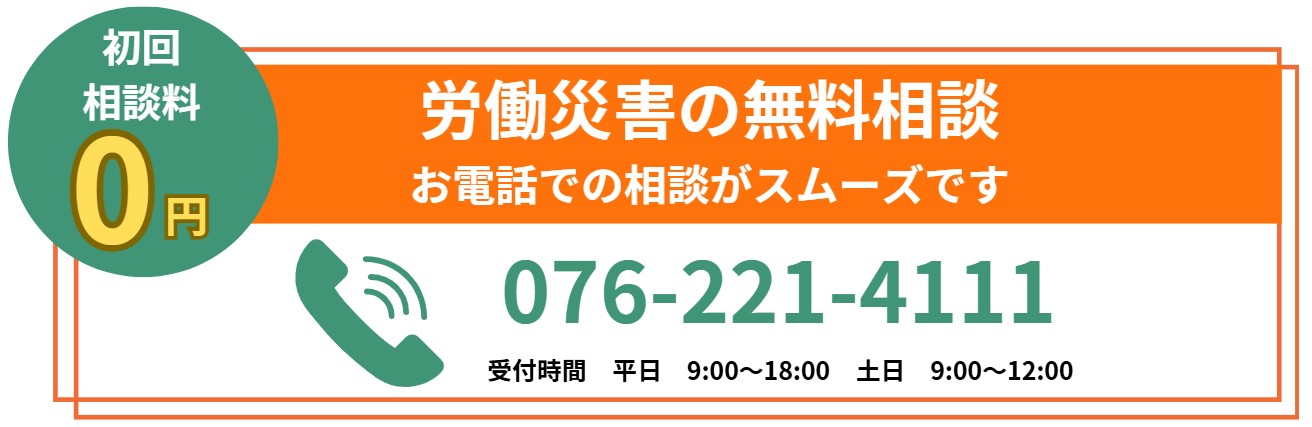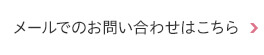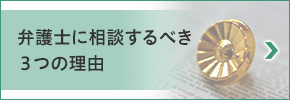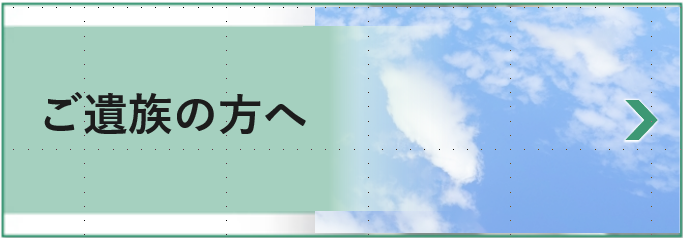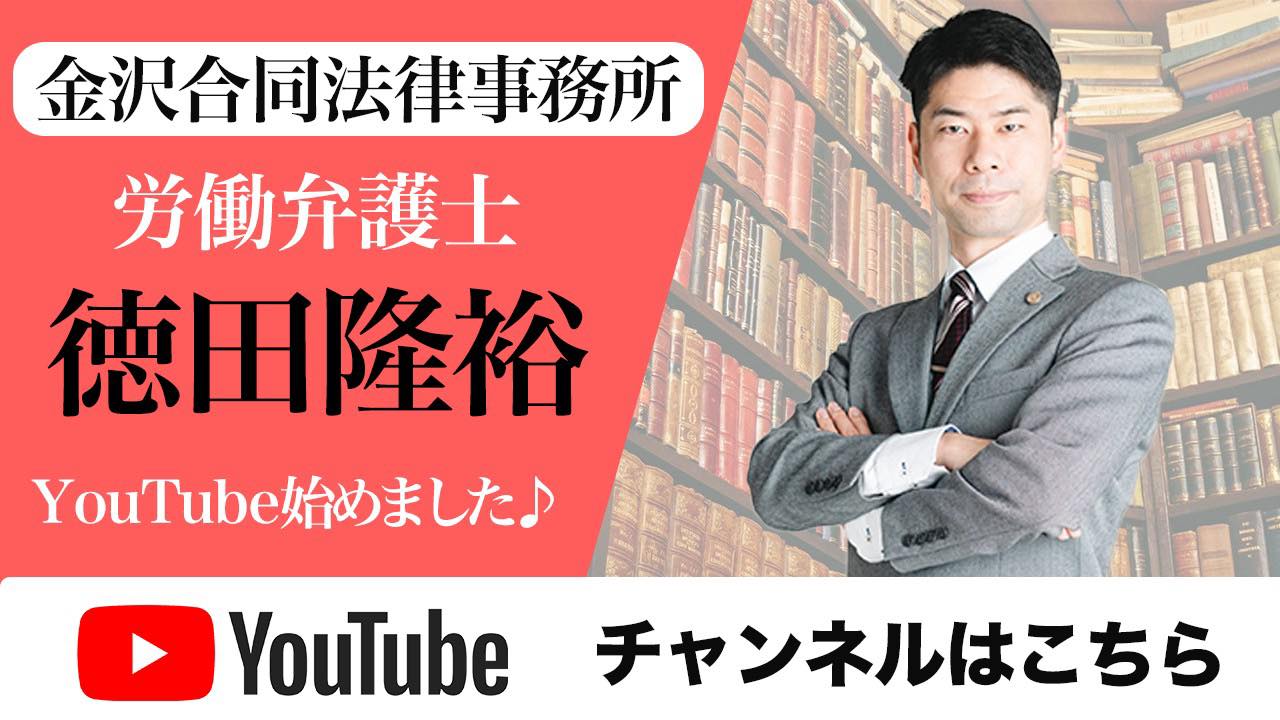労災事故による腕の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
廃棄物処理工場内で、ゴミ分別時に使用するベルトコンベアの清掃作業中、ローラーとゴムベルトの間に挟まっているゴミを取ろうとして手を入れたところ、右腕が挟まり、右腕を骨折しました。
この労災事故の後、右腕の骨折の治療をしていましたが、肘の関節がうまく曲がらず、痛みが消えません。
医師からは、後遺障害が残るかもしれないと言われました。
労災事故による腕の骨折の場合、労災保険からどのような補償があるのでしょうか。
結論から先にいいますと、腕の骨折の場合、関節が動きづらくなったことについての後遺障害、変形の後遺障害、痛みや痺れについての後遺障害が認定された場合、労災保険から、一時金若しくは年金が支給されます。
今回は、労災事故における腕の骨折の後遺障害について、わかりやすく解説していきます。

1 労災事故における腕の骨折の具体例
まずは、仕事中に腕を骨折する労災事故の具体例を紹介します。
①工場において、機械の操作中に、機械の中に腕を挟んで、骨折した。
②建設現場において、床の開口部に気付かずに転倒し、腕を床にぶつけて、骨折した。
③倉庫で荷物を整理していたところ、フォークリフトに腕を挟まれて、骨折した。
製造業、建設業、運輸交通業などで、腕を骨折する労災事故が発生しています。
2 労災保険からの補償
⑴ 療養補償給付
まず、労災事故にまきこまれて、腕を骨折した場合、必ず、労災申請をしてください。
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。
⑵ 休業補償給付
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
⑶ 障害補償給付
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑷ 労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
厚生労働省の労災申請の書式については、こちらのサイトをご参照ください。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

3 労災事故における腕の骨折の後遺障害
労災事故における腕の骨折の後遺障害は、3種類あります。
1つ目は、腕の関節が動きづらくなった場合の機能障害です。
2つ目は、腕の骨や関節が正常な形状や機能を持たない状態になった変形障害です。
3つ目は、痛みや痺れといった神経障害です。
⑴ 機能障害
腕の機能障害とは、3大関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなった後遺障害のことをいいます。
腕の機能障害については、次の通り、1級から12級までの後遺障害等級があります。
|
等級 |
認定基準 |
|
1級7号 |
両上肢の用を全廃したもの |
|
5級4号 |
1上肢の用を全廃したもの |
|
6級5号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
|
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
|
10級9号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では稼働するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のもの
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
⑵ 変形障害
腕の変形障害は、偽関節を残すもの、又は、長管骨に変形を残すものとされています。
偽関節とは、骨折部の骨や軟部組織の欠損、骨片間の過大な離開や不安定、軟部組織の介在・血行不良、あるいは感染の存在などによって骨癒合が妨げられているうちに、ついに骨癒合機転が完全に停止してしまった状態をいい、異常可動性が認められることが多いです。
長管骨とは、長い棒状の骨のことであり、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨です。
腕の変形障害については、次の通り、7級、8級、12級の後遺障害等級があります。
|
等級 |
認定基準 |
|
7級9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|
8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
|
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
第7級9号の「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
第8級8号の「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号の①以外のもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号の②以外のもの
③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
第12級8号の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
a上腕骨に変形を残すもの
b橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの
②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
③橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上腕骨の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨の直径が1/2以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
⑶ 神経障害
腕の骨折に伴い、腕に痛みや痺れが残ってしまった場合、腕の神経障害として後遺障害と認定されることがあります。
腕の神経障害は、12級と14級があります。
|
12級12号 |
局部にがん固な神経症状を残すもの |
|
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
12級は、神経障害の存在が他覚的に証明できるもの、14級は、神経障害の存在が医学的に説明可能なものと言われています。
12級の他覚的な証明とは、労災事故により身体の異常が生じ、その異常により現在の障害が発生していることが、医師による診察や検査によって客観的に捉えられて、判断できることをいいます。
14級の医学的に説明可能とは、現在存在する症状が、労災事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なものをいいます。
⑷ 後遺障害10級の場合に障害補償給付としていくら支給されるのか
ここで、後遺障害の第10級9号の「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当した場合で、いくらの補償が受けられるのかを検討してみます。
後遺障害10級の場合、障害補償給付として、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。
10級の場合、①障害補償一時金は、給付基礎日額の302日分が支給されます。
給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。
10級の場合、②障害特別一時金は、算定基礎日額の302日分が支給されます。
算定基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前1年間の賞与の金額を365日で割ってえられたものです。
10級の場合、③障害特別支援金は、39万円が支給されます。
具体的なケースで、10級の障害補償給付の金額を計算してみます。
毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円の労働者が10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害10級と認定されたケースで、障害補償給付の金額を計算すると、次のとおりとなります。
①障害補償一時金
まずは、直近3ヶ月間の給付基礎日額を計算します。
7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,782.6
1円未満の端数は、1円に切り上げるので、給付基礎日額は、9,783円となります。
10級の場合、障害補償一時金は、給付基礎日額の302日分が支給されますので、9,783円×302日=2,954,466円となります。
②障害特別一時金
まずは、直近1年間の算定基礎日額を計算します。
1年間の賞与が60万円なので、365日で割ると、60万円÷365日=1,643.8となり、1円未満の端数は1円に切り上げるので、算定基礎日額は、1,644円となります。
10級の場合、障害特別一時金は、算定基礎日額の302日分が支給されますので、1,644円×302日=496,488円となります。
③障害特別支援金
10級の場合の障害特別支援金は、39万円です。
以上を合計すると、2,954,466円(①障害補償一時金)+496,488円(②障害特別一時金)+39万円(③障害特別支援金)=3,840,954円となります。

4 会社に対する損害賠償請求
⑴ 労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
⑵ 安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
⑶ 後遺障害10級の場合にいくらの損害賠償請求ができるのか?
それでは、後遺障害の第10級9号の「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当した場合、会社に対して、いくらくらいの損害賠償請求ができるのかを計算してみます。
先ほどと同じように、毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円、年収420万円の40歳の労働者が、10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害10級と認定されたケースで、損害賠償請求の金額を計算してみます。
ここでは、労災事故の損害賠償請求で大きな金額になる、①休業損害、②逸失利益、③慰謝料を計算します。
①休業損害
まず、労災事故後に会社を休んでいた期間の休業損害を計算します。
休業損害は、収入日額に休業日数をかけて計算します。
収入日額は、労災事故前3ヶ月間の給料総額を期間の総日数で割って計算するので、労災保険の給付基礎日額の計算とほぼ同じです。
今回のケースの場合、収入日額は、7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,783円
休業日数が90日であれば、休業損害は、9,783円×90日=880,470円となります。
もっとも、休業損害からは、労災保険から支給された休業補償給付を控除します。
休業補償給付は、給料の約80%が支給されますが、80%のうちの20%の休業特別支給金は控除されません。
そのため、休業損害から控除されるのは、給料の約60%分である休業補償給付だけです。
例えば、今回のケースで、給料の約60%分である休業補償給付として、498,933円が支給されていた場合、会社に対して請求できる休業損害は、880,470-498,933=381,537円となります。
②逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
逸失利益は、次の計算式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、労災事故の前年の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害によって、労働者の労働能力がどれくらいの割合で喪失したかを算出するものです。
後遺障害10級の場合、労働能力喪失率は、27%です。
労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力が喪失された期間のことで、原則として、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて計算します。
今回のケースの場合、40歳で症状固定なので、労働能力喪失期間は、27年間となります。
ライプニッツ係数とは、労災事故などの損害賠償金に生じる中間利息を控除するための係数です。
逸失利益の損害賠償請求では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることなります。
その損害賠償金を運用すると利息が生じるので、この利息分を控除するために、ライプニッツ係数を使用します。
27年に対応するライプニッツ係数は、18.3270です。
今回のケースで逸失利益を計算すると、次のとおりとなります。
420万円×27%×18.3270=20,782,818円
この逸失利益の金額から、障害補償給付のうち、障害補償一時金を控除します。
障害補償給付のうち、障害特別一時金と障害特別支援金は控除されません。
今回のケースでは、障害補償一時金が2,954,466円なので、会社に対して請求できる逸失利益は、20,782,818-2,954,466=17,828,352円となります。
③慰謝料
労災事故の損害賠償で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
入通院慰謝料については、入院の月数と通院の月数から計算します。
例えば、入院2ヶ月、通院3ヶ月の場合、入通院慰謝料は、154万円になります。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
後遺障害10級の場合、後遺障害慰謝料は、550万円になります。
このように、労災保険では補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説