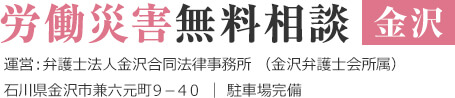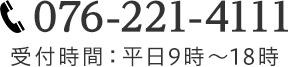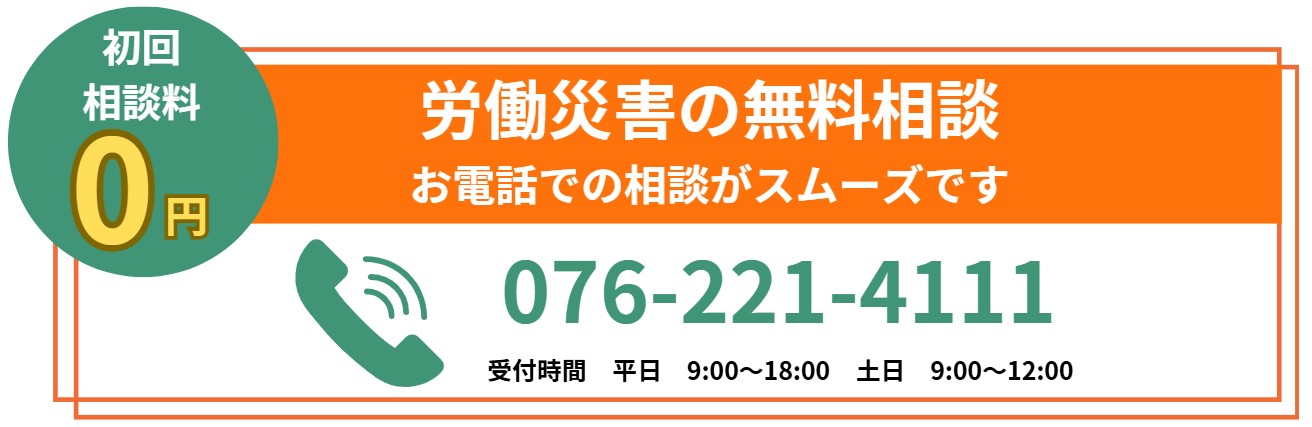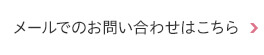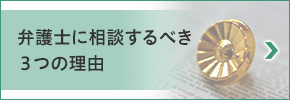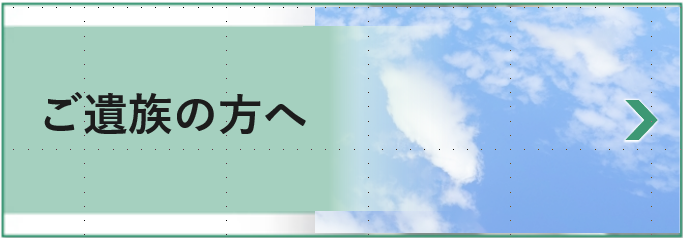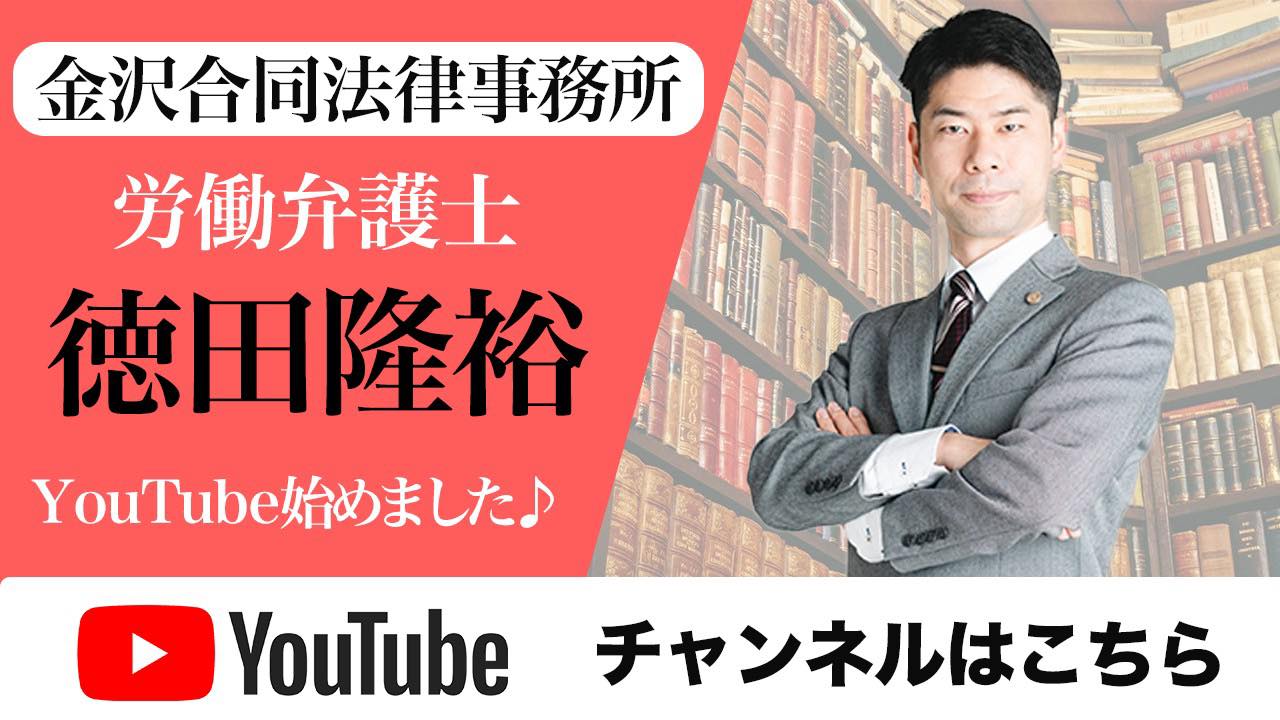労災事故で家族が死亡したら、遺族が受け取れる労災保険からの給付はいくらになる?
労災事故で大切なご家族を亡くされた場合、突然の出来事で心身ともに大きなショックを受けてしまいます。葬儀の準備や各種手続きなど、慌ただしく進めなければならないことは多岐にわたりますが、遺族の方を支えてくれる制度として労災保険からの給付が用意されています。
本記事では、労災保険における具体的な給付内容と金額の目安、さらに会社への損害賠償請求の考え方を幅広く解説いたします。
遺族補償給付や葬祭料、さらに労災就学等援護費など、労災保険からの給付は、それぞれ受給要件や申請時期が異なります。特に遺族補償年金は、残されたご家族の生活を安定させるために長期的な支えになる制度です。
他方、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、さらなる損害賠償を請求できる可能性もあります。
ここで紹介する手続きの流れや給付内容を押さえておくことで、万一の事態に備えやすくなります。弁護士に相談すれば、労災申請から会社との交渉までのサポートを受けられるため、不確かな点が多い方にも心強い味方となるでしょう。まずは、労災事故によってご家族を亡くされた際に知っておきたい基礎知識から順に見ていきます。

労災でご家族を亡くされた方へ
最初に、予期せぬ労災事故によってご家族を失った方が押さえるべき基本事項を確認します。
労災保険は、仕事が原因で死亡した労働者の遺族を支援するために、さまざまな給付を提供する制度です。ご家族が亡くなられた状況を正確に把握し、早めに労働基準監督署などの専門機関に相談することが大切です。
労災で家族が死亡したときに受け取れる主な給付の全体像
労災でご家族を亡くされた場合、労災の遺族補償給付を受給できるかを検討し、その後、会社に対する損害賠償請求が認められるかを検討します。
労災事故による死亡時には、まず労災保険からの遺族補償給付や葬祭料が代表的な給付となります。さらに、扶養していたお子さんがいる場合は労災就学等援護費による学費負担軽減も検討可能です。
また、会社の安全配慮義務違反が疑われるときは、会社への損害賠償請求も見据える必要があります。
労災保険からの補償で受け取れる金銭の種類
労災保険からは、主に遺族補償給付(遺族補償年金・遺族補償一時金)や葬祭料が支給され、亡くなられた労働者の子どもの就学を支援する就学等援護費も用意されています。遺族補償年金は、一定の対象遺族が継続的に受給できる仕組みで、給付基礎日額(労災事故発生前の亡くなられた労働者の直前3ヶ月間の賃金総額を日割り計算したもの)と遺族の人数に応じた給付基礎日額の日数で算定されます。これらの給付は、仕事を失った生活の基盤を支えるために重要な役割を果たすため、必ず確認しておきましょう。
会社への損害賠償請求で受け取れる可能性があるお金の種類
会社が労働者の安全を確保する義務を怠った結果、労災事故が発生した場合、会社に対して民事上の損害賠償請求を行える可能性があります。損害賠償には、被害者本人の将来の収入が失われた分を補填する逸失利益や、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。ただし、実際に請求するには労災事故の原因調査や、過失の有無を精査する必要があり、専門家のサポートが不可欠です。
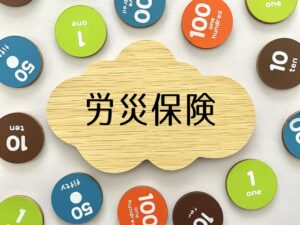
労災保険からの補償
ここでは、労災保険制度から受け取れる具体的な補償の種類と申請手続きのポイントを詳しく確認します。
労災保険は、労働者が安心して働ける環境を整えるための社会保険制度であり、業務上の災害を幅広くカバーします。死亡事故においても、遺族の生活を支えるさまざまな給付が設定されており、正しく理解することで、家計の崩壊を防ぐ大きな助けとなるでしょう。以下では、遺族補償給付・葬祭料・就学等援護費などを順番に解説します。
労災保険の遺族補償給付とは
労災保険の遺族補償給付は、亡くなった方の収入で生計を維持していた遺族に対して支払われるものです。遺族が一定の要件を満たした場合、年金形式で支給される遺族補償年金と、一時金として支払われる遺族補償一時金があります。対象となる遺族の範囲や給付金額は法律で細かく規定されているため、該当しそうな方は必ず内容を把握しておく必要があります。
①遺族補償給付
遺族補償給付の中心となるのは遺族補償年金で、亡くなった労働者の収入に依存していた家族を継続的に支える仕組みです。一方、遺族補償一時金は、条件を満たさず遺族補償年金を受給できない場合に支給されます。これらの制度を正確に理解し、家庭の経済事情に合わせて、どちらが給付されるのかを検討することが重要です。
遺族補償年金の対象となる遺族と順位
遺族補償年金は、亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが受給対象となります。ただし、配偶者や子など優先順位の高い遺族が存在する場合は、優先度の低い遺族には支給されない仕組みです。受給順を誤って理解すると、後から給付が認められないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
遺族補償年金の受給資格者が複数いる場合、以下の順番で優先順位が決まり、具体的に支給を受け取れる者が決まります。
①妻、60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
②18歳までの間又は一定の障害の状態にある子
③60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
④18歳までの間又は一定の障害の状態にある孫
⑤60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
⑥60歳以上、18歳までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
遺族補償年金の支給要件と支給期間
遺族補償年金を受給するためには、亡くなった労働者と生計を同一にしていたことや、婚姻関係や血縁関係を示す戸籍の証明が必要です。支給期間は基本的には終身となりますが、遺族の状況によっては期間が限定される場合もあります。特に子どもの受給資格は年齢要件があるため、早めに確認することが大切です。
遺族補償年金を申請するには、労働基準監督署に対して、労災保険の様式第12号の遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書を提出します。
遺族補償年金の支給額の計算方法とシミュレーション例
遺族補償年金の金額は、亡くなられた労働者の給付基礎日額に、遺族の人数に応じた給付基礎日額の日数を掛け合わせることで算定されます。
ここでは、年収が500万円(給付基礎日額が1万4000円、年間賞与が73万円と仮定)の夫が労災事故で死亡し、遺族が妻と子供2人(11歳と16歳)のケースで、遺族補償年金の支給額をシュミレーションしてみます。賞与が支給されている場合、遺族補償年金の他に、遺族特別年金、遺族特別支給金が支給されます。
遺族が3人の場合、遺族補償年金は、給付基礎日額の223日分となりますので、1万4000円×223日分=312万2000円(年額)となります。
遺族が3人の場合、遺族特別年金は、算定基礎日額の223日分となり、算定基礎日額とは、1年間の賞与を365日で割って得られたものですので、算定基礎日額は、73万円÷365日=2000円となり、2000円×223日分=44万6000円(年額)となります。
なお、遺族の数が、1人の場合、遺族補償年金は、給付基礎日額の153日分、遺族特別年金は、算定基礎日額の153日分、2人の場合、遺族特別年金は、給付基礎日額の201日分、遺族特別年金は、算定基礎日額の201日分が支給されます。
遺族補償年金と遺族特別年金は、毎年偶数月の中旬ころに2ヶ月分がまとめて支給されます。
そして、遺族特別支給金として、はじめに一時金300万円が支給されます。
遺族補償一時金が支給されるケースと金額の目安
遺族補償一時金は、死亡した労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族がいない場合に、その他の遺族に支給されます。そのため、遺族補償年金の受給者が見当たらない場合でも、突然生活の支えを失った遺族を救済する仕組みとして存在します。
賞与を受給している労働者が死亡した場合、遺族補償一時金の他に、遺族特別一時金が支給されます。
遺族補償一時金については、給付基礎日額1000日分が、遺族特別一時金については、算定基礎日額1000日分が、それぞれ支給されます。また、遺族特別支給金300万円も支給されます。
遺族補償一時金の申請をするには、労働基準監督署に対して、労災保険の様式15号の遺族補償一時金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別支給金申請書を提出します。
厚生年金・国民年金との併給・調整のポイント
労災保険からの遺族補償年金と、公的年金制度である厚生年金の遺族厚生年金、国民年金の遺族基礎年金との二重給付が起こる場合は、一定の調整が行われることがあります。たとえば、配偶者が厚生年金の厚生遺族年金を受給している場合、労災保険の遺族補償年金が一部減額されるケースも考えられます。詳細は年金事務所や労働基準監督署に確認し、適切に手続きを進めましょう。

葬祭料・葬祭給付とは
葬祭料(または葬祭給付)は、亡くなられた労働者の葬儀にかかる費用を一定の範囲で補填する制度です。突然の不幸により、経済的負担も大きくなる葬儀費用を少しでも軽減できるように設けられています。既に他の補償制度を利用していても受給できる可能性があるため、対象となる方は必ず確認してください。
②葬祭料
葬祭料の支給額は、「被災労働者の給付基礎日額の60日分」と「給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額」を比較して、高い方となります。先程のシュミレーションのケースの場合、1万4000円×60日分=84万円となります。支給額は大きくはないものの、少しでも遺族の経済的負担を減らす上で重要な役割を果たします。申請の際には、葬儀を実際に行った方が申請人となるのが一般的であり、領収書や証明書類を揃える必要があります。
葬祭料の支給要件と請求できる人
葬祭料を請求できるのは、実際に葬儀等を執り行った遺族や手続きを代行した方となります。既に葬儀を執り行っている場合に請求できること、及び、現実に要した葬儀費用と支給額とは関係がないことに注意が必要です。労災事故として認定されていることが前提であり、申請には死亡診断書や葬儀費用の領収書などが必要となる場合があります。
労災就学等援護費とは
労災就学等援護費は、亡くなった被災者の子どもが学校へ進学したり、学業を継続する際の費用負担を軽減するために設けられた仕組みです。普通教育だけでなく、高校や大学など幅広い就学過程で活用できる場合があります。遺児の将来を守るための重要な支援制度として、該当する方はぜひ活用を検討してみてください。
③労災就学等援護費
労災就学等援護費は、亡くなった労働者の子どもの学資等の支弁が困難であると認められる場合に、就学の状況に応じて支給されます。家庭の教育費の負担は大きくなりがちですが、この制度を利用することで将来にわたって学びの機会を確保しやすくなります。必要書類を整えて正しく申請することがポイントです。
労災就学等援護費の支給対象となる遺児の範囲
労災就学等援護費は、基本的に被災者に扶養されていたお子さんが対象となります。遺族補償年金の受給権者の子供が学校に在学していて、学費の支弁が困難な場合に、支給されます。
労災就学等援護費の支給額と支給期間の目安
支給額は就学先によって異なります。子供一人当たりの支給月額は次のとおりとなっています。
①小学生 1万2000円
②中学生 1万6000円
③高校生 1万9000円
④大学生 3万9000円
労災による死亡事故の手続きの流れ
突然の事故死に直面すると、多くの手続きを短期間で行わなければなりません。
死亡直後から葬祭料の請求、そして遺族補償給付の申請まで、スムーズに進めるためには一連の流れを把握しておくことが重要です。遺族年金や労災保険の手続きと並行して、会社との連絡や証拠の確保も必要になります。早めの情報収集と専門家への相談が、複雑な手続きの混乱を防ぐ大きなカギとなるでしょう。
死亡直後から葬儀までに行うべき主な手続き
ご家族が死亡された場合、まず警察への連絡、死亡診断書の取得、市区町村役場への死亡届の提出などの公的手続きを行う必要があります。併せて、労災の可能性がある場合は会社や労働基準監督署への報告も検討しましょう。初動段階で不備があると後々の手続きが複雑化するため、迅速かつ正確に進めることが肝要です。
労災申請の準備で行うこと
労災申請では、労災事故発生状況を示す書面や、亡くなった労働者の雇用形態・就労条件を示す資料などをそろえる必要があります。証人となり得る方の連絡先を確保しておくことや、現場写真などの証拠の確保が後々重要です。曖昧な点が多い場合は、弁護士や労働基準監督署に早めに問い合わせを行いましょう。
遺族補償給付・葬祭料などの請求の具体的なステップ
まずは労働基準監督署に必要書類を提出し、労働者が業務上の理由で亡くなったと認定されれば支給手続きが進行します。遺族補償給付や葬祭料については、申請書類の書き方や添付資料に不備がないように注意しましょう。審査の結果には時間がかかる場合があるため、早めに動き出すことが必要となります。
年金事務所などで行う遺族年金の手続き
労災とは別に、公的年金制度に基づく遺族年金の手続きも進める必要があります。年金事務所へ行く際は、戸籍や住民票、死亡した労働者の年金手帳や年金加入記録などを確認しておきましょう。労災保険と遺族年金を同時に受給するときの調整が発生するケースもあるため、あらかじめ相談しておくと間違いが生じにくくなります。
会社とのやり取り・損害賠償請求を視野に入れた証拠の確保
労災事故の原因が会社の安全管理不備によるものであれば、会社に対する損害賠償請求を検討します。会社とのやり取りのメールや書類、労災事故当時の写真・動画などは重要な証拠となるため、すべて保管しておきましょう。弁護士に相談する際にも、証拠の有無は交渉を有利に進めるうえで大きく影響します。

会社に対する損害賠償請求を検討する
労災保険の給付だけでは、十分に生活を補うことが難しい場合もあります。
特に、死亡によって将来的な収入が失われたり、慰謝料が必要となる場合には、会社に対して損害賠償請求を検討する余地があります。会社が安全配慮義務を怠っていたかどうかを慎重に調査し、経済的損失や精神的な苦痛に関して正確に積算することが重要です。早めに専門家に依頼することで、法的な主張を裏付ける証拠整理や交渉をスムーズに進められるでしょう。
(1)労災保険からの補償では足りない?
労災保険の遺族補償給付は大きな助けにはなりますが、すべての損害をまかなうには不十分な場合があります。会社に責任があるケースでは、損害賠償請求によって不足分を補うことを検討することが大切です。具体的には、亡くなられた労働者が稼ぎ得たはずの収入や精神的苦痛に対する慰謝料などが請求対象となります。
(2)労災事故による死亡の逸失利益
亡くなられた労働者が本来得ていた、または将来得るはずだった収入が絶たれたり、減少した分を逸失利益と呼びます。逸失利益は、労働者が生きていれば働いて得られる収入を前提とし、就労可能年数や生活費控除率などを考慮して計算されます。会社の過失があった場合、この逸失利益に対する賠償を請求することが可能です。
逸失利益とは何か
逸失利益とは、亡くなられた労働者が通常の状態であれば稼いでいたであろう将来の収入のことです。死亡事故の場合、その先の労働期間や収入見込みがまるごと失われるため、非常に大きな損害となり得ます。特に一家の大黒柱が亡くなったケースでは、家族が大きな経済的打撃を受けるため、損害額の算出が重要になります。
労災死亡事故における逸失利益の計算の基本
逸失利益は、亡くなられた労働者の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数の計算式で計算します。
生活費控除率は、死亡した労働者の生活費がかからなくなるために、その生活費を控除するための割合のことです。すなわち、労災事故によって死亡すると、働けなくなるので、収入は得られなくなりますが、その代わり生活費がかからなくなるため、逸失利益の計算の際には、本来かかるはずの生活費が、かからなくなる分を差し引くことになります。一家の支柱が死亡して、被扶養者が2名以上の場合の生活費控除率は、30%です。
就労可能年数は、通常、67歳までとされています。ライプニッツ係数は、労災事故の被災労働者が将来受け取るはずの収入を、現時点の価値に換算するときに使われるものです。すなわち、逸失利益では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることになるので、利息を差し引くことになるのです。ようするに、一度に受け取ったお金を運用すれば、利息が増えため、現在請求できる金額は、将来もらえるはずの金額からそれまでの利息分を控除した金額になるのです。先程のケースでは、ライプニッツ係数は、18.7641となります。
先程のケースで、逸失利益を計算すると、500万×(1-0.3)×18.7641=6567万4350円となります。
このように計算した逸失利益から、これまでに受給した遺族補償年金が控除されます。なお、遺族特別年金と遺族特別支給金は、逸失利益から控除されません。また、将来支給される遺族補償年金も、逸失利益から控除されません。
(3)労災事故による死亡の慰謝料
被災労働者が労災事故で亡くなられたことによる精神的苦痛のほか、残された遺族の苦しみに対しても慰謝料が発生します。労災保険の補償には慰謝料の概念は含まれないため、会社との交渉や訴訟で独自に請求する必要があります。遺族固有の慰謝料は親族関係や労災事故状況によって異なるため、慎重な計算と主張が必要です。
慰謝料の相場感と増額要素・減額要素
労災事故で、一家の支柱が死亡した場合の慰謝料については、2800万円が相場となっています。また、母親や配偶者が死亡した場合の慰謝料については、2500万円、独身の男女の場合の慰謝料については、2000万円~2500万円が相場となっています。
遺族の精神的苦痛が深刻な場合には増額要素になり、逆に被害者にも過失があった場合には減額要素になることがありえます。
遺族固有の慰謝料と被害者本人の慰謝料
慰謝料には、大きく分けて亡くなられた労働者の精神的苦痛に対する慰謝料と、遺族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料があります。亡くなられた労働者の慰謝料は、労災事故当時の苦痛や死亡に至るまでの苦しみを考慮したものです。一方、遺族固有の慰謝料は、残された家族が今後抱える悲しみや負担を補う目的で認められます。
(4)労災における安全配慮義務違反とは?
会社は、労働者の生命・健康を危険から保護するように配慮する義務を負っています。これを安全配慮義務といい、例えば危険予防策を怠ったり、安全装備の提供を怠ったりした場合は違反にあたる可能性があります。もし会社が安全配慮義務に違反していたと認められる場合は、会社に対する損害賠償責任を追及できる可能性が高くなります。
会社に損害賠償請求できるケース
機械設備の整備不良や過剰な残業を強要していたケースなどは、安全配慮義務違反の代表例です。業務手順に重大な欠陥があったり、労災のリスクを知りながら適切な対策を取らなかった場合も含まれます。
労災事故では、会社に、労働安全衛生法令やこれに関する通達に違反している場合に、安全配慮義務違反が認められます。ですので、労災事故の内容から、会社に労働安全衛生法令の違反がなかったかを検討することが重要になります。
また、労災事故の発生に、労働者の落ち度も関与していた場合、過失相殺をされてしまい、認められる損害賠償額から、いくらか控除されることがあります。この過失相殺で、何割くらい、損害賠償額が減額されるのかについては、労働者の落ち度の程度によって変わってきますので、ケースバイケースで判断していくことになります。
労災保険給付と損害賠償請求の関係
労災保険からの給付を受けつつ会社に損害賠償請求を行うことは可能ですが、二重取りとみなされないよう調整が行われることがあります。具体的には、労災保険から支給された金額が損害額の一部に充てられているとみなされ、損害賠償の算定に反映される場合があるということです。最終的な受け取り額に影響するため、専門家のアドバイスを受けるのが得策といえます。
会社との示談交渉と訴訟の流れ
まずは会社と話し合い、示談交渉によって合意に至るのが一般的ですが、折り合わない場合は裁判で決着を図ることもあります。示談では早期解決が期待できますが、会社側との見解の差が大きい場合は長期化する可能性があります。示談や裁判を合理的に進めるには、法的知識や交渉力を持った弁護士のサポートが欠かせません。

労災の死亡事故の各種手続きや損害賠償を弁護士に依頼するべき理由
労災事故に関する手続きは多岐にわたり、法律知識や交渉力が必要になる場面が少なくありません。
特に死亡事故の場合は、遺族補償給付や会社への損害賠償請求を並行して行うことが一般的であり、スケジュール管理や法的根拠の整理が大きな負担です。弁護士に依頼すれば、申請書類の作成から会社との交渉・示談、必要に応じた訴訟手続きまでを一元的にサポートしてもらえます。結果として、適正な補償獲得につながりやすく、精神的負担の軽減効果も期待できます。
弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士は労災の専門知識や会社の交渉手法に精通しており、複雑な法律関係や請求手続きについて的確なアドバイスを提供できます。法律の素人が独力で行うよりもスムーズかつ迅速に進められ、漏れやミスを大幅に減らせることが大きな利点です。さらに、交渉時に精神的ストレスを軽減できることも、遺族にとって大きな安心材料となります。
どのタイミングで弁護士に相談すべきか
労災事故直後の段階で相談するのが理想ですが、少なくとも労災申請や会社との示談交渉を始める前に弁護士の見解を得ることが望ましいです。初動での対応によって、後の手続きが有利に進むかどうかが大きく分かれる場合があります。何らかのトラブルが生じてから相談するよりも、早めに専門家に声をかけておく方が結果的に費用や時間の節約にもつながります。
労災に強い弁護士の選び方
過去に労災や死亡事故の案件を多く取り扱った実績のある弁護士や法律事務所を選ぶと、スムーズに対応してもらいやすいです。無料相談や初回相談で、どのような進め方を提案してくれるか、費用面の説明が明確かなどを確認することも重要といえます。安心して手続きを任せられるかどうか、コミュニケーションを通して判断するのがポイントです。
当事務所の強み
一口に弁護士と言っても、注力している領域は様々であり、それによって研鑽・経験を積んでいる内容も異なります。当事務所は、死亡事故をはじめとして、70年以上にわたって労働者側の労働災害事件や労働問題に取り組んでおり、労災事故に巻き込まれた労働者の権利擁護の実現を目指しています。
また、当事務所の弁護士は、日本労働弁護団・過労死弁護団連絡会議に所属しており、労災事件や労働事件に関する専門性を磨いております。
更に、当事務所は、ベテランから若手まで、個性豊かな男女6人の弁護士が所属している、石川県内では最大規模の法律事務所です。
複数の弁護士がチームを組み、よりよい解決を導き出せるように協働するとともに、労災申請から損害賠償請求まで、ワンストップでサポートをご提供できる連携体制づくりに努めております。
まとめ
労災でご家族を亡くされた際に押さえておきたいポイントを総括します。
業務上の死亡事故では、まず遺族補償給付や葬祭料など労災保険からの給付制度を正しく理解し、早めに申請手続きを行うことが欠かせません。さらに、会社の安全配慮義務に違反がある場合は損害賠償請求によって、経済的損失を補填できる可能性があるため、証拠の確保や専門家への相談を怠らないようにしてください。弁護士への依頼は費用面を含めハードルに感じる方も多いですが、結果として適切な補償を受けられるケースが増えるため、ぜひ前向きに検討してみてください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説