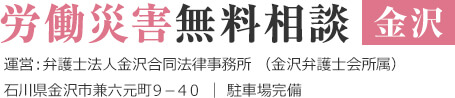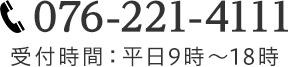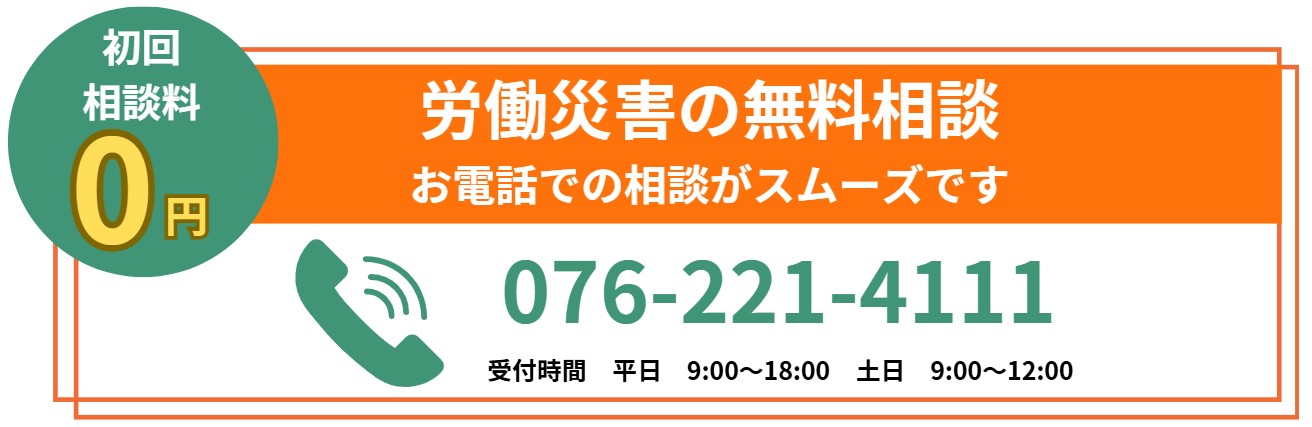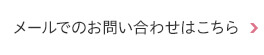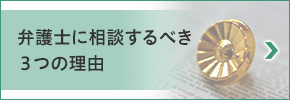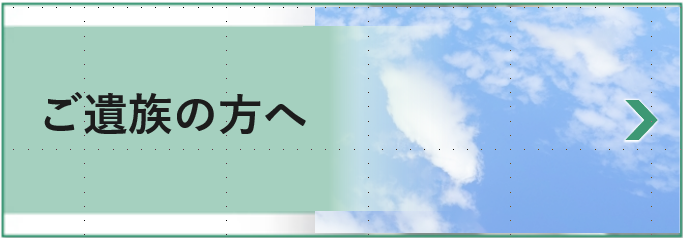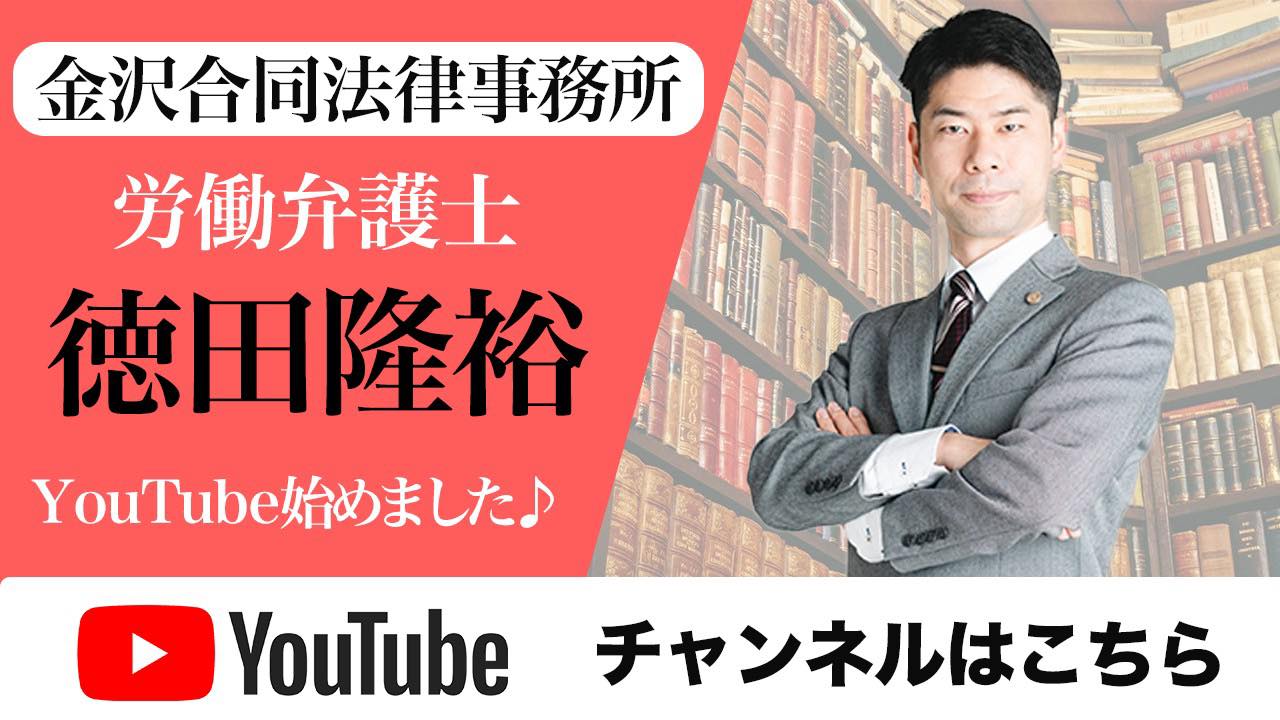建設現場で労災事故にまきこまれた時の対処法【弁護士が解説】
1 建設現場における労災事故の実態

建設現場において、墜落や転落といった労災事故にまきこまれて、重大なケガを負った場合、どうすればいいのでしょうか。
結論から先にいいますと、建設現場で労災事故にまきこれまた場合には、労災保険を利用し、その後、会社に対する損害賠償請求を検討します。
公費解体中の労災事故に遭われた方はこちらもお読みください>>
今回の記事では、①建設現場における労災事故の実態、②労災申請、③損害賠償請求の3つの順番で解説します。
労災事故によって死亡が最も多く発生している業種は、建設業です。
建設業の労災事故で、死亡に至るもので最も多い類型は、墜落・転落です。
建設現場では、高所で作業することが多く、高所から墜落して地面に衝突する瞬間、時速40kmの自動車と衝突した時と同じ衝撃が加わるといわれており、死亡に至ることが多いのです。
建設現場における墜落・転落で死亡に至った労災事故として、次の事例が挙げられます。
①ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者が墜落防止用の手すりの解体作業中に、手すりと共に高所から墜落して死亡した事例
ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者は擁壁上の手すりを撤去する作業を行っていたところ、墜落制止用器具を掛けていた手すり(単管をクランプで固定し、ロの字型にした囲い手すり)が倒壊し、手すりと共に約10m下の水路に墜落した。被災者は病院に搬送されたが、その後死亡した。
②6階建てのビル屋上での足場組み立て作業で、被災者が屋上の床スラブ上を移動中、開口部から23.5m下の地上まで墜落して死亡した事例
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造6階建てのビル屋上において、解体用の防音シートを張るための足場組み立て作業中、被災者(学生アルバイト)は壁つなぎの部材(長さ1.3mの単管)を壁つなぎ増設作業中の鳶工に橋渡しをしようとして、屋上床スラブを移動中、解体ガラ投下用の開口部(幅1.7m×長さ3m×高さ23.5m)から、地上(1階床スラブ)まで墜落して死亡した。
③マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、足場上を移動していたところ、足場から地上に墜落した事例
マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、解体した足場材の受け渡し役として、足場材を足場上で運んでいた被災者は、荷降ろし役の作業員に足場材を渡した後、次の足場を解体役から受け取るために足場上を移動した際、足場から地上に転落した。
2 労災申請をする

このように、建設現場で、墜落・転落の労災事故が発生した場合、重度の後遺障害が残る大ケガをするか、最悪、死に至ることがあります。
不幸にも、建設現場で、墜落・転落の労災事故にまきこまれた場合、必ず、労災申請をしてください。
建設現場における墜落・転落の労災事故が、労災と認定されれば、労災保険から、治療費が全額支給されます。
治療のために、会社を休業している期間、給料の約8割が支給されます。
そのため、安心して治療に専念できます。
墜落・転落の労災事故によるケガの治療を続けていたものの、これ以上、現在の医学では、症状が改善されない時がきます。
これを、症状固定といいます。
症状固定時点で、残ってしまった症状で、労働能力の喪失を伴うものを、後遺障害といいます。
労災保険では、1級から7級までの後遺障害の認定がされた場合には、年金が支給され、8級から14級までの後遺障害の認定がされた場合には、一時金が支給されます。
後遺障害が残った場合、労災保険から、年金または一時金が支給されることで、後遺障害によって、労働能力が失われたことによる収入の減少に対する補償がなされ、今後の生活が安定します。
他方、墜落・転落の労災事故によって、不幸にも、死に至った場合、ご遺族は、労災保険の遺族補償給付を受給できます。
遺族補償給付を受給できれば、2ヶ月に1回、労災保険から、年金が支給されますので、残されたご遺族の生活の安定につながります。
このように、建設現場で墜落・転落の労災事故にまきこまれた場合、今後の生活の安定のために、必ず、労災申請をしてください。
労災申請をするには、①会社に手続を代行してもらうか、②ご自身で労働基準監督署へ行って手続をする、③弁護士に労災申請を依頼する、の3つの方法があります。
労災の申請書に、労災事故の発生状況を正確に記載する必要があること、適切な後遺障害の認定を受ける必要があることから、労災申請の手続を、弁護士に依頼することをおすすめします。
3 会社に対する損害賠償請求を検討する
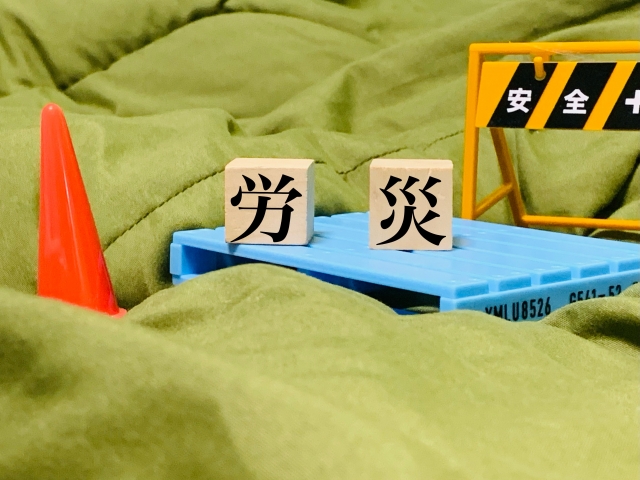
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付と、労働者の死亡による収入の喪失に対応する、労災保険の遺族補償給付では、労働者の将来の収入の減少・喪失という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少・喪失の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
すなわち、建設現場における、墜落・転落の労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
では、どのような場合に、会社に安全配慮義務違反が認められるのでしょうか。
それは、会社が、労働安全衛生法令に違反した場合です。
労働安全衛生規則519条には、次のように規定されています。
「事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
すなわち、会社は、高さ2メートル以上の場所で、労働者に作業をさせる場合、墜落防止のための囲い等を設置しなければならず、囲い等を設置できない場合には、防網を張り、労働者に安全帯を使用させなければならないのです。
そのため、会社は、高さ2メートル以上の場所で、労働者に作業をさせる際に、囲い等を設置していなかったり、安全帯を使用させていなかった場合、安全配慮義務違反が認められます。
このように、会社が労災事故を防止するための安全対策を怠っていた場合、労働者は、会社に対して、労災保険からの補償では足りない損害について、損害賠償請求をすることができるのです。
当事務所では、労災事故で不幸にも後遺障害が残ってしまった方が適切な補償を受けられるために、労災申請のサポートをさせていただいております。
また、当事務所では、労災事故において、安全対策を怠った会社に対する損害賠償請求の事件に、積極的に取り組んでおります。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説