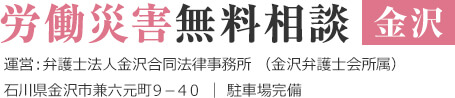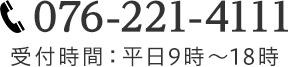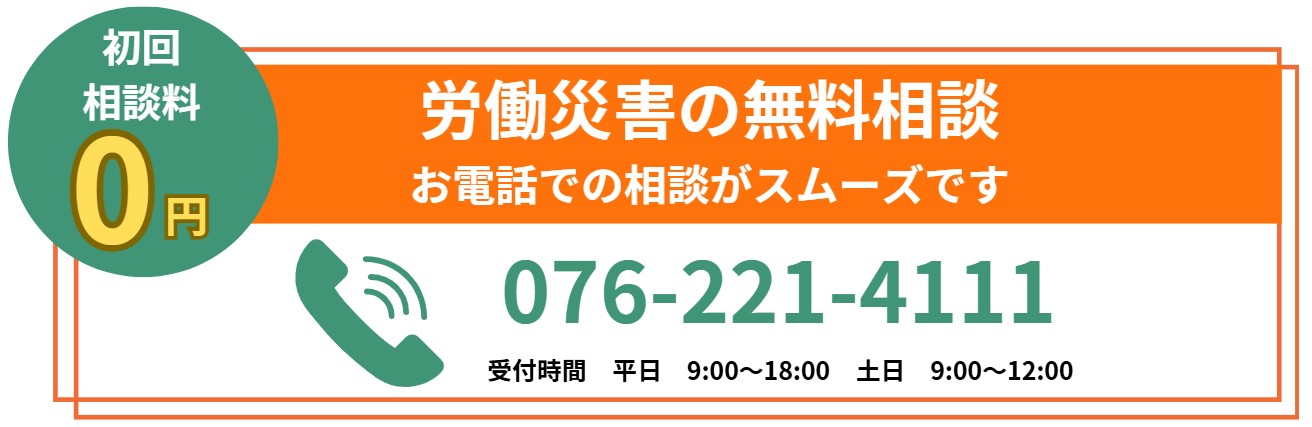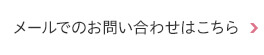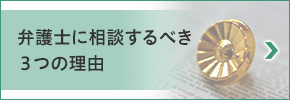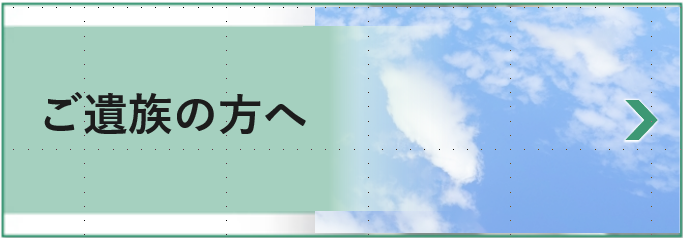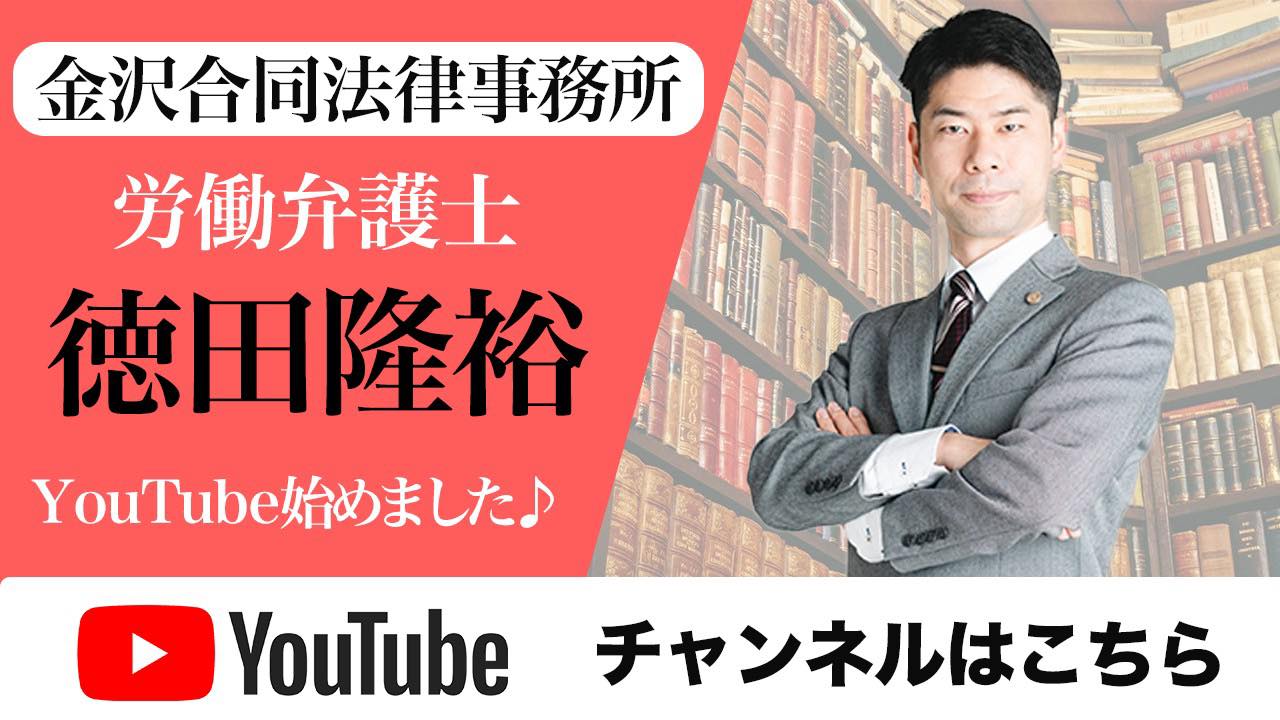通勤災害とは?労災保険の基準から給付・手続きまで弁護士が徹底解説
通勤災害は労働者のみならず、パートやアルバイトなど多様な働き方をする方々にとっても決して他人事ではありません。通勤中の交通事故やケガは予期せず発生することがあり、いざというとき、どのような補償を受けられるのか知っておくことで、不安を減らすことができます。
本記事では、通勤災害と業務災害との違い、具体的に受け取れる給付内容と申請手続きの流れまでを網羅的に解説します。
万が一通勤途中にトラブルや交通事故に巻き込まれた場合、本記事の情報が役立つはずです。トラブルの際に正しい手続きを踏むことで、労災保険から適切な補償を受けることが可能になります。いざというときに備えて、通勤災害に関する知識をしっかり把握しておきましょう。

通勤災害と業務災害との違い
まずは通勤災害とは何かを正しく押さえ、業務災害との差異を理解することが重要です。
通勤災害は、住居と就業の場所を往復する際の合理的な経路や方法を用いた移動中に発生する負傷や疾病、死亡を指します。労災保険上では、たとえ正社員でなくパートやアルバイトであっても、就業に関わる通勤中であれば幅広く補償の対象となります。通勤災害は、一見すると私生活の延長のようにも思えますが、業務と切り離せない重要なリスクとして位置づけられているのです。
一方、業務災害は、仕事が原因となって労働者が負った怪我や病気、死亡のことを指します。業務災害は、労働者が労働契約に基づき会社の支配下にあるという業務遂行性と、業務に内在する危険が現実化したという業務起因性の2つの要件が認められる必要があります。通勤災害と業務災害では条件や給付内容に微妙な違いがあり、請求手続きの際にも区別が必要です。
通勤災害が適用される条件
通勤災害が認められるためには、就業の場所と住居の間を合理的な方法や経路で移動している最中に起きた事故であることが大前提です。公共交通機関や徒歩、自転車、マイカーなど、普段利用している手段で通勤している場合に適用される可能性があります。ただし、大幅な寄り道や私的な目的での遠回りがあると、通勤ではなくなるリスクが高まるため注意が必要です。
業務災害と通勤災害の相違点
休業補償給付の待機期間の取扱
労災保険の休業補償給付には、3日間の待機期間があります。労働基準法76条1項により、業務災害の場合、被災労働者は、待機期間中の休業補償について、会社から、直接休業補償を受けることができます。
他方、通勤災害には、上記規定が存在しないため、待機期間中の休業補償を受けることができないという相違点があります。
療養中の解雇制限
労働基準法19条1項により、会社は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間、労働者を解雇することができません。そのため、業務災害による休業療養中の解雇は、無効になります。
他方、労働基準法19条1項は、通勤災害には適用されませんので、通勤災害によるケガで治療するために休業している期間に、労働者が解雇されたとしても、当然に解雇が無効になるわけではありません。
通勤災害の要件
通勤災害として,労災保険の適用を受けるためには,次の要件を満たす必要があります。
①就業に関し,次のア・イ・ウのいずれかの要件を満たす移動行為であること
ア 自宅などの住居と会社などの就業の場所を始点または終点とする往復
イ 就業の場所から他の就業の場所への移動(例えば,本業の就業場所から副業の就業場所へ移動する場合などです)
ウ 住居と就業の場所との間の往復に先行し,または後続する住居間の移動(例えば,単身赴任者が週末を自宅で過ごし,日曜日の夕方に自宅から単身赴任先の社宅へ移動する場合などです)
「就業に関し」とは,当該移動行為が仕事を開始するため,または,仕事を終えたことによって行われることをいいます。通勤災害にあった日に出勤することになっていたか,現実に出勤していたことが必要になります。
「住居」とは一般的に自宅を指しますが、単身赴任先の部屋や一時的に居住している場所も含まれる場合があります。要は、その人が生活の拠点として使っている場所であれば住居と認定される可能性があるのです。
「就業の場所」とは、通常、労働契約に基づいて働いている事業所やオフィスを指します。現場仕事や出張が多い職種の場合は、契約書に明示されている就業場所以外の現場先や顧客先も含まれることがあります。
②合理的な経路及び方法により行われる移動であること
「合理的な経路」とは,労働者が通勤のために通常利用する経路のことです。
子供を幼稚園や保育所に預けるために利用する経路は,合理的な経路といえます。
「合理的な方法」とは,往復または移動を行う際に,一般に労働者が用いるものと認められている方法をいいます。
鉄道やバスなどの公共交通機関を利用する場合,自動車や自転車などを本来の用法に従って使用する場合,徒歩の場合などには,当該労働者が通常その方法を用いているかにかかわらず,合理的な方法と認められます。
③業務の性質を有する移動行為ではないこと
例えば,会社に出勤した後に,外回りの営業のために移動していたときに事故にまきこまれた場合は,通勤災害ではなく,業務災害となり,労災保険が利用できます。
④移動行為において合理的な経路の逸脱または中断がないこと
「逸脱」とは,通勤の途中において就業や通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
「中断」とは,通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
例えば,通勤の途中に,ゲームセンターやパチンコ店に入って遊ぶ,居酒屋などで飲み会に参加するなどの場合に,逸脱や中断があったとされてしまいます。
逸脱や中断と認められれば,その後は通勤となりませんので,逸脱や中断の最中や後に事故にまきこまれても,労災保険が適用されなくなってしまうのです。
もっとも,次のような日常生活上必要な行為であって,通勤の途中で行う必要があり,必要最小限の時間と距離の範囲で行う場合には,逸脱や中断の間を除いて,合理的な経路に戻った後は再び通勤となります。
①日用品の購入
②職業訓練
③選挙権の行使
④病院などへの通院
⑤親族の介護

通勤災害として認められるケース・認められないケース
具体的な事例を挙げながら、通勤災害として認められる場合とそうでない場合を確認します。
通勤災害の認定では、どのような目的で移動していたか、またその行動が就業との関連性を保っているかで左右されます。同じように見える行動でも、実際には法的な区別が細かく存在するため、ひとつひとつのケースで判断基準が異なる点に注意が必要です。
ここでは、よく相談が寄せられる典型的なシチュエーションを取り上げ、その適用可能性を考察します。
保育園・幼稚園の送迎中に事故に遭った場合
子どもの送迎を含む場合、労災上の通勤とみなされるかどうかは、送迎ルートが通勤経路に含まれるかが重要なポイントです。保育施設が家と職場の間にあり、経路の逸脱がなければ通勤災害として認められる可能性があります。
飲み会や用事での寄り道中に起こった事故
通勤途中に友人との飲み会やショッピングといった私的行為を挟む場合、大抵は通勤ルートとして認められません。その理由は、業務とは無関係な目的で移動を逸脱・中断しているからです。たとえ短時間の寄り道でも実質的な方向転換が認められると通勤とはみなされない場合が多いため、注意が必要です。
看護・介護のために立ち寄った際に起こった事故
家族の看護や介護が必要な事情で、やむを得ず経路を変更するケースは、認定の可否が判断の難しい領域となります。看護や介護目的が日常生活にとって欠かせない行為とみなされる場合は、法的に許容される範囲として通勤災害が認められることがあります。しかし、立ち寄りのために大きく道を外れていると通勤行為から外れるリスクがあるので、どの程度の迂回かを丁寧に確認することが重要です。
熱中症などが通勤災害と認められる場合
真夏の暑い時期に公共交通機関の待ち時間や徒歩移動の途中で倒れてしまうケースは、条件によっては通勤災害として認められることがあります。ポイントは、その熱中症が仕事へ向かうための合理的な移動行為の中で発症したかどうかです。特に高温多湿の日や体調面の問題など、通勤中の環境条件も含めて総合的に判断されます。

通勤災害と自賠責保険・健康保険の違い
交通事故などでよく聞く自賠責保険や健康保険との違いを理解し、重複や適用範囲を整理しましょう。
通勤災害は労災保険の対象となりますが、事故の相手方がいる場合には自賠責保険や任意保険との関係も生まれ、補償内容が重複することがあります。労災保険は、あくまで労働者の就業に関する災害をカバーする制度である一方、自賠責保険は自動車事故における被害者救済を目的としています。
また、日頃利用している健康保険を通院に使えると思いがちですが、通勤災害に該当する場合は基本的に労災保険が優先します。複数の保険を組み合わせて治療費や休業補償を受ける際には、どの保険をどのタイミングで使うのが適切か整理しておくことが大切です。
自賠責保険との相違点
自賠責保険は自動車損害賠償保障法によって定められた強制保険であり、交通事故の被害者救済を目的とするものです。一方、労災保険の通勤災害は、労働者が仕事のために通勤している最中に被った損害を補償する制度であり、保険金の給付対象や計算方法も異なります。
労災保険・健康保険・自賠責保険を併用する際の注意点
複数の保険を同時に使用する場合、重複給付の問題に注意が必要です。例えば、医療費を健康保険で支払った後に改めて労災保険を請求すると、後日精算が複雑になることも考えられます。どの保険がメインになるか、負担割合はどうなるかなど、事前に会社や保険会社と連携しつつ書類の手続きを進めることが大切です。
交通事故で労災保険を利用するメリット
労働者が仕事中や通勤途中に交通事故にあった場合,労災保険を利用できます。
一方で,交通事故については,交通事故の相手方の自動車損害賠償責任保険(自賠責)と,相手方の任意保険からの支払いを受ける場合があります。
ほとんどの交通事故では,相手方の任意保険の損害保険会社が被害者の通院先の病院へ治療費を支払い,損害賠償金を支払ってくれますが,労災保険を利用したほうが,被害者にとって有利な場合があります。
⑴長く治療を続けられる
交通事故でむち打ち症となった場合,相手方の損害保険会社は,おおむね1~3ヶ月,長くて6ヶ月までしか,治療費を負担してくれません。
相手方の損害保険会社に治療を打ち切られてしまった後にも,痛みが続く場合には,自分の健康保険を利用して通院し,治療費を自分で負担しなければなりません。
他方,労災保険を利用できれば,主治医がこれ以上治療を続けても症状が改善しないと判断するときまで,自分で治療費を負担することなく,治療を続けることができます。
そのため,労災保険を利用したほうが,治療費を打ち切られることを心配せずに,安心して治療をすることができます。
なお,途中までは,相手方の損害保険会社に治療費を支払ってもらい,相手方の損害保険会社から治療費を打ち切られた後に,労災保険に切り替えることもできます。
⑵原則として過失相殺されない
交通事故では,自動車が動いていれば,双方に過失(落ち度)があったとして,過失相殺されて,交通事故の相手方に対して請求できる損害賠償金の額が減額されてしまいます。
特に,ご自身の過失が大きい場合には,大幅な減額がされることがあります。
労災保険を利用できれば,労災保険では原則として過失相殺がされませんので,治療費や休業補償給付,障害補償給付などの全額が支給されるので,メリットは大きいです。
⑶特別支給金は控除されない
交通事故によって被害者に生じた損害については,現実に発生している損害を補填すればよく,それ以上に損害賠償が認められません。
そのため,相手方の損害保険会社から損害賠償金を支払ってもらい,さらに労災保険からも補償を受けるというように,二重に損害を補填してもらうことはできないのです。
例えば,先に労災保険から休業補償給付の受給を受けた後に,相手方の損害保険会社に対して,休業損害の損害賠償請求をしても,すでに労災保険から受給している休業補償給付の分が控除されてしまうのです。
これを損益相殺といいます。
もっとも,休業補償給付は給料の60%に相当する分が支給され,その他に給料の20%に相当する分が休業特別支給金として上乗せして支給されます。
結果として,給料の80%に相当する分が支給されるのです。
この休業特別支給金は,損益相殺の対象にならないので,休業特別支給金を受給していても,相手方の損害保険会社に対して,損害賠償請求をしても,休業特別支給金の分は控除されないのです。
休業特別支給金以外にも,後遺障害の認定があれば支給される障害特別支給金や障害特別年金も,損益相殺の対象になりません。
また,自賠責保険や任意保険から,休業損害や後遺障害の逸失利益の損害賠償金を受け取っていたとしても,休業特別支給金や障害特別支給金などについて,労災申請をすれば,受給することができます。
⑷費目間流用の禁止
例えば,交通事故にあった労働者に生じた損害額が,治療費100万円,休業損害100万円,慰謝料100万円であり,労働者に30%の過失があったケースで考えてみましょう。
相手方の損害保険会社が治療費100万円を被害者が通院していた病院に既に支払っており,相手方の損害保険会社が休業損害の60%である60万円を既に被害者に支払っていたとして,労災保険を利用できない場合,次のような計算になります。
300万円×70%-160万円=50万円
被害者は,相手方の損害保険会社に対して,残り50万円しか請求できません。
同じケースで労災保険が利用できて,労災保険から被害者である労働者が通院していた病院に治療費100万円が支払われており,被害者である労働者に対して休業補償給付60万円の支給がされているとします。
この場合,労働者の過失が30%あるので,治療費については,100万円-70万円=30万円の過払いが生じていることになります。
この治療費30万円の過払い分を休業損害や慰謝料から控除することが許されないのです。
これを費目間流用の禁止といいます。
その結果,被害者の労働者は,相手方の損害保険会社に対して,治療費0円,休業損害70万円-60万円=10万円,慰謝料100万円×70%=70万円の合計80万円を請求できるのです。
結果として,労災保険を利用できる場合の方が,30万円多く請求できることになります。
このように,仕事中や通勤途中に交通事故にまきこまれたときには,労災保険を利用したほうが,被害者にとって有利になることがありますので,労災保険が利用できないかについて,検討してみてください。
交通事故で労災保険を利用するときには,労働基準監督署に「第三者行為災害届」という文書を提出する必要があります。
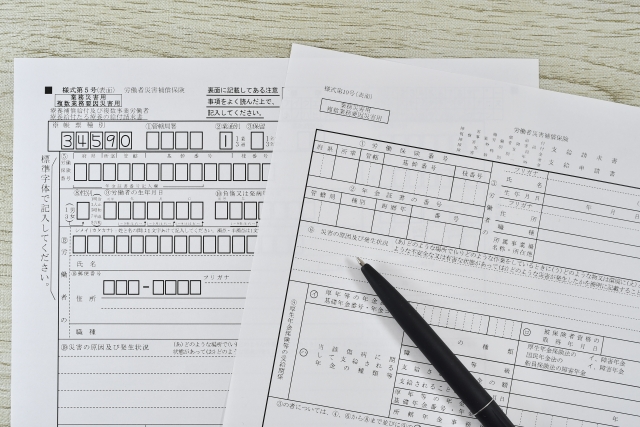
通勤災害で受け取れる労災保険給付の種類
通勤災害により受けられる具体的な補償を理解しておくことで、適切な申請や受給が可能になります。
労災保険では、通勤災害に該当する事故が認定されると、様々な給付を受けられる可能性があります。治療費の補償から休業中の賃金補填、後遺障害や遺族のための給付など、状況に応じて内容が異なるため自分のケースに合った給付制度をしっかりと確認することが大切です。
また、後々請求が必要になる場合に備え、医師の診断書や通院記録などの書類をきちんと保管しておくと手続きがスムーズに進みます。
療養給付
通勤中の事故で負ったケガや病気の治療費を労災保険から負担してもらえる制度です。労災指定の医療機関を受診すれば窓口負担がゼロとなる場合が多く、経済的負担を軽減できます。ただし、指定外の医療機関を受診する際は書類手続きが増えることがあるため、医療機関選びの段階で確認しておきましょう。
休業給付
通勤災害によるケガや病気が原因で仕事を休む場合、休業給付によって給料の一部をカバーすることができます。休業4日目以降に労災保険から給付が支給される仕組みです。早期に症状が回復して復職できるよう、休業期間中もリハビリや適切な医療を受けることが望ましいでしょう。
障害給付
後遺障害が残る場合には、障害給付を受けられる可能性があります。後遺症の程度により障害等級が定められ、それに応じて年金または一時金が支給されます。
遺族給付
通勤災害が原因で死亡した場合は、その遺族に対して遺族給付が支給されます。遺族の要件に応じて、労災保険から、年金若しくは一時金が支給されます。
通勤災害の労災申請手続き
通勤災害が認められそうな場合には、正しい書類と手順による申請が不可欠です。
通勤災害として認定を受けるためには、所定の申請書類を労働基準監督署に提出する必要があります。事故の状況や休業日数、治療内容などを正確に記入し、医師の証明が必要となる欄もあるため、医療機関での診断内容なども揃えておきましょう。申請に不備があると手続きの遅延を招くので、チェックは念入りに行うことをおすすめします。
また、会社側の協力が不可欠となる場面も多々あります。事実関係の確認や証明が必要な書類があるので、早期に担当部署や保険担当者と連携し、書類作成のサポートを受けるのも大切です。
手続きの流れと必要書類
まず、労災申請書を取得し、記入後に医療機関や会社の証明を受けます。次に、揃った書類一式を労働基準監督署に提出し、審査を受ける流れです。認定には数週間から数ヶ月の期間を要することがあるため、できるだけ速やかに手続きを開始することがポイントです。
会社や保険会社とのやり取りで気をつけるポイント
事故が起きた直後は、気が動転して会社や保険会社とのやり取りがスムーズにいかないことも考えられます。しかし、誤った情報を伝えてしまうと後々修正が難しくなる場合もあるため、正確な状況報告が重要です。特に通勤経路や事故のタイミングなど細かい点について、曖昧にしないよう意識して対応しましょう。
認定されなかった場合の不服申し立て手続き
通勤災害の認定がされなかった場合、納得がいかなければ不服申し立てを行うことができます。審査請求、再審査請求、行政訴訟など、段階的に執りうる手続きが用意されているため、弁護士に相談しながら進めるのが望ましいでしょう。ただし、申し立てには期限があるので、早めの行動が必要です。

通勤災害に関するよくある疑問Q&A
通勤災害は広く知られてはいますが、具体的にどこからどこまでカバーされるのか、どんな手続きが必要なのかなど、不明点も多く寄せられます。ここでは、通勤災害についての疑問や、休業補償にまつわるトラブルなど、よくある質問に答えます。
パート・アルバイトや派遣社員も対象になる?
労災保険は基本的にすべての労働者を対象としているため、パートやアルバイト、派遣社員も通勤災害が認定される可能性があります。
マイカー通勤の場合はどうなる?
マイカー通勤であっても、合理的な経路と方法であれば通勤災害として認められる可能性があります。ガソリン代の支給や駐車場所の有無などは通勤災害の判断に直接影響しませんが、定期的に通っているルートかどうかが重視されます。ただし、大幅な遠回りや私用での運転が絡む場合は、通勤災害の認定が難しくなる場合があるので注意しましょう。
休業と通院にまつわるトラブル事例
会社によっては労災の扱いに慣れておらず、休業補償や治療費の対応で混乱が生じることがあります。治療開始が遅れたり、休業補償をめぐって意見が対立するケースもあるため、できるだけ早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。特に手続き方法や書類の書き方を正確に理解しておくことが、トラブルを回避するための鍵となります。
まとめ
最後に、通勤災害のポイントや労災手続きの流れなど重要事項をまとめます。
通勤災害は労働者が仕事に行く、あるいは仕事から帰る途中で被ったケガや病気を補償する制度であり、通勤経路や手段の合理性、移動経路の逸脱・中断があったかどうかなどの要件をチェックする必要があります。業務災害とは異なる認定基準が存在するため、事故が起きた際にはどちらの災害なのかを正確に見極めることが大切です。
労災保険の仕組みや給付の種類、申請手順を知っておけば手続きが円滑に進みます。トラブルが生じた場合も、慌てず正しい情報をもとに会社や保険会社と交渉し、必要に応じて専門家の力を借りて解決を目指しましょう。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説