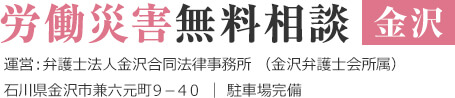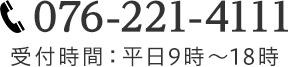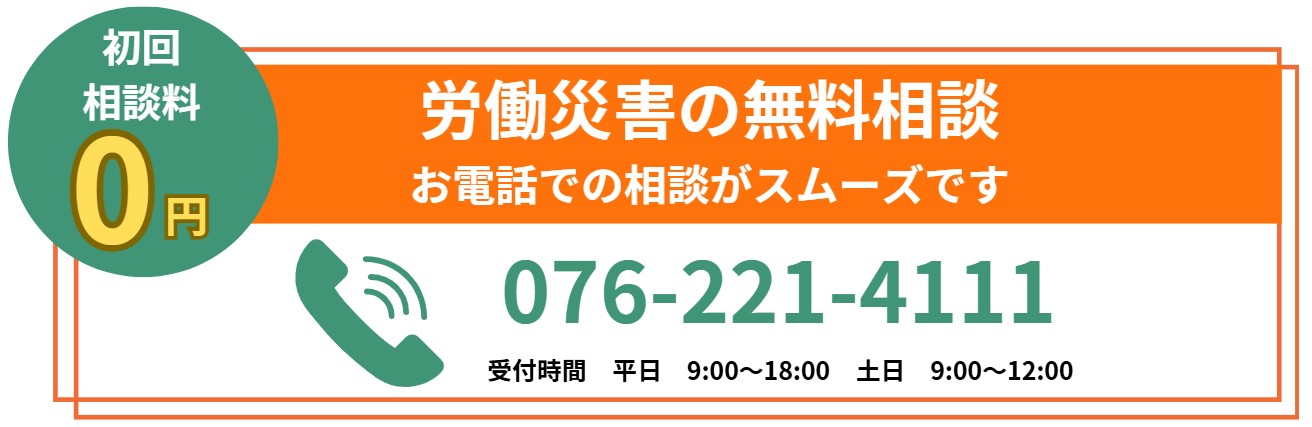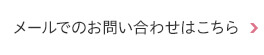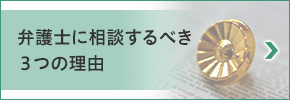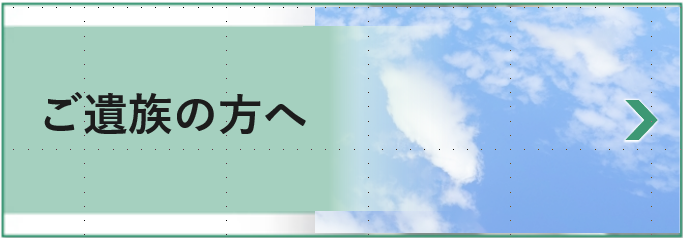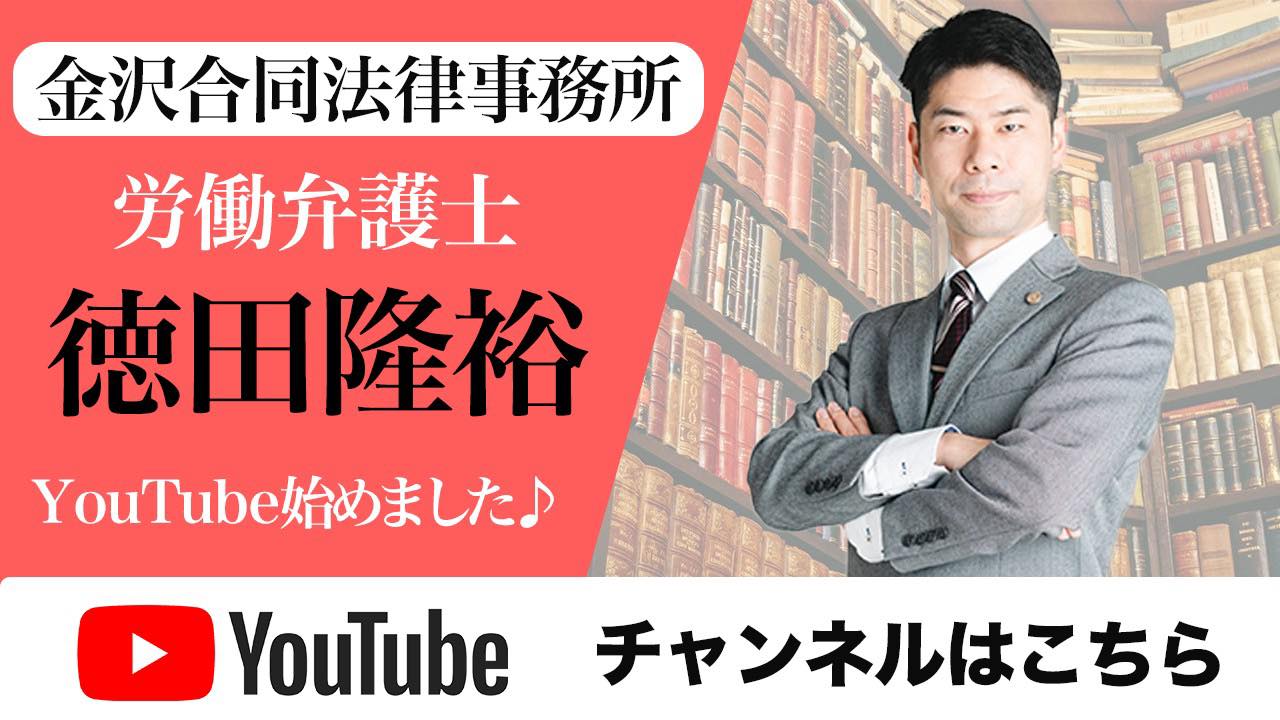化学物質による労働災害に巻き込まれた時の対処法【弁護士が解説】
食品製造工場で実験をしていた際、指導者から誤った指導を受け、その誤った指導に従って実験をした結果、有害な化学物質が発生してしまい、有害な化学物質を吸引しました。
その結果、咳がひどくなり、呼吸困難になる等の被害を受けました。
このような化学物質による労働災害に巻き込まれた場合、どうすればいいのでしょうか。
結論から先に言いますと、労災申請をして、労災と認定された後に、会社に対する損害賠償請求を検討します。
今回は、化学物質による労働災害に巻き込まれた時の対処法について、わかりやすく解説します。
1 化学物質の労働災害の発生状況

まず、化学物質による労働災害の発生状況について解説します。
平成26年から令和5年までの10年間で、化学物質による労働災害の発生件数は、年間500件前後で推移しています。
化学物質による労働災害が多く発生している業種としては、1位食料品製造業、2位化学工業、3位清掃・屠畜業、4位金属製品製造業、5位建築工事業となっています。
製品別の労働災害の発生状況ですが、洗剤・洗浄剤による労働災害が全体の約3割を占めて、圧倒的に多く、次いで、ガス、消毒・除菌・殺菌・漂白、酸類、水酸化ナトリウム等が原因で労働災害が発生しています。
化学物質による労働災害の具体的事例として、次のものが挙げられます。
器具を消毒するための消毒液を作る作業において、消毒液が跳ねて、目に入り、角膜上皮びらんの症状が発生した。
ドラムから原料を小分け計量する作業中、原料がこぼれて、足に付着し、薬傷が発生した。
ゴミ袋から漏れた廃液が足にかかり、化学熱傷が発生した。
このように、化学物質を取り扱う職場では、化学物質による労働災害が発生するリスクが高いといえます。
2 労災申請をする

化学物質による労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
労災と認定されることで、労災保険から、以下のような補償を受けることができ、労動者にとってメリットが大きいです。
(1)療養補償給付
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。
(2)休業補償給付
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
(3)障害補償給付
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
労災保険では、1級から7級までの後遺障害の認定がされた場合には、年金が支給され、8級から14級までの後遺障害の認定がされた場合には、一時金が支給されます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
(4)遺族補償給付
他方、化学物質による爆発の労災事故が発生して、不幸にも、被災労働者が死亡するに至った場合、ご遺族は、労災保険の遺族補償給付を受給できます。
遺族補償給付を受給できれば、2ヶ月に1回、労災保険から、年金が支給されますので、残されたご遺族の生活の安定につながります。
(5)労災申請
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
厚生労働省の労災申請の書式については、こちらのサイトをご参照ください。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。
このように、化学物質による労災事故にまきこまれた場合、今後の生活の安定のために、必ず、労災申請をしてください。
3 会社に対する損害賠償請求を検討する

⑴ 労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害や死亡による収入の減少や喪失に対応する、労災保険の障害補償給付や遺族補償給付では、労働者の将来の収入の減少や喪失という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少や喪失の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
⑵ 安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
(3)化学物質による労災の安全配慮義務違反
例えば、有機溶剤を屋内作業所で使用する場合、会社は、局所排気装置を設置する義務、防毒マスク等の保護具を支給する義務、有機溶剤の濃度を測定する義務を負っています。
会社がこれらの義務を怠り、労働者が有機溶剤の中毒を発症した場合、会社に、安全配慮義務違反が認められます。
また、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質とその化学物質を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に、労働者を従事させる場合、会社は、労働者に、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋等の適切な保護具を着用させなければなりません。
会社が、労働者に対して、適切な保護具を着用させずに、健康障害を引き起こしうる化学物質を使用させた場合、安全配慮義務違反が認められます。
そして、労動者に、危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡、提供する会社は、文書の交付等の方法で、通知対象物に関する事項を、労動者に通知しなければなりません。
この際に、交付される安全データシート(SDS)は、化学物質の安全な取扱を確保するために、化学物質の危険有害性に関する情報を記載した文書です。
会社が、労動者に対して、SDSを交付していなかったために、労動者が化学物質の危険性を理解できずに、化学物質を使用して、労災事故が発生した場合、会社に安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。
このように、会社が労災事故を防止するための安全対策を怠っていた場合、労働者は、会社に対して、労災保険からの補償では足りない損害について、損害賠償請求をすることができるのです。
会社に対する損害賠償請求が認められ、適切な損害賠償金が支払われることで、今後の生活の安全が確保されることにつながります。
ここまで、化学物質による労働災害について解説してまいりました。
もし、労災事故に巻き込まれた場合には、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説