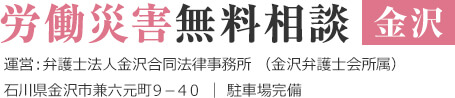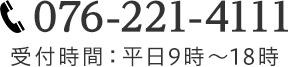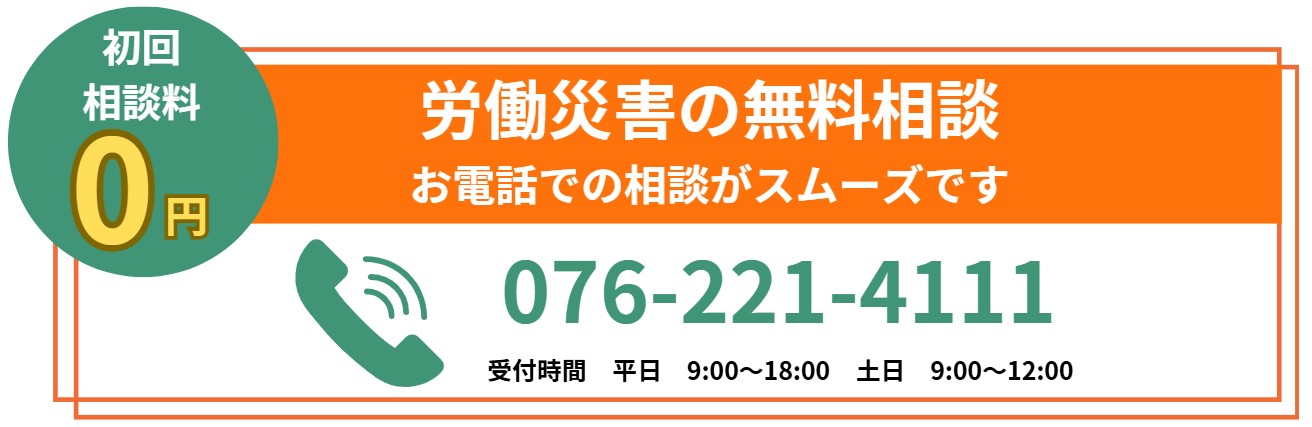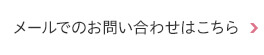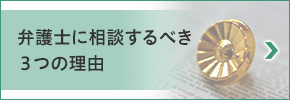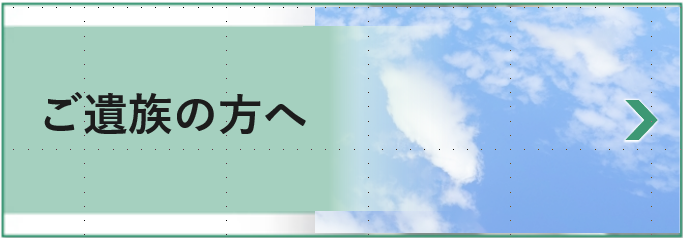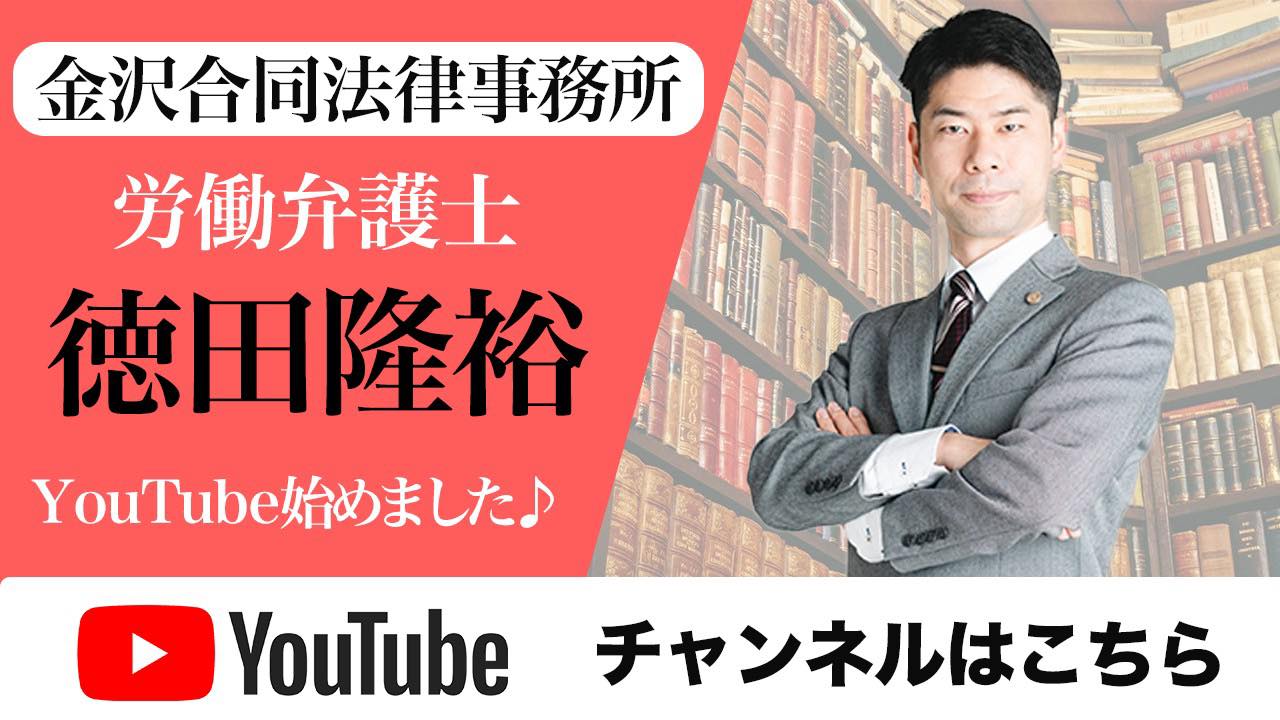労災の手続きの流れを弁護士が完全解説!

仕事中に転倒してしまい、けがを負い、治療のために、長期間、会社を休むことになりました。
長期間、仕事を休むことになったので、会社から給料が支払われなくなり、今後の生活が不安です。
労災事故にまきこまれて、長期間、会社を休む場合、どのような補償があるのでしょうか。
結論から先にいいますと、労災と認定されれば、労災保険から、治療費が全額支給され、会社を休業している期間、給料の約80%が支給されますので、安心して治療に専念することができます。
今回は、労災保険からの支給を受けるための、労災の手続きについて、わかりやすく解説します。
1 労災申請とは
労災とは、労働災害の略語で、労働者が仕事中にケガや病気をしたことをいいます。
労動者の仕事中のケガや病気が、労働基準監督署において、労災と認定された場合、労災保険から補償を受けることができます。
具体的には、労災保険から、治療が全額支給され、休業期間中に給料の約80%が支給されます。
治療が終了した時に、後遺障害が残れば、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険から補償を受けるために、労働基準監督署に対して、仕事中のケガや病気を労災と認定してくださいと、申請することを労災申請といいます。

2 労災申請の手続きの流れ
⑴ 医療機関での治療
労災事故にまきこまれて、ケガをしてしまった場合、まず最初に、病院へ行き、ケガの治療をします。
労災保険指定医療機関で治療をする場合、窓口で治療費を支払う必要はなく、労災保険の様式5号の文書を、労災保険指定医療機関へ提出すれば、無料で治療を受けられます。
労災保険指定医療機関以外の病院で治療をする場合、労動者は、一旦、窓口で、治療費を支払い、病院から受け取った領収書と、労災保険の様式7号の文書を、労働基準監督署へ提出すれば、後日、労災保険から、治療費が振り込まれます。
労災事故にまきこまれて、負傷した場合、早期に回復を図るために、治療に専念する必要があります。
⑵ 会社への報告
労災事故が発生したことを会社へ報告します。
また、労災申請をする際に、労災の請求書に、会社に証明をしてもらう欄がありますので、会社に対して、会社の証明欄に記載を求めます。
会社は、労災事故が発生したことを、遅滞なく、労働基準監督署へ報告する義務を負っています。
会社が、この報告義務を怠った場合、50万円以下の罰金に処せられることになります。
⑶ 労働基準監督署へ労災申請
労災保険指定医療機関以外の病院で治療をしている場合には、領収書を、後遺障害が残った場合には、後遺障害の診断書を集めて、労災保険の様式に従い、労災申請の請求書を作成して、労働基準監督署へ提出します。
会社を休業している期間の休業補償給付の請求書は、労災保険の様式8号、後遺障害による障害補償給付の請求書は、労災保険の様式10号、労動者が死亡した場合の遺族が申請する遺族補償給付の請求書は、労災保険の様式12号を使用します。
労災保険の各請求書は、こちらの厚生労働省のホームページから入手できます。
⑷ 労働基準監督署による調査
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
具体的には、労災事故にまきこまれた労働者、労災事故を目撃した他の従業員、現場責任者等から、事情を聴取します。
また、労働基準監督署は、労動者に後遺障害が残る場合、その後遺障害の等級を認定するために、主治医や嘱託医に意見を求めます。
⑸ 労災保険の支給決定
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。
なお、労働基準監督署が、労災とは認定できないと判断して、不支給決定の通知をする場合もあります。
労災保険の不支給決定の通知を受けた場合、被災した労動者は、労災保険の不支給決定に対して、審査請求という、不服申立て手続きをすることができます。
審査請求をするには、労働基準監督署から、労災保険の不支給決定の通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に申立てをしなければなりません。
審査請求の手続きにおいて、労働基準監督署の決定を覆すのは、ハードルが高いため、労災に詳しい弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
3 労災申請から給付までの期間はどれくらいか?
労働基準監督署が労災申請を受理してから、労災保険の支給決定がなされまのでの期間ですが、厚生労働省は、次のように公表しています。
療養補償給付 概ね1ヶ月
休業補償給付 概ね1ヶ月
障害補償給付 概ね3ヶ月
遺族補償給付 概ね4ヶ月
もっとも、厚生労働省の資料には、労災事故の内容によっては、上記の期間以上の時間を要することが記載されています。
具体的には、因果関係の判断が難しい、腰痛、脳や心臓の疾患、精神障害の事案では、労働基準監督署の調査に時間がかかり、労災保険の支給決定がなされるまでの期間が長期化する傾向にあります。
4 労災申請3つのポイント
⑴ 速やかに労災申請をする
労災申請には時効があります。
療養補償給付は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から、2年で時効になります。
休業補償給付は、労働不能のために賃金を受けない日ごとに、その翌日から、2年で時効になります。
障害補償給付は、症状固定日(現代の医学ではこれ以上治療しても、症状がよくならなくなった時点)の翌日から、5年で時効になります。
遺族補償給付は、被災した労動者が死亡した日の翌日から、5年で時効になります。
労災保険から補償を受ける権利が、時効で消滅してしまいますと、労災保険からの支給はされません。
また、労災事故から時間が経った後に、労災申請をした場合、会社に労災事故の証拠が残っておらず、労災と認定されないリスクがあります。
そのため、労災事故にまきこまれた場合には、なるべく速く、労災申請をするべきなのです。
⑵ 会社からの労災隠しにひるまない
労働者本人が労災申請をしようとしても、会社から労災隠しをされてしまい、労災申請ができないリスクがあります。
すなわち、労働者が会社に対して、労災申請の依頼をしても、会社が労災申請に協力してくれないことがあります。
このように、労災事故が発生し、労働者が負傷して、労働者が労災申請をしようとしても、会社が、労災保険ではなく、健康保険を使うように指示してきたり、会社からお金を支払うので、労災保険を使わないでほしい等と、労災隠しをするように、圧力をかけてくることがあります。
なぜ、会社が労災隠しをするのかといいますと、その理由は、労災事故が発生したことが、労働基準監督署に発覚すれば、会社は、労働基準監督署から、行政指導や刑事告発をされるリスクがありますので、これを避けたいと考えることがあるからです。
また、労災事故の発生によって、会社が負担する労災保険料が増額される可能性もあります。
このような理由から、会社は、労災隠しをしてくることがあるのです。
労働者が会社からの労災隠しの圧力に屈してしまい、結果として、労災申請ができないというリスクがありえます。
しかし、労災隠しは犯罪です。
会社が労災申請に協力してくれなくても、労働基準監督署へ、会社が労災隠しをしていることを申告すれば、問題なく、労災申請をすることができます。
会社から労災隠しの圧力があったとしても、ひるむことなく、必ず、労災申請をしてください。
⑶ 労災に詳しい弁護士に相談する
労災事故によっては、因果関係が問題になるものがあります。
そのような労災事故の場合、労動者本人だけで労災申請をしても、労災と認定されない可能性があります。
労災に詳しい弁護士に依頼すれば、弁護士は、労災認定のための証拠を収集し、仕事中に負傷したことが労災と認定されるべき事実を効果的に主張し、労災認定されるように、全力を尽くしてくれます。
また、労災の後遺障害では、適切な等級認定を受けることが重要になりますところ、弁護士に、後遺障害の等級認定のサポートを依頼することで、適切な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。
このように、労災申請を、労災に詳しい弁護士に依頼することで、労災保険から適切な補償を受けられる可能性が高くなります。
さらに、労災に詳しい弁護士に依頼することで、会社に対する損害賠償請求が認められる場合があります。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
すなわち、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があるのです。
労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
弁護士は、労災事故の状況から、会社が、どのような労働安全衛生法令やガイドラインに違反していたかを調査し、会社に安全配慮義務違反が認められないかを検討します。
そして、弁護士は、会社に安全配慮義務違反が認められる見通しがたてば、労働者本人のために、代理人として、損害賠償請求をしてくれます。
会社から、損害賠償金が支払われることで、労災事故にまきこまれた労働者の今後の生活が安定します。
労災事故について、会社に対して損害賠償請求をするためには、専門知識が必要になりますので、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
- 労災事故で家族が重傷を負った方へ|労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説
- 振動障害は労災認定される?損害賠償請求まで弁護士が徹底解説
- 労災による骨折の休業補償期間を弁護士が徹底解説|支給条件・申請の流れ・注意点まで
- 仕事中に熱中症になったら?労災申請と損害賠償請求について、令和7年6月法改正をもとに弁護士が解説
- 労災事故による足の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労働者が元請の会社に対して損害賠償請求できる?労災事故の責任と損害賠償を弁護士が解説